 |

| No.120 1998 10 |
| 科学技術庁 科学技術政策研究所 NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |
 |
| 目次 [Contents] |  |
Ⅰ.創立10周年記念国際コンファレンス特集 |
 |
Ⅱ.創立10周年記念シリ−ズ 政策研の思いで6 「政策科学への『煉獄』」 永田助教授 (北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科) |
|
 |
Ⅲ.トピックス 私と日本についてのこと ステイ−ブン・コリンズ特別研究員 |
|
 |
Ⅳ.研究会等紹介 技術貿易統計検討会の開催について 情報分析課 |
|
 |
Ⅴ.海外事情 欧州科学技術政策ワ−クショップ出席 佐藤所長 IMD訪問 藤原2研特別研究員海外出張報告 EPTA年次会議への出席 木場2調上席研究官海外出張報告 |
|
 |
Ⅵ.最近の動き |
|
当研究所は、創立10周年を記念した国際コンファレンスを「科学技術政策研究の新たな挑戦―グローバル知識社会を迎えて―」のテーマにより、平成10年10月8日から9日間の2日間、東京(星陵会館)で開催した。
本会議は、3部からなり、1部では「科学技術庁長官からのご挨拶及び井村科学技術会議議員による特別講演」、2部では「21世紀の社会展望」、3部では「科学技術政策の形成過程への貢献と今後の政策研究のあり方」についてという構成で行い、招待講演者11名を含む1国際機関、10カ国から合計322名(延べ420名)の方のご参加を頂いた。
第1部 竹山大臣のご挨拶と特別講演
主催者を代表して佐藤科学技術政策研究所長より開会挨拶を行った後、竹山大臣より次の要旨のご挨拶(表紙写真)を賜った。その後、井村科学技術会議議員よりの特別講演が行われた。
(司会:国谷 実 科学技術政策研究所総務研究官)
竹山 裕 国務大臣・科学技術庁長官ご挨拶の要旨
21世紀に直面する困難な課題の解決のためには、科学技術が大きな役割を果たしていく必要がある。科学技術創造立国のための政策の実現の基本となる政策研究に対する期待は大きい。今回のコンファレンスが21世紀の政策研究の発展の基礎となるような実り多いものになることを希望している。
井村 裕夫科学技術会議議員による特別講演要旨
テーマ:21世紀の科学技術 -生命科学を中心に-
科学と技術は、それぞれが別々の歴史をたどって発展してきたが19世紀後半から密接な関係になってきた。特に技術は、際限のない人間の欲望に基づいて発展してきた。現在の科学技術の重要分野としては、情報通信、バイオサイエンス、エネルギーの3分野があげられる。バイオサイエンスについては、個々の遺伝子機能の解明などにより、生物の進化、多様性などの生命の本質の解明を目指した研究が進んでいる。これらの研究の進展により、感染症の防止等の新しい診断及び治療技術の進展、人口増加に対応する食料生産技術の進展等が期待できる。21世紀は生物の世紀であり、生命に対する深い理解が必要である。このためバイオサイエンスを今後どのように発展させていくかが大きな課題である。
 |
 |
 |
 |
第2部 シンポジウム:21世紀の社会展望
「21世紀の社会展望」をテーマに、将来の科学技術政策を考えるにあたっての基礎となる将来の社会の展望について国内外の5名の有識者からの講演があった。さらにその後、講演者に対する質疑応答が行われた。(司会:榊原 清則 科学技術政策研究所総括主任研究官)
(1)Jerome Glenn(国連大学「これからの1000年プロジェクト」共同責任者、国連大学アメリカ評議会理事)
テーマ:これからの1000年
「これからの1000年プロジェクト」は、1994年に国連を中心として全世界的な規模で開始された未来研究であり、貧困の拡大、テロの凶悪化、情報技術の進展等の将来において予想される様々な可能性について、来世紀を展望する上で有益な指摘と提案を行っている。
(2)公文 俊平(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター所長)
テーマ:21世紀情報文明と科学技術
コンピュータの「2000年問題」を克服した後に我々を待ち受ける21世紀の情報社会においては、知識分野における新しいバランスが生まれ、"智民(Netizen)"が中心的な役割を果たすことになる。また社会的なインフラとして分散型のNetworkが構築されることが予想される。
(3)Marjory Blumenthal(米国国家研究会議コンピュータ科学・情報評議会理事)
テーマ:情報技術と社会の変容
情報技術(IT)の進展は、これまで我々が描いていた素朴なユートピア的な未来像に対して修正を迫ることになるだろう。ITの進歩は予想以上の速さで社会を変容させるとともに新たな不確実性をもたらしており、IT社会の意味合いそのものをも変化させている。
(4)橋爪 大三郎(東京工業大学教授)
テーマ:2010年の若者像
21世紀においては、科学の果たす役割がますます重要になると予想され、その担い手としてより多くの優秀な若者の出現が期待される。しかし諸外国に比べると、現行の日本の社会制度及び教育制度は硬直的で、若者の科学離れを一層深刻なものとしている。
(5)桑原 輝隆(科学技術政策研究所総括上席研究官)
テーマ:世界各国における技術予測への取組み
わが国の技術予測は1970年に開始されて以来、大きな成果をあげている。近年欧米諸国を含む世界各地で、技術予測の重要性が認識され、各国においても実施され始めている。今後の技術予測においてはそれぞれの国における特徴、社会の特性に配慮しつつ、従来の実施方法を再検討していくことが必要である。
 |
 |
 |
 |
第3部 ワークショップ:科学技術政策の形成過程への貢献と今後の政策研究のあり方
英国、米国、独国、仏国及び日本において政策形成、政策評価などに関与するそれぞれの機関の代表者から、機関の役割、機能等についての講演を行った後、パネルディスカションを行い、政策形成過程へのより最適な貢献等のための国際比較等の議論を行った。
(司会:平澤 冷 科学技術政策研究所総括主任研究官)
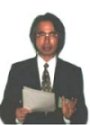 (1)平澤 冷(科学技術政策研究所総括主任研究官)
(1)平澤 冷(科学技術政策研究所総括主任研究官)
テーマ:導入講演
司会者からの導入講演として、今後10年間に
科学技術をとりまく社会状況についての第1日目
の議論のまとめが述べられた。続いて、科学技術
政策と他の政策との相違点、各国の科学技術政策
システムを比較研究するための枠組み等の議論の
ためのフレームが提出された。
 (2)Luke Georghiou(英国マンチェスター大学工学・科学・技術政策研究所長兼教授)
(2)Luke Georghiou(英国マンチェスター大学工学・科学・技術政策研究所長兼教授)
テーマ:英国における科学政策への助言とマンチェスター大学工学・科学・技術政策研究所(PREST)の役割
英国の研究資金の流れと特徴、省庁の構成、最
近の政策の傾向、政策形成支援機関の概要、及び
その一つであるPRESTの活動の具体例が紹介され
た。このPRESTの活動の具体例の中には、例えば
評価という文化を作っていったプロセスがふくま
れている。
 (3)Bruce Don(米国科学技術政策研究所長)
(3)Bruce Don(米国科学技術政策研究所長)
テーマ:米国における科学技術政策の改善のための支援ー分析において考慮すべきいくつかの将来の問題ー
科学技術政策研究所(旧Critical Technologies
Institute)の活動がどのように政策立案を改良、補
助するかについての具体的な報告がなされた。例え
ば、研究開発、健康、環境、宇宙開発、教育各分野
の政策分析をおこない、データベースを作成してい
る活動等が報告された。

(4)Winfried Benz(独国学術評議会事務局長)
テーマ:ドイツの科学政策と連邦及び州政府に対する助言におけるドイツ学術評議会の役割
ドイツのシステムの特徴(連邦政府と州政府の
並立的な関係)と大学および各協会ごとの研究所
運営の概要が紹介されたのち、学術評議会の活動
が紹介された。この機関は、1957年に設立され、
科学技術政策の諮問活動をおこなうカウンシルと
しては欧州で最も古い機関であると紹介された。
 (5)Alan Rodney(仏国教育・高等教育・研究・技術省 研究技術高等会議事務局長)
(5)Alan Rodney(仏国教育・高等教育・研究・技術省 研究技術高等会議事務局長)
テーマ:フランスにおける助言及び助言者の歴史
政策の支援および諮問というものの機能に関す
る考え方の説明があったあと、フランスの状況を
説明するための独自の分類軸(政策のレベルと時
間軸の2軸で構成される)をもとにフランスの各
機関の位置付けと今後の変化の分析が説明された。
(6)佐藤 征夫(科学技術政策研究所長)
テーマ:変わりつつある科学技術政策の枠組み
日本の科学技術政策の枠組みについて、科学技
術基本法、科学技術基本計画、中央省庁等改革基
本法等の最近の動向に触れつつ、科学技術会議の
約40年の活動を中心に説明があった。続いて、
国立研究機関の持つ研究実施と研究支援の二つの
機能についての考えが述べられた後、科学技術政
策研究所の使命及び機能についての説明が行われた。
パネルディスカッション
上記6名の講演者に、Don Kash 米国ジョージ・メーソン大学教授並びに丹羽
冨士雄 政策大学院大学教授が加わってパネルディスカッションが行われた。
Kash教授から「次世紀におけるNISTEPの役割とは何か」という問題提起がなされた。そしてこの問題を考える上での科学技術と情報化社会の未来についてのコメントが加えられたのち、「どうやって、予測できない対象をマネージしてゆくか」が今後の重要な課題であるとの提示があった。続いて丹羽教授より、政策内容分析、特に日本の科学技術会議の第11号答申を分析した例が紹介され、「各国における科学技術政策は総合的(comprehensive)になされているのか」という問いが提出された。さらに、政策内容の分析と政策システムの分析とを組み合わせることによって、政策支援を考える上での政策研究の枠組みが得られるのではないか、との問題提起がなされた。会場からは地域の科学技術政策のあり方、社会の意見を科学技術行政に反映するシステムのありかた、宗教も含めた各国の文化風土と科学技術政策の関係、などについての質問が提起され、それぞれについて、パネリストからの意見が提示がされた。なお全般的に、21世紀の科学技術政策、そのなかでの政策支援のあり方と科学技術政策研究所の役割について示唆の多い議論が行われた。

第4部 レセプション
第1日のシンポジウム終了後星陵会館内でレセプションが開かれた。
レセプションにおいては、竹山大臣がご挨拶に立たれ、創立10周年記念のお祝いの言葉を述べられ、続いて、岡村
総吾 政策研顧問(東京電機大学名誉学長)から乾杯の御発声を頂き、懇親会となった。創立10周年記念国際コンファレンスであるところから、近江元科学技術庁長官を初め多くの方々にご参加を賜り、これまでの国際会議の思い出や、将来の科学技術政策研究に話の花が咲いた。
 |
 |
 |
 |

| 政策研の思いで6 |
| 「政策科学への『煉獄』」 |

|
| 私は92年4月から6年間に亘って第1研究グループに在職いたしました。私が入所した当時の政策研では、村上健一所長の高遠なビジョンの下でいくつかの挑戦的なテーマが着手されており、その一つとして政府研究開発投資の経済効果に関する計測手法の検討も始められていました。些か経済学を勉強し研究人材の需給予測などを手掛けてきた私は、そのテーマを推進するために発足したグループ横断的なプロジェクト・チームに参加させて頂くうちに、マクロ経済モデルの応用を検討してみたいと考えるようになりました。経済学的な理論や方法を科学技術政策の研究に応用する過程で、私はしばしば大学に入ったばかりの頃に読んだマックス・ヴェーバーの翻訳書を思い出していました。最近、『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』として改訳版が出版されたその論文の中で、ヴェーバーは、経験科学は何をなすべきかを教えることはできず、何をなし得るかを教えられるに過ぎないと主張し、社会科学における認識を政策的な価値判断から峻別すべきであると説いています。このあまりにも有名な価値からの自由をめぐる議論に対しては、ハーバーマス以後の認識論の地平から多くの批判が行われてきました。しかし、行政機構の一環である組織の中で科学的な政策研究を志向する者にとって、科学と政策の緊張関係についてのヴェーバーの記述は、極めてアクチュアルな課題を言い当てていたのです。私は、科学技術への公共投資は持続的な成長に寄与するであろうという強い命題に励まされながら、一方ではこの命題が過剰にモデリングのための作業仮説に混入することを排除しなければなりませんでした。やや大仰となることに臆せず言えば、これは自らの科学観が試され、政策科学へと至る煉獄のような経験であったと思います。私の開発しようとした経済モデルは、在職中に漸くプロトタイプが完成し、政策研には現在その改良作業を継続して頂いています。私にとって何よりも幸いだったことは、在職期間を通じて、研究の自由を最大限に尊重して下さる二人の総括主任研究官にご指導頂けたことです。野中郁次郎先生には、組織論ないし戦略論的な視点に蒙を啓いて頂き、後藤晃先生には、イノベーション・プロセスに関する重要な国際比較研究のプロジェクトへと導いて頂きました。 私が政策研において何事かを学び得たとすれば、二人の師の手引きによるものであったと思われます。政策研が今後も若い研究者にとっての試みの場であり続けてくれることを願って止みません。 |
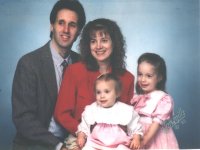
皆様、お世話になっております。私は米国のワシントン大学で教養学部の政治経済学助教授として日本の科学技術政策と経済歴史を専門に研究しております。佐藤所長のお陰様で今年9月から12月までの期間、STAフェローとして日本の地域における科学技術振興のため、変わりつつある政府と地方公共団体の連携のための枠組みを勉強しております。とりわけ、地域科学技術の政策形成過程における政府と地方公共団体の役割分担などのイノベーション・システムの視点から検証したいと思います。
今回NISTEPに来るのは初めてではなく、実際に初
めて来たのは、博士課程に入っているときに、日本の生命科学の歴史とバイオインダストリーを対象となる博士論文を研究していた1991年の秋でした。そのとき以来、殆どの研究員が変わっていますが、今回も皆様のご厚意で元気に研究することができ、確かに貴重な勉強となっています。
私の専門は日本の近代政治経済でありますが、以前には大学で科学工学部を専攻して工学士号を取得し、技術者としてPhilip
Morris社の社員になりました。5年間がたって、1988年には会社は、私に「日本風の品質管理」を身につけさせるためにW.Edwards
Demmingが設立した専門学校に私を派遣するようになりました。このことがきっかけとなり、私は日本についての勉強に没頭しはじめ、日々がたつにつれて日本の経済と技術ばかりではなく、文化、考え方および文学にも関心を持つようになりました。1年半がたたないうちに、「日本と東アジア」の経済歴史を専攻して大学院に入ることになりました。1994年に政治経済学と東アジア学(Political
Economy and East Agian Studies)というテーマで博士号を取得しました。歴史、政治、経済および文化は勿論日本語も一生懸命に勉強しました。しかし、日本語を勉強する学生たちの殆どとは違い、私は東洋漢字から始めて読み書きを熱心に学びました。こういうわけで漢字力が漸く向上し、新聞や専門雑誌などを読めるようになりましたが、子供が使う表現や擬声語などを聞いたり読んだりするときには、さっぱり分からなくなる場合もあります。日本語は外国人にとってはずいぶん難しいといわれていますが、私には漢字を読み書きすることは本当に心地のよいことです。
(S.コリンズ特別研究員は、日本語が堪能であり、本稿は氏が日本語で記述したものである。)
我が国には、技術貿易収支を取り扱った統計として、日本銀行「国際収支統計月報」、総務庁「科学技術研究調査報告」があるが、対象とする技術範囲、業種範囲等の違いから、技術貿易額が異なっており、我が国の技術貿易収支の決定を困難にしている。
この技術貿易収支については、技術に関する国際競争力を示す指標として社会的にも、学問的にも関心が高く、技術貿易収支額の推定は、極めて意義が大きい。技術貿易収支の推定については、知的所有権に関する最近の動向を踏まえ、対象とする技術を定義し、技術貿易収支の推定を行う。
なお、本調査研究については、専門家からなる技術貿易統計検討会(参考参照)を設置し、同検討会で議論を行いながら調査研究を進めていく。
総務庁「科学技術研究調査報告」、日本銀行「国際収支統計」については、利用目的の違いから技術貿易の対象となる業種、技術範囲が異なっている。
本調査研究では、技術貿易の対象とするべき技術の定義(ただし、既存の技術貿易統計との関係より分析可能な範囲で定義)を検討し、それに基づく技術貿易収支の推定法を構築する。特に、最近、取引件数が増えているソフトウエアに関する技術貿易額が増加しており、ソフトウエアが両統計でどのように扱われているかも検討する。
(参考)
技術貿易統計検討会
| 委員長 | 東京大学大学院総合文化研究科 | 廣松毅教授 |
| 委員 | 早稲田大学大学院アジア太平洋研究センター | 西村吉正教授 |
| 〃 | 東京大学先端科学技術研究センター | 玉井克哉教授 |
| 〃 | 早稲田大学社会科学部 | 浦田秀次郎教授 |
| 〃 | 麗澤大学国際経済学部 | 高橋三雄教授 |
| 〃 | 慶応義塾大学経済学部 | 木村福成助教授 |
| 〃 | 筑波大学社会工学系 | 椿広計助教授 |
| 〃 | 総務庁統計局統計調査部経済統計課 | 山内健生課長 |
| 〃 | 通商産業省大臣官房調査統計部企業統計課 | 丸山芳樹課長 |
| 〃 | 科学技術庁科学技術政策局調査課 | 加藤重治課長 |
| 〃 | 科学技術政策研究所情報分析課 | 吉水正義課長 |
| 〃 | 科学技術政策研究所第1調査研究グループ | 前澤祐一総括上席研究官 |
| 〃 | 科学技術政策研究所 | 丹羽冨士雄客員総括研究官 |
| 〃 | 科学技術政策研究所 | 清家彰敏客員研究官 |
| 〃 | 科学技術政策研究所 | 寺本義也客員研究官 |
9月18日(金)にウイーンに於いて開催された「European
Science andTechnology: Still in the Ivory
Tower?」と題する科学技術政策に関するワークショップに、スピーカーおよびパネリストとして参加する機会を得た。
このワークショップは、9月16日〜19日に開催された、第三回欧州国際関係論会議(主催:International
Studies Association、およびStanding Groupon
International Relations)の約80のセッションの一つとして特別に企画されたもので、ウイーンにある非営利学際研究機関ICCR(The
InterdisciplinaryCenter for Comparative Research
in the social Science)主催で行われ、冒頭にオーストリア科学・運輸省のKneucker局長より歓迎の挨拶があった。
本ワークショップは4つのセッションから構成され、講演中心のセッションとパネルディスカッション中心のセッションとが交互に行われた。講演者(8名)の勤務先所属国は、日本、米国、EU、フィンランド、オーストリアなどであり、様々な内容の講演が行われた。
筆者からは「Can Evaluation Be a Tool
for or Barrier to Innovation?」のテーマで、我が国における科学技術基本法制定以降の科学技術政策の動向について説明した後、政府関連機関の評価について、無機材質研究所、航空宇宙技術研究所、及び宇宙開発事業団を例に取り上げ、研究機関の使命と評価手法の相違等の事例を示すとともに、一般論として、イノベーションに影響を与える評価ファクターについて論じた。
米国MITのSkolnikoff教授からは、米国の基礎研究の実状として、必ずしも公的研究費は増えておらず、軍事研究費が減少し、産業も軸足を応用研究にシフトしつつある現状から、顕在化はしていないが基礎研究の弱体化を憂うなど、最近の状況について説明があった。
また、欧州委員会のGabolde氏のスピーチでは、欧州においては、国際的な協力と競争や異分野研究者の協力が新たなイノベーションをもたらしており、EU内外を含めた国々の協力の必要性が指摘された。
さらに、フィンランドTampere大学のKaukonen教授からは、国の規模が小さいため、政策とR&Dシステムをイノベーション志向に組み替え、通信技術などに特化した政策が成功を納めた事例などが紹介された。
このほか、科学技術政策での社会科学の役割などの講演があり、また、参加者の多くが社会科学系研究者だったためか、科学技術活動と社会との関係や、合意形成、民主性確保などの視点からのディスカッションが多かった。
議論の中で、本ワークショップの標題とは裏腹に、ヨーロッパにおける応用分野での科学技術推進の意欲を強く感じた。また、欧米とも「自国には一貫した科学技術政策がない」との見解が示され、どこでも同じ様な議論がなされていると興味深く感じた。
IMD(International Institute for Management
Development)はスイス連邦 ローザンヌ市に所在するビジネススクール・研究機関であり、45人の教授と33000人にのぼる卒業生、および50年以上の伝統を有している。同機関の名は国際競争力レポート(The
World Competitiveness Yearbook)の発行元としても知られている。今回、同機関を訪問する機会を得たので、同レポートの内容や調査方法などに関するディスカッションを行った。
同レポートは、世界主要46ヶ国の国際競争力を指標化して順位づけたものであり、我が国でも新聞などで比較的大きく報道されている。本レポートの日本に対する評価は、バブル経済崩壊以降、総合順位の下落傾向(94年3位→95年4位→96年4位→97年9位→98年18位)が続いている。分野別の順位では、科学技術分野が2位と健闘しているが、ほかにベストテンに食い込んでいる分野はなく、今年は金融と経営分野の順位が急落した。対照的に米国は過去5年間、総合首位を保ち続けている。
国際競争力の評価方法は、まず259の調査項目を設定し、これを統計データ及び質問票調査により数値評価し、統計処理により順位付けしている。調査項目は、国内経済、国際化、政府、金融、インフラ、経営、科学技術、国民の8分野に区分されており、総合順位のほか、分野別の国際競争力評価もできるように考慮されている。
調査項目は、統計データが2/3、質問票調査から得られるデータが1/3の比重を占めるように設定されている。各調査項目や質問調査の内容は、専門家から構成される委員会により毎年審査されており、世界情勢の変化に対応できるよう改善が図られている。
データの採取方法は、主に対象国に所在する協力機関(日本は電通総研)に入手を依頼している。質問票調査の方法は、各国に在住する評価者が自国の状況について、6段階評価で採点を行うものである。昨年度の場合、質問項目は87、回収数は約4000通であった。なお質問票を送付する評価者の選定は、各国の協力機関に一任されている。このように、データ採取における協力機関の役割は非常に重要なものと思われる。
こうした国際競争力レポートは、大規模かつ綿密な調査であるとの所感を持った一方で、順位はあくまでも一つの側面であり、評価にはその内容や評価手法などを精査する必要性も感じた。
例えば、質問票調査は評価者が上記8分野にわたる全質問に回答する形式となっており、評価者が全分野にわたる専門知識を有しているとは限らないので、専門性の観点から必ずしも厳密なものではない可能性がある。また、評価の1/3の比重を占める質問票調査方法によれば、自国の評価は主に自国民が行っている。従って近年の我が国の順位低下は、日本人自らが「自信喪失」して、自国の評価を貶めている側面もあろう。
このほか、我が国が比較的優れていると評価されている科学技術分野(2位)も、この高順位は、研究開発支出と研究者数、および特許出願が多いことに支えられている。しかし、例えば技術経営や研究環境の評価は12位と低く、弱点も内包していることに留意すべきと思われる。
1.概要
10月1日、2日にブリュッセルで、欧州議会の活動の一環であるEPTA(European
Parliamentary Technology Assessment)の年次会議に出席した。主催は欧州議会の一部であるSTOA(Scientific
and Technological Options Assessment)であった。EPTAはSTOAの他、議会に関連するテクノロジーアセスメント機関を持っている国からなっている。参加者は約60名。先月のデンマークにおける会議(EUROP(participatory)TA)と参加者が多少重なっていた。テーマは「倫理的文脈における技術選択:副題 技術と倫理、問題と解決の相互作用のケーススタディとしての議会のテクノロジーアセスメントのプロジェクトの例」というものであった。
2.会議の内容
全体としては、ライフサイエンスに関連する事柄と、コンセンサス会議のような市民参加指向のテクノロジーアセスメントと倫理を関係づけるような議論が割合多くなされた。倫理にはいくつかの視点があり、功利主義的倫理、宗教的・信条的な倫理、言説としての倫理などに区別されるという発言があった。言説としての倫理というのは、皆が平等であるという前提で適切な手続きによって話し合いがなされて、納得することによって得られるものである。テクノロジーアセスメントと倫理の関係を考えると、倫理とは功利主義的なものと考えられることが多いが、それだけではなく、言説としての倫理の編成もテクノロジーアセスメントの内容として重要なこともあるとの発言があった。そのような観点からすと、コンセンサス会議のような市民参加型テクノロジーアセスメントの手法がある程度有効と考えられるという発言があった。
3.出張者の発言内容
「日本におけるテクノロジーアセスメントと倫理」というテーマで話をした。その内容は、日本においては議会ではなく、政府がテクノロジーアセスメントを70年代に行ったこと、及び最近の科学技術に関連した事件として、オウム真理教のサリン事件、薬害エイズ事件があり、また、生命倫理の問題がクローズアップされていることなどから、科学技術と倫理の関係が問われる時代となっているが、そのような議論が未成熟であると述べた。
4.所感
科学技術と倫理というテーマは、ライフサイエンスの進歩に深く関連していると考えられる。新たな法律の制定をめぐって議論がされていることなど、欧州では科学技術と倫理が議会において具体的な問題になっていると感じた。規範形成の一つの手段として市民参加型・対話型アプローチが模索されているという状況であると感じた。科学技術と倫理という問題が日本よりは深化しているように見受けられた。

○ 海外出張
| ・8/31-9/6 | 木場第2調査研究グループ上席研究官(デンマーク) |
| ・9/16-9/21 | 佐藤所長(オーストリア) |
| ・9/16-9/24 | 藤原第2研究グループ特別研究員(オーストリア、スイス) |
| ・9/30-10/5 | 木場第2調査研究グループ上席研究官(ベルギー) |
科学技術政策研究所10周年記念国際コンファレンスも盛況裏に終了した。今回の参加者322人 は、今までの13回の国際コンファレンスの中でも記録的な数字で、文部省国立教育研究所などと共催した平成4年のシンポジウムについで多数の参加者であった。ご参集いただいた皆様にはこの場をかりて改めて御礼申し上げたい。特に今回は、コンファレンスの開会にも夜のレセプションにも竹山大臣にご出席いただいたほか、国会議員の方々をはじめ科学技術政策立案に当たる要職の方々にもご多忙中ご臨席いただき実のある政策実現に向けての国際会議になったと思っている。7月から始まった創立10周年行事も、記念式典、10年誌の刊行、今回の国際シンポジウムとほぼこれで終了し、これからは機関評価や中長期計画の策定など今後の10年に向けての種をまく仕事が始まることになる。社会が政策研に望んでいる仕事は何かを自問しつつ、かつ自ら先見性のある方向性を示しながら新しい社会の形成に向けて進んで行きたいと思う。(K)