

| No.117 1998 7 |
| 科学技術庁 科学技術政策研究所 NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |
科学技術政策研究所創立10周年記念特集

岡崎科学技術事務次官のご挨拶
| 目次 [Contents] |  |
創立10周年記念特集 |
| 1. 創立10周年記念式典 | ||
| 2. 創立10周年記念コンファレンス開催案内 | ||
| 3. 政策研の思い出1〜3(上原元総務研究官/尾藤元所長/平野元総括上席) |
||
 |
レポート紹介 Highlight of the New Report | |
| 1. 技術導入の動向分析 | ||
| 2. 公的資金による研究機関のあり方 |
||
 |
コラム Column | |
 |
最近の動き Current Topics | |
 |
編集後記 |
科学技術政策研究所は、昭和63年7月1日に創立され、本年7月1日で10周年を迎えた。これを記念して、7月1日昼前、当研究所内において科学技術政策研究所創立10周年記念式典を開催した。科学技術庁からは岡崎事務次官を初め官房・各局幹部、外部からは井村、石塚両科学技術会議議員、創立時以降の歴代事務次官、政策研歴代所長、研究所顧問、客員研究官、旧在職者等160名の方々にご参加を頂いた。
 式は、冒頭 佐藤 征夫政策研所長より「10年目の本年は、記念式典、機関評価、10周年記念誌の発行、さらに、10月開催予定の国際コンファレンスがある。今後の展開として、2001年発足の総合科学技術会議、教育科学技術省のより広い範囲の課題への対応を考える必要がある。このため、政策研への期待もますます高まるものと考えている。制約条件もあるが、国内及び海外の科学技術政策研究機関とのさらなる連携、より開かれた研究体制の整備、先見性を持った計画的な調査研究の推進など、マネジメント面を含めた新たな10年に向けて努力したい。」と挨拶があった。
式は、冒頭 佐藤 征夫政策研所長より「10年目の本年は、記念式典、機関評価、10周年記念誌の発行、さらに、10月開催予定の国際コンファレンスがある。今後の展開として、2001年発足の総合科学技術会議、教育科学技術省のより広い範囲の課題への対応を考える必要がある。このため、政策研への期待もますます高まるものと考えている。制約条件もあるが、国内及び海外の科学技術政策研究機関とのさらなる連携、より開かれた研究体制の整備、先見性を持った計画的な調査研究の推進など、マネジメント面を含めた新たな10年に向けて努力したい。」と挨拶があった。
次に政務のためご出席いただけなかった谷垣科学技術庁長官のご挨拶を岡崎事務次官が代読され、「我が国全体が閉塞状況に包まれている状況のなかで、社会システム全体の構築に向けて真剣な取り組みが求められている。こうした閉塞状況をうち破る科学技術の振興を、政府は限りない未来の夢を開く先行投資と位置づけている。21世紀を見据えた新しい社会資本の整備に重点が置かれ、将来の日本の姿を描く上で特に力が置かれたのが創造的科学技術政策行政体制の整備である。政府の研究開発投資の拡充を始め、魅力ある研究環境の実現、新産業の創出に向けてのベンチャー企業の育成や研究投資の及ぼす経済的効果の吟味等の検討に当たり、政策研究所は、この10年間に蓄積した能力を十分に活用し、政策部局と一体になって我が国の発展に貢献されることを希望する。」と述べられた。
引き続き岡崎事務次官ご自身のお言葉として、「行政基本法が成立し、行政改革に向けて全力で取り組んで参りたい。この行政改革から2つの視点を申し上げる。一点が創造的な科学技術行政体制の強化であり、総合科学技術会議や教育科学技術省の設置あるいは国の研究機関の再構築である。もう一点は中央省庁の政策企画立案機能の強化である。いずれにしてもこの中で政策研究所に対する期待は大変高まっていくものと思われる。これまで政策研の活動に協力を頂いた先輩諸先生方のさらなるお力添えを期待し、さらに、佐藤所長以下職員の一層のご活躍を期待する。」と付け加えられた。 さらに、来賓として、石塚
貢 議員より、「10年前の当研究所の発足は、私の科学技術政策局長就任と同時であり、思い出深い出来事である。10周年記念誌のアルバムを見ると、科学技術庁からは、現在衆議院議長の伊藤先生(当時科学技術庁長官)を初め、本日ご来席の内田事務次官(当時)、さらに政策研の川崎初代所長その他幹部と撮影した写真が載っていて、鮮明な記憶がある。
科学技術会議の議員として、日本の科学技術政策について総理大臣を始め、閣僚の方々と議論する機会が多い。理論的な研究に裏打ちされ、かつ、具体的な社会的ニーズに応えていくという、政策研特有の成果をこうした場に反映させていくことの必要性を強く感じている。」とご祝辞があった。
式典に引き続き、場所を改め、所内の懇親会場に移り、中原 恒雄
政策研顧問(住友電気工業株式会社副会長)による乾杯の御発声で懇親が始まった。創立時のご苦労や、政策研究などお話は尽きないものがあったが、ご多忙の皆様のご予定も考えて1時間あまりでお開きとなった。準備が十分行き届かなかった中で、盛況裏に式典及び懇親会を終えられたことに感謝申し上げる。

| 1. | テーマ: | 科学技術政策研究の役割と未来 |
| 2. | 開催日時: | 平成10年10月8日(木)〜9日(金) |
| 3. | 場 所: | 星陵会館ホール(東京都千代田区永田町2−16−2) |
| 4. | 開催趣旨: | 21世紀を目前に控え、我が国は、大競争時代への突入、高齢化・少子化社会への移行、環境、食料、エネルギー問題等、既存の経済社会システムでは適切な対応が困難な課題に直面しつつあります。本コンファレンスでは、このように日本社会の変革が求められる中での科学技術を取り巻く我が国社会の展望及び具体的な政策立案に結びつけていくための政策研究のアプローチに関する議論を行い、科学技術政策研究の今後の展望を示すことを目的にします。 (本コンファレンスは(財)つくば万博記念財団との共催である) |
| 5. | プログラム: | 本コンファレンスは、第1部から第3部までの3部構成とします。(入場無料)
|
| 政策に反映する調査研究を |
| 上原 哲 元総務研究官 (動燃事業団経営改革企画本部副部長代理) |
 昨年7月からわずか3ヶ月あまりで、政策研から現在の職場である動燃事業団に移り、ご迷惑をおかけしただけで申し訳なく思っております。 昨年7月からわずか3ヶ月あまりで、政策研から現在の職場である動燃事業団に移り、ご迷惑をおかけしただけで申し訳なく思っております。さて、私自身と政策研の係わり合いは、政策研の前身である資源調査所に勤務したことに始まります。申すまでもなく、当時の私たちのミッションは、資源調査所を改組し、科学技術政策に関する調査研究機関を設置することにありました。言葉を変えて申し上げますと、いわゆる昭和57年臨調に基づき、科学技術政策の企画、立案機能を強化するため、科学技術会議に政策委員会を設けたことをはじめ、行政内部部局についても科学技術政策局を設置するなどの体制整備は、既に1年前に終了しておりました。そして、唯一残された宿題が科学技術政策に関するシンクタンク機能の強化であり、既に一浪しており、どうしても二浪はしたくないという状況下にありました。 当時の資源調査所おいては、一浪した間に5グループのうち、2グループが実態的に科学技術政策研究を、他のグループが資源関係の調査研究を行っておりました。この結果、当時の最大の課題は、新たな調査研究機関をどのような構想のもとに設けるかということでありました。 この構想の具体化を図るため、「科学技術政策研究懇談会」でご議論いただく運びとなり、3ヶ月という短時間ではありましたが、精力的な検討の結果、報告書をとりまとめていただきました。 これを下敷きにして、科学技術政策研究所の組織や予算要求を行ったものであります。爾来10年を経過した現在においても、研究テーマについていろいろ変遷がありましたが、研究所の活動の基本的枠組みは変わっていないのではないかと思っております。 当時の活動の基本的な枠組みは、まず科学技術活動を構造的に捉えること、すなわち、経済のマクロ分析と同じよう科学技術活動のマクロの分析ができないかという点であり、もう一つが科学技術活動の動的に捉えること、すなわち、ある分野への科学技術投資というインプットに対し、アウトプットをどう捉えるかというミクロの分析ができないかという点を中心に考えました。具体的には、前者がカスケード構造を中心とした科学技術指標論であり、後者が技術融合論などを中心としたモデル論として考えられたと記憶しております。いずれにしろ、科学技術統計の不備や統計の持つ本来的な不確実性により、上記の課題を解明することは今後の問題であります。これを実際の政策に反映するにはさらに長い道のりを必要とすると考えられますが、初心忘れるべからずでがんばっていただきたいと考えております。 |
| 活力ある政策研への期待 |
| 尾藤 隆 元所長 (関西学院大学教授) |
 政策研では総務研究官と所長として2度勤務した。所長としては期間が短く、いささかも貢献することが出来なかった感がある。一方、総務研究官として転任した年は、政策研が発足して1年たとうとしていたころで、川崎所長が陣頭に立って指揮を執っており、児玉、丹羽両氏が常勤の総括主任研究官として配下の研究員を叱咤指導し、全員が意欲的に課題に取り組み、大変に活気がみなぎっていた様子が思い出される。改めてそのころの活気ある状況につき感じたことを述べてみるのも、これから政策研を発展させていく方たちへの何らかの参考になるかもしれない。 政策研では総務研究官と所長として2度勤務した。所長としては期間が短く、いささかも貢献することが出来なかった感がある。一方、総務研究官として転任した年は、政策研が発足して1年たとうとしていたころで、川崎所長が陣頭に立って指揮を執っており、児玉、丹羽両氏が常勤の総括主任研究官として配下の研究員を叱咤指導し、全員が意欲的に課題に取り組み、大変に活気がみなぎっていた様子が思い出される。改めてそのころの活気ある状況につき感じたことを述べてみるのも、これから政策研を発展させていく方たちへの何らかの参考になるかもしれない。当時は、科学技術政策という言葉はあってもその意味するところは人様々。 科学技術発展メカニズムの中身はブラックボックスで、経験則をこつこつ築く努力の段階。 優先研究開発分野の選定は政府にとって重要な事項であるが、先を見通すいわゆる事前評価のための合理的な手法は確立されておらず、結局、専門家集団のコンセンサスや意見の積み上げ及び上からの裁きという政治的決定プロセスに依存せざるを得ない。 それ故に、政策研という政策立案のために直接係わる研究活動を行う機関が求められ、これは当時先進国共通の課題であったと思う。 そのような大きな課題に対応するには、限られた資源しか持たない政策研では限界があるが、政策研は当初から意欲的姿勢で、基本問題であって当面の成果は期待できないが先行き展開の期待が大きいテーマへ優先的に取り組んでいた。すなわち、科学技術と経済成長との関係、企業レベル、世界レベルの技術革新メカニズム、人材問題、先端技術のパブリックアクセプタンス等である。 また、科学技術指標、技術動向調査、技術予測、情報収集と整理及びその電子化等の支援システム等、研究用の道具の開発に長期的視点に立って取り組んでいた。研究所の活力は内外からの訪問者の数で計ることが出来る。 情報発信無くして情報収集出来ず、であるので、政策研は当初からCOEを指向していた。従って政策研では、基本ポリシーとして、国内よりも海外を相手に成果を問おうとしていた。 当時は現在とは反対で日本の経済は上り坂。 経済の強さは日本の製造業の国際競争力の強さにあると見なされ、「その秘密は何か。」と、欧米先進国での日本への関心は高かった。 多数の海外専門家の招聘と講演会、郊外のホテルに缶づめになっての国際シンポジウム。いづれも盛会で思い出深い。 科学技術政策という分野そのものが国際的にも新しい分野として注目された時期に当たり、国内でも産業界を中心に関心が高かった。 政策研のシンポジウムが事実上の最初の国際学会のような役割を果たし、政策研自ら、この分野の国際ネットワークの要になるべく意識的にリードしようとしていた。 そのためには、政策研自体の研究能力向上が肝要である。しかし、この分野の国内専門家の数は少ない。 対応としては、この分野に関心の高い学界や産業界の人々の国内ネットワークを創成し、外部の研究能力を効率的に活用していくこと。 一方、研究所内部では、役人出向者も管理者でなく一騎当千の研究者としての気概が求められ、一人一台のパソコンがあてがわれて文書作成やコピーは自ら行うこと。 一人1年に最低一つの印刷物での成果。実績は難しかったが各員必死に努力していた。当時政策研では、科学技術会議の答申案や科学技術白書の作成に貢献する事を希望していた。 他の自然科学系の研究機関と異なり政策を扱う政策研にとって、そのことは研究所を生かす道だからである。そのため当時の科学技術会議第18号答申に関して、所内に臨時の組織を作って作業を行ったが、残念ながら能力不足で貢献出来なかった。答申や白書の作成は、事務局である本庁の責任事項である。その本庁は政策研をどのように活用すべきだろうか。 当時の経験では、本庁が必要とするデータ、資料、情報を、求めに応じて提供しさえすればよいという空気だったかと思われる。政策研は研究所なのか調査下請け機関なのか。 政策研としても、本来の研究テーマの追求の片手間にそれらが出来ることなのか。傘下の研究機関を生かすも殺すも本庁次第で、本庁に長期的視点に立って先手を打っていく政策研の育成指導の戦略が求められる。 このため、そのときそのときの白書や答申のテーマについて、本庁と政策研との間で共同作業グループを作ってブレーンストーミングを行う慣習を確立し、実際の白書や答申案の作成において政策研の外部研究者ネットワーク活用を円滑にする工夫をしていったらどうだろうか。 国民へのビジョンと指針の提示を役割とする答申や白書は、長期的視点や現実と課題の正確な把握と説得力ある対応策を持つことによって、責任官庁にオーソリティを確立させる。時間がかかっても少しづつ、本庁、政策研間の作業リンケージが形成されることを期待している。 |
| 創立時の雰囲気 |
| 平野 千博 元総括上席研究官 (岩手県立大学総合政策学部教授) |
 このたび、科学技術政策研究所が創立10周年を迎えられたことについて、心よりお祝いを申し上げます。 このたび、科学技術政策研究所が創立10周年を迎えられたことについて、心よりお祝いを申し上げます。策研が発足した当時、私は、科学技術庁の原子力安全局におりました。このため、私自身が政策研の設立に直接関わったわけではありませんが、政策研が全庁の期待と注目の中で船出したこと、そして、私自身、政策研の発足を非常にうれしく感じたことは良く覚えています。何と言っても、当時は、政策研究機関の設立は、政策立案能力の向上をめざしていた科学技術庁にとっての全庁的な悲願となっていたのです。 策研の発足から半年ほどたった平成元年2月、私は、縁あって政策研の一員となることができました。その後、平成4年の秋まで3年半にわたって政策研のお世話になったのですが、もともと科学技術政策の基本論に興味があったこともあって、非常に楽しく仕事をさせて頂き、今でも良い思い出になっています。 私が政策研で頂いた仕事は、第1調査研究グループの総括でした。前任者は、林光夫氏です。私が着任したときの第1調査研究グループは、林前総括上席研究官の指導の下、科学技術人材、科学技術政策史などの課題に取り組んでいました。特に、科学技術人材に関する調査研究は、その後、科学技術政策の新しい柱のひとつとなって、科学技術会議の第20号答申や科学技術振興事業団の理解増進事業の発足につながっていくことになります。私の最初の仕事は、これらの研究課題を引き継いでグループの皆さんと一緒に仕上げに取り組むことでした。研究は、テーマを考えるところが最も神経を使うステップですので、とにかく既に進行中の研究課題があり、それに全力をあげれば仕事になるという状況は、肉体的にはともかく、精神的にはかなり楽なスタートだったと思います。 私が着任した当時の政策研には、川崎所長、鈴木総務研究官、上原企画課長、大学から来られた児玉・丹羽両総括主任研究官といった議論好きの方々がおられ、ほとんど毎日どこかで大議論が行われているという活発な雰囲気でした。私も、新参者ながら、時折はこれらの議論に参加させていただき、いろいろ仕事上のヒントを頂いたものです。 また、当時の政策研の国際的な雰囲気も、私にとっては、とても新鮮でした。英国のダイアナ・ヒックス女史、米国のジャニス・キャシディ女史、ジェラルド・ハネ氏など、多彩な外国人研究者が政策研に参加し、彼らの独特な物の見方、議論の仕方、仕事のやり方、頑張り、電子メールに代表される新技術の利用などの全てが我々日本人研究者にとって良い刺激となっていました。中でも、ハネ氏は、後に私が日本原子力研究所の職員としてワシントンに駐在しているときに、ホワイトハウスの科学技術政策局(OSTP)スタッフとして私を助けてくれることになった人です。当時は、ワシントンで再び彼と出会うとは全く想像もしていなかったわけで、不思議な縁を感じたものでした。 政策研には、科学技術庁本庁とは別種の活気があったように思います。こんな世界もあるかと感激して、成果を世に問い、反響を楽しむという生活に浸っているうちに、あっという間に3年半が過ぎてしまったように感じています。私は、政策研を離れてから、調査課長として科学技術白書のとりまとめに当たったり、前述のようにワシントンに駐在して米国の科学技術行政の動きを追う仕事に携わったりした後、この4月から、岩手県立大学総合政策学部に勤めているわけですが、これらの仕事全てにわたって、政策研での経験が役に立ち、私を支えてくれたと思っております。 現在の職場で、私は、久しぶりに科学技術政策研究に取り組むことになりました。ここでも、政策研での経験を生かし、おもしろいことをやってみたいと思っております。特に、この6月からは、所長、総務研究官を始めとする皆様のご好意により政策研の客員研究官を拝命させて頂きました。これからは、政策研に頻繁にお邪魔し、昔のように議論に参加させて頂いて、大学での仕事にも役立つようなヒントを得たいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 政策研は、最近においても、技術予測や科学技術指標など様々な分野で立派な成果を上げられており、また、今年に入ってからは政策研自身の研究評価についても積極的に取り組まれていると伺っております。このようにダイナミックに変化していく諸情勢に積極的に対応していく姿勢は、政策研の健在を示すものと拝見しております。 私は、政策研の重要な任務のひとつは、既成の観念にとらわれることなく、科学技術政策に関わる新しい見方や大胆なアイデアを積極的に世に問い、科学技術政策に関する議論の輪を拡げていくことにあると思っております。このような意味で、政策研には、最初の10年間の野心的な取り組みにより勝ち取られた高い評価と国際的な名声に安住されることなく、これからもアグレッシブな政策研であり続け、科学技術政策に関する建設的な議論を巻き起こしていく役割を果たして頂くようお願いして、筆を置きたいと思います。 |
Ⅱ.レポート紹介 Highlight of the New Report
本調査は、「外国為替及び外国貿易管理法」による技術導入契約の締結(変更)に関する報告書等に基づき、我が国における平成8年度(平成8年4月1日〜平成9年3月31日)の外国からの技術導入3,145件の実績を取りまとめるとともに、最近における技術導入の動向分析を行っている。ここ数年の特徴的事項をいくつか挙げると、
である。
《新規技術導入件数》
新規技術導入件数は3,145件で、前年度に比べ19%(
756件)の減少であるが、例外的な特定の商標の分を除くと2,980件で若干の減少である。
技術形態別(ハード系技術、ソフトウェア、商標のみ)では、「ソフトウェア」が1,621件で、ほぼ横ばいとなっており、「ハード系技術」は、
1,051件で若干減少(6.5%)している。

《国別導入件数》
国別では、米国からの導入が1,902件で全体の6割を占めているが、ハード系技術は前年度に比べ、1割以上減少(13.3%)している。
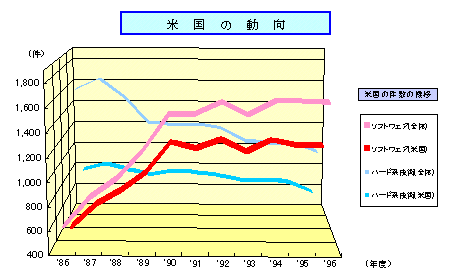
《資本金規模別導入件数》
技術形態別に導入企業の資本金規模をみると、ハード系技術では、ここ数年減少傾向であるのに対し、ソフトウエアでは、資本金100億円以上の企業の導入が、ここ数年大きく増加している。
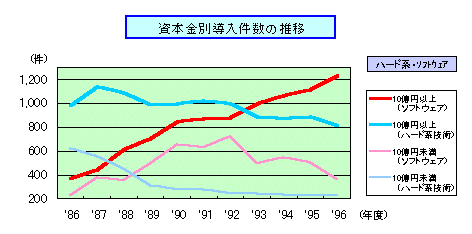
《技術形態別権利取得件数》
技術形態別権利取得状況については、権利(独占権または再実施権)を伴った導入が、ソフトウェアでは減少に転じ、ハード系技術では、若干増加している。
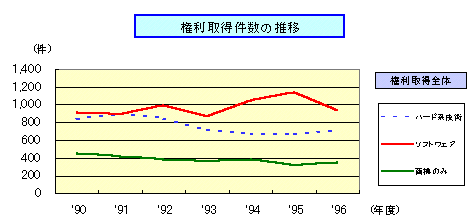
設置形態 英国のリサーチ・カウンシル傘下の研究所や独国のマックスプランク、フラウンホーファー、ヘルムホルツ等の研究所群は、いずれも法人格を有し国立(政府の内部組織)ではない。これらの研究所は、いわゆるscience-baseの各省横断的な研究を担当する研究所であり、この他に各省のミッションに特化した研究を担当する国立の直轄研がある。英国における研究所のエイジェンシー化は、この部分を対象としたものである。フランスの場合、公的資金に依存する研究所の大部分は公施設と位置づけられ、政府の内部組織ではない。そのうち、大学と病院の研究強化を各々の使命とする巨大研究組織CNRSとINSERM(予算ベースで研究機関全体の約45%)が横断型研究所に相当する。米国では民生技術分野の2/3に当たるGOCO(government
owned contractor operated、国有民営)型研究所は国有ではあるが大学や民間企業にその運営が委ねられていて、政府の内部組織ではない(非公務員)。米国の残りの国立研究所は、全体のほぼ2/3に相当し、軍事関連および市民サービス(健康・医療を担当するNIH等)を目的とした研究部門を担当するGOGO(government
owned government operated、国有国営)型研究所で、これらは直轄研に相当する。科学技術のフロンティアを開拓する研究は、巨大施設を必要とする例外的な分野を除いて研究所を設置せず、公的資金は大学を中心にしてファンドの形式で提供されている。このように研究の質に応じてそれを担う研究機関の設置形態や運営方式に、様々な工夫が凝らされている。
組織の構成原理 欧州主要国では、公的研究所は先ずscienceやresearchの基盤を担う横断的な研究所群と各省のミッションに特化した研究所群に大きく2分されている。これに対し米国では横断型研究所は置かず、NASAのようなリサーチ・エイジェンシーを含め各省毎にその目的別に研究所群が付設されている。欧州主要国の横断型研究所群は、英国では研究分野毎に大括りされ、さらにその内部が研究の専門分野毎に階層的に細分化されているが、独国では、基礎、応用、大型等の研究特性毎に大括りされた後、その内部が研究分野や目的毎に細分化されている。フランスの横断型研究所は対象組織別に2分されているが、その下で研究分野毎に階層別に細分化されている。このように、研究所群の組織構成の区分原理は、目的、研究分野、研究特性がそれぞれ組み合わされて採用されているが、第1
原理を何にするかで、各国の特徴が表れている。各区分原理には、それぞれ長所と短所があり、研究の効率的な運営と区分領域の長期的な展開とに配慮し区分原理のベストミックスを設計する必要がある。
行政組織と研究組織の関係 政策の企画立案を担う行政組織と研究を実施する研究機関との間には、通常多様な中間組織が配置され、政策の執行を担うと共に、研究現場の知識を政策形成に反映させる役割も果たしている。米国では“research
and policy community”がリサーチ・エイジェンシーの内部各層から政権中枢部、さらには議会スタッフまでを占めていて、彼等の手により研究機関毎に作成される「戦略計画」が多様なメカニズムを経て省庁レベルの「戦略計画」として統合される。米国の場合は、NASAやNSFがそうであるように、それぞれのリサーチ・エイジェンシーや省が独立した組織としての中間機構を持つのではなく、通常政策形成と執行を一体的に担っている。英国では、リサーチ・カウンシルが政府と研究機関を相互に媒介する中間組織と位置づけられる。また、統合的プログラムに対してはOST事務局の一部もその機能を担っている。独国では、大括りされた研究所(例えばマックスプランク研究所)全体の運営事務局(マックスプランク協会)、ファンディング機関、プロジェクトエイジェンシー等機能の異なるいくつかの中間組織がある。これらは、政策立案機関の下請け機関ではなく、英国の場合では契約に基づき、また独国の場合では“信頼”に基づき権限委譲された執行機関であると位置づけられている。研究開発の効果的な運用は、科学技術と政策の両面を熟知したパブリック・マネジメントを専門とするテクノクラートを配置したこれら中間機構の能力と活力にかかっている。残念ながら我が国は、このような機能が未分化のまま行政府内部に包含されていて、2年毎の定期移動によりそのマネジメント・スキルの定着が著しく阻害されている。一方で、資金配分等の執行を行う機関は、省庁の下請け機関と位置づけられテクノクラートが育成される環境にはない。研究機関の再編と共に、この中間機構の多様化と強化を図ることも必要である。
科学技術政策研究所は創立10周年記念行事の一環として「新世紀の深みのある政策展開を目指して」と題し、当研究所としては初めての通史を編纂し刊行した。内容は、研究所の10年の活動を通覧するとともに科学技術政策研究の将来展望にも目を向けたものとしており、10周年企画委員会が企画・編集した。
冒頭、佐藤所長、谷垣科学技術庁長官の挨拶と、内田元事務次官、川崎初代政策研所長の祝辞を置く。本文は「研究所の10年と今後」と題し、3部構成となっている。第1部は「21世紀の科学技術政策」で、吉川日本学術会議会長、Meyer-Krahmerフラウンホーファー協会ISI所長に広い視野から21世紀の科学技術政策について書き下ろして頂いた論文を掲載(要旨は以下に掲載)。第2部は「10年間の研究成果と将来展望」で、海外の科学技術政策研究機関の代表者及び政策研に在籍した大学研究者の回想と各分野毎の研究成果のとりまとめと展望。第3部は「創立10周年に思うこと」で、政策研創設に当たりご尽力頂いた方々の回想となっている。
このほか関連資料も豊富に収録し、また、国立試験研究機関の年誌にしては珍しく全てに英文対訳をつけ、政策研の活動を広く海外にも示す体裁をとった。本誌は10周年記念式典のご列席者にお配りするとともに、政策研究に関する機関にも送付している。すでに政策研の新入職員に対する教育の用にも当てており、今後広く活用を図って行くつもりである。ご一読いただきたい。
「英国出張記」
第1研究グループ総括主任研究官 榊原 清則
私はこの5月に英国を訪問した。訪問の主目的は、英国王立協会(The
Royal Society)の招待 に基づき、「天皇陛下へのチャールズ二世メダル授与式およびレセプション」に参列することであった。またその出張の折りに、マンチェスター大学とサセックス大学にも立ち寄った。
5月28日にロンドン王立協会にてメダル授与式があった。メダルは「チャールズ二世メダル」といって、「国家元首クラスの人で、かつ科学者として顕著な業績を上げた」人を対象とし、きわめて例外的に贈られるものである。英国王立協会は1660年に設立されたが、当時の国王チャールズ二世がその設立に深く関わっていたことから、その名前がメダルに冠されている。
メダル授与式には、日英の約100名ほどの科学者が参列した。まず会長(Sir
Aaron Klug)から挨拶があり、王立協会の歴史とメダルの説明が行われた。次に協会側から、日英の科学交流の歴史、天皇陛下ご自身の科学的業績の説明があり、そしてメダルが授与された。それに答えて、天皇陛下の御答辞および御記帳が行われた。最後に、ダイニングルームに全員が移って、天皇、皇后両陛下が日英の科学者と一時間ほど御懇談を行った。
この会に参列した感想として、第一に、イギリスの科学者が天皇陛下のご研究に科学的好奇心をもち、その内容を高く評価していること、第二に、天皇陛下ご自身も、このメダル受賞を科学者として率直に喜んでおられることを、感じとることができた。
次に、マンチェスター大学のPRESTで、所長のLuke
Georghiou、所員のDenis Loveridgeおよび Hugh
Cameronの合計三名と面談した。Luke Georghiouについては説明を要しまい。Denis
Loveridgeは化学者で、民間企業での経験が長く、いま技術を基盤とするベンチャー企業の実態調査をしている。Hugh
Cameronは評価および知的財産権の専門家である。
最後に、サセックス大学SPRUでは所長のBen
Martin、所員のKeith Pavitt、David Gannを含む多くの教職員・学生と面談した。私が訪問した日に、たまたま大学院博士課程学生の研究発表会が開かれていた。参加者のなかにはアメリカ、イタリア、オランダ、デンマーク、ドイツ、ベルギーからやって来た学生もおり、もちろんSPRU自身の学生にも様々な国籍のものが含まれているので、発表会は国際色豊かであった。発表自体のレベルは様々だったけれど、参加者構成の国際性を反映して、問題意識やテーマ、調査方法が実に多様である点が印象的だった。
○ 講演会等
| ・6/2 | 「韓国新政権下での科学技術関係政策の展開」 崔 享變(韓国科学技術協会総連合会長) |
| ・6/8 | 「イノベーションの3類型企業戦略と公共政策への示唆」 Pref. Don E Kash |
| ・6/29 | 「情報科学技術の高度化と法的対応」 堀部 政男(中央大学法学部教授) |
○ 人事往来
| ・ | 6月30日付けで、根本光宏企画課長が科学技術振興局研究基盤課地域科学技術振興企画官に転出し、後任には植田昭彦航空宇宙技術研究所企画室総括研究企画官が就任しました。 |
○ 海外出張
| ・6/10-17 | 古賀第1研究グループ研究員(オーストリア) 後藤客員総括研究官 |
| ・6/14-19 | 富澤第2研究グループ主任研究官(仏国) |
今月で、政策研も10周年を迎えた。政府機関で10年といえば、まだ新しい方で、本年は、50周年を迎えた機関もあった程である。ただ、次の10年を考えた時、色々な意味で考えさせられる。まず、行政改革により、科学技術行政体制が、新たなシステムに変更されることである。また、新たな世紀、新たなミレニアム(千年期)を迎え、様々な意味で社会が大きく変化するのではとの予感がある。次の10年は、霧の深い大海に漕ぎ出していくようなものかもしれない。従って、羅針盤ともいうべき政策科学研究の重要性がいよいよ増していくだろう。身の引き締まる思いである。次の10年の政策研の活動が、科学技術政策にとっても実りの多いものであることを、切に願うばかりである。
7月号の10周年記念号は、いかがだったであろうか。本号より、編集スタイルを一新してみた。今後も、読者に適時適確な情報を提供していきたい。(T)