




| No.116 1998 6 |
| 科学技術庁 科学技術政策研究所
NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |
| 目次 [Contents] |
 | レポート紹介 Highlight of the New Report |
 | 研究会等紹介 Research Meeting | |
 | コラム Column | |
 | 最近の動き Current Topics |
Ⅰ.レポート紹介/Highlight of the New Report
第1調査研究グループ
吉田 通治 神田 由美子 前澤 祐一
1. はじめに
1.1 調査目的
現在の日本における大学の学部のほとんどは、文系・理系のどちらかに分類され、またさらに各々が細分化されている。これらの専門指向型の学部は、学部間・学科間の壁が非常に高く、他の学部・学科の講義を受けることは非常に困難である。また最近では、この細分化(専門化)がさらに進んでいく傾向にある。
一方で、最近起こっている社会問題(環境問題、高齢化問題、臓器移植問題等)は、1つの専門分野の専門家では解決することは出来ない、様々な分野の要因が複雑に絡み合った大変難しいものとなっている。これらの問題を今後解決していくには、ある一つの専門分野の領域にとらわれない幅広い視野を持った人材の育成・活用や、各専門分野の専門家達による共同研究等が必要不可欠である。
また、日本の大学では4,5年前から大きな変革の波が押し寄せている。それは、これまでの日本の大学の伝統であった縦割り構造をうち破る、学際的な学部が増加してきているのである。つまり、これまでの理系・文系の専門学部とは違う、また文理学部とも違った、文系・理系の枠を越えた新しい構想の学部である(以後、これらの学部を「新構想型学部」と称する)。
これまで、「科学技術人材=理系の人材」という図式が成り立ってきた。しかし、社会と科学技術との関わり合いが、今後より一層密接になってくると考えられ、また、社会がこのように大きく様変わりしてきていることから、この図式が成り立たなくなってきている。従って、今後はこれらの新しいタイプの人材が、新たな科学技術人材として大きく期待されている。
しかし、現在のところ新構想型という定義はない。また、各大学のこのような新設学部における新たな試みの実態や、特色、学生の卒業後の進路等についてはよく把握されていないのが現状である。
そこで、本報告は、いくつかの大学の新構想型学部における状況や実態について、統計やインタビューを用いて調査を行ったものである。
1.2 調査内容
本報告書は、
1)「文部省 学校基本調査報告」による、学部入学志願者数、学部入学者数等の統計データと、
2)実際にいくつかの大学を訪問して行った、学部の実態に関するインタビュー調査を行った結果の報告である。
新構想型学部とは何か
学際化が成立するには、その前提として確立された学問の専門分野が必要である。従って、学際化とは、既存の学問の専門分野を相互に関連づけることである。しかし、学問の学際化といってもその手法は様々である。その中で、いま日本の大学が取り組んでいる学際化の手法は大きく分けると、マルチディシプリナリ(Multi-disciplinary)とインターディシプリナリ(Inter-disciplinary)の2つに分けられる。
ここで、マルチディシプリナリとは、複数の学問の専門分野を学生が学び、学生自身の中で融合されるものである(図1−1(A)参照)。また、インターディシプリナリとは、複数の学問の専門分野が相互作用し、新しい構造の知識体系の構築がなされたもの(融合されたもの)を、学生が学ぶものと考える(図1−1(B)参照)。
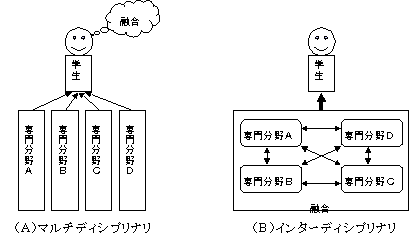
最近、新設される学際的な学部や、新たな学部としての試みとして行われている学際化の多くは、マルチディシプリナリの手法であり、主として文系の専門分野と理系の専門分野が複合している。従って、本報告で扱う新構想型学部は、マルチディシプリナリの手法で学際化の試みを行っている学部に限定する。
新構想型学部の選定
新構想型学部を持つ国公立大学と私立大学の大学および学部名は、「文部省 学校基本調査報告書」より、日本の大学の全学部名の中から、既存の専門学部の名称には現れることのない、総合、人間、情報・コミュニケーション、環境をキーワードに持つ学部を抽出し、学部設立の経緯や教育理念等から選定した、49大学52学部である。「文部省 学校基本調査報告」では、これらの新しいタイプの学部は既存の学問分野の中に組み入れて計上しているので、個別に集計する以外にこれらの学部の統計は存在しない。従って、本調査では選定した学部をもとに「文部省 学校基本調査報告」を用いて集計を行った。ただし、同名の学部の中には新構想型学部に該当しない学部も存在するが、統計上これらの学部も含まれるとする。また、逆に名称の上では既存型学部に分類されるが、内容的には学際的な学部も存在する。しかし、それらの学部は今回の調査から除外されている。このカテゴリーの代表的なものは教養学部である。また、理学部や工学部でも部分的には学際化現象が見られる。これらの学部の解明には、学科ないし専攻レベルでより詳しく見ていく必要がある。
訪問大学はこの中から、学部から卒業生がでている(又はでる)事を条件として、7校8学部を選定した。
2.調査結果の概要および考察
文部省「学校基本調査報告」による統計、および各大学におけるインタビュー調査の結果から、日本の新構想型学部の現時点における実態は、以下の通りである。
| ・ | 最近新設されている学部は、1991年6月の文部省における「大学設置基準等の大綱化」に伴い、既存の教養部の改組や現在の社会問題に対応できる人材の育成を目的に誕生している(新構想型学部のなかで、1992年度以降に新設された学部の割合は74%である)。これらの新設学部の多くは、学際的な学部であり、学際化の手法はマルチディシプリナリである。 |
| ・ | 新構想型学部は、大きく分けて総合系学部、人間系学部、情報・コミュニケーション系学部、 環境系学部の4つに分類することができる。 |
| ・ | 新構想型学部の新設が各大学で相次いでおり、必然的にその入学志願者数、入学者数の絶対数は増加傾向にある。特に、総合系学部、人間系学部、情報・コミュニケーション系学部の増加率が大きい。既存の専門学部である理・工学部においては、ほぼ横ばいである。 |
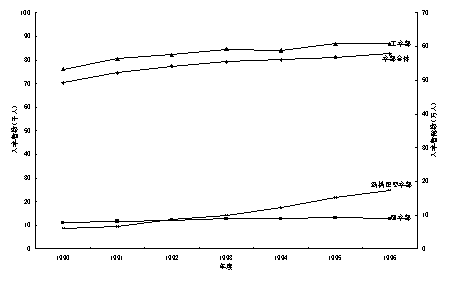
| ・ | 新構想型学部に対する女子学生の人気は、既存の専門学部である理学部や工学部と比較すると断然高い。新構想型学部の入学者に占める女子の割合は約40%であり、理・工学部は10%前後である。しかし、女子割合の値は新構想型学部の方が多いものの、過去7年間における増加率の伸びは理・工学部の方が大きい。 |
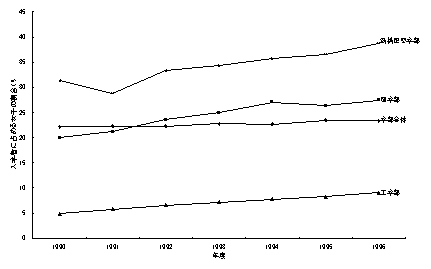
| ・ | 新構想型学部の入学倍率は、どの学部も新設された初年度の値は高い傾向にあり、その後徐々に落ち着くため、7年間の経過を見ると減少傾向になりがちである。しかし、新構想型学部の値の方が、既存の専門学部である理学部や工学部の値と比較すると高い。 |
| ・ | 新構想型学部の学際の試みには3つある。 |
| ・ | 新構想型学部の大きな利点は、入学してから自分の進路について意志決定が出来るところである。しかし反面、意志決定が出来ない学生には、この利点が不利になることもある。 |
| ・ | 新構想型学部の卒業生の中で就職を希望する学生は、自分の進路について意志決定が出来ている場合が多いので、企業の規模や名前にこだわることなく、自分のやりたいことが出来る分野への就職が決定している学生が多い。しかし、就職活動時に学部の社会的認知度の低さや企業の既存の文系・理系といった縦割り構造の残存により、不利を被っている学生もいる。 |
| ・ | 新構想型学部は、文系・理系の学科の講義を相互に受けることが可能なカリキュラム構成にすることにより、マルチディシプリナリによる学際教育を行っている。インターディシプリナリという、1つの学部で学際の理念に基づいた教育を行う手法もあるが、このような複合領域の教育が行える教授自体まだ極めて少数であり、今後これらの専門家を増加させていくために、早期の体制の整備・拡充が望まれる。 |
| ・ | 新しい試みの学部であるため、様々なミスマッチが学部と学生の間で生じる場合がある。この場合、学部側ではなるべく多くの学生に学部の理念を理解してもらい、学んでもらうために、いろいろな対応策を講じて学生に対応している。 |
| ・ | 学際という新しい領域の学問をどのように今後発展させていくかという事を、各学部で試行錯誤している。それは、新構想型学部自体の独自性を強調していくことでもあるが、大学院を含めた教育・研究体制の早期確立が大きな課題である。 |
| ・ | 学部段階の学際には、主にマルチディシプリナリとインターディシプナリの手法がある。マルチディシプリナリの利点は、学生自身に学ぶ学問の選択肢があり、意志決定が出来ることである。インターディシプリナリは、新しい体系の学問分野を学ぶ場であるので、その時点で既存の専門分野と変わらないということになり、マルチディシプリナリの利点である学生の自由度は失われてしまう恐れがある。 |
これらのことから、新構想型学部とは、まだ出来て間もない学際領域を学ぶ場所であり、新しいが故に様々な問題を抱えているのが実状である。しかし、いま起こっている学際領域の社会問題を解決する上で、これらの知識を持つ人材の育成は必須である。また、大学入学までの受験戦争を乗り切ったあとに、自分を見つめ直す時間がもてることは、個人の個性をより伸ばすことができ、新構想型学部の大きな利点の1つである。
このように、新構想型学部は将来にむけて大きな期待がかかる学部である。その為にも、これまでに挙げた課題を克服し、学際領域を学ぶ場として、土台をしっかりと築いていかねばならない。このような観点から、今後関連する調査研究および、議論がさらになされることを期待する。
「総合科学技術会議」が担うべき機能
第2研究グループ
総括主任研究官 平澤 冷
昨年度、海外の科学技術政策関連機関への訪問調査をする機会があった。研究所の若手研究者らと手分けをして、米・英・独・仏・蘭・瑞(スウェーデン)・EUの120機関(部署)、合計176名から詳細な聴取調査を行った。この種の調査は、私にとって、何回目かだが、率直にいって、今回ほど、我が国のパブリック・マネジメント・イノベーションの遅れを痛感したことはなかった。知識社会におけるグローバル・コンペティションへの対応を考えるとき、マネジメント格差の大きさの意味は深刻である。その体制整備を本気で急ぐ必要がある。
折しも、「中央省庁等改革基本法」が成立し、個別の府省や制度のあり方について、より具体的な詰めの作業が行われる段階になった。このフェーズをいかに仕上げるかで、改革のパフォーマンスは大きく左右される。「総合科学技術会議」や「教育科学技術省」の内実をどのように整えるか、独立行政法人への移行を検討することになっている国立研究機関をどのように再編するか、「基本法」で見落としている重要事項は無いか等。
調査結果の一部は、まず「主要各国の科学技術政策関連組織の国際比較」科学技術政策研究所調査資料・データNo.55(1998年6月)として、米、英、独、仏の各国間比較の形でまとめられた。本欄では、その紹介を兼ねて、我が国が直面している課題別に報告書の内容を再整理し、連載形式で主要な論点を挙げてみたい。今回は、「総合科学技術会議」のあり方についてである。
1.「総合科学技術会議」の位置づけ
先の行革論議の中で、我が国の政策形成における戦略性の欠除が各方面から指摘されていた。しかし、「基本法」では「総合科学技術会議」の任務を「科学技術の総合的かつ計画的な推進に関する政策の基本、科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の基本方針、その他政府全体として取り組むべき科学技術政策に関する重要な事項」等と定めていて、戦略性というより、総合性や統合性により強いアクセントが置かれている。上記の第1項目はいわば総合的な基本政策の形成に関して定めたものであり、科学技術会議設置法第二条にある「基本的かつ総合的な政策の樹立」とか「長期的かつ総合的な研究目標の設定」と大差がない。しかし、第2項目は科学技術会議設置法にある「特に重要なものの推進方策の基本の策定」に比べると、より戦略性に配慮したプライオリティ・セッティングの必要性を規定しているとも読める。この規定が、"調整結果の追認"という従来しばしば見られたパターンのみに陥らないようにするためには、新たななにがしかの仕掛けが必要であろう。これについては後で論じたい。
科学技術会議は審議会として位置づけられているが、「総合科学技術会議」も行政組織法上のいわゆる八条機関であり、行政府の一部として行政権限を持つ三条機関ではない。
2.調整機能と助言機能
「総合科学技術会議」の議長は、科学技術会議のそれと同様首相である。行政府の長が議長を努める合議制の機関(「基本法」第十二条3項)は、外国ではNSTC(米国:国家科学技術会議)やSTPC(フィンランド:科学技術政策会議)にその例を見ることが出来るが、これらはいずれも総合的な調整機関である。科学技術関係で、その調整機能を行政府の長を責任者とし財政当局者と科学技術関係当局者とを加えた機関で行う方式の源はといえば、おそらく日本の科学技術会議であろう。そしてその効果は、実施体制を担保した機能的な調整計画策定体制として、十分実証済みである。このような我が国の知恵は、たとえば米国ではレーガン政権の末期に真剣に検討され、ブッシュ政権のFCCSET(米国:連邦科学工学技術調整会議)の復活(ここではまだその長は大統領科学技術担当補佐官である)を経て、クリントン政権のNSTCになってようやく形式的な完成を見る。そして、その意義が米国においても認識されつつある(大統領がNSTCの本会議に出席できないことが多いが、本会議で合意された内容や、大統領優先事項に指定されたものが、大統領名で出されていることに重要な意味がある等)。
「総合科学技術会議」のその他の構成者は、やはり科学技術会議のそれとほぼ同様官民混在型である。あえてこれに類似した組織構成と設置形態を有する海外の機関を探すと、RFTI(独国:研究技術革新評議会)やCST(英国:科学技術会議)がある。この両者とも、フィンランドのSTPC同様、我が国の科学技術会議を参考にして構想された経緯があることからも理解されるように、大臣と民間有識者の混合組織となっている。しかしながら、RFTIは、産学連携を強化するために設置された機関であり、目的が限定されていると共に、首相に対する産学官(官は関係大臣)の会議による助言機関と位置づけられている。なお、RFTIのメンバーに首相は入っていない(助言を受ける者が、助言内容を検討する会議の責任者というのでは、助言内容に対して誰が責任をとるのかを不明確にしてしまう)。また、RFTIはBMBF(連邦教育科学研究技術省)大臣が司会をするが、大臣側は多くの場合、民間有識者(産学)の発言を一方的に受容する側に回っているとのことである。そして、RFTIの設置経過やそのメンバーの選任プロセスから、ドイツではRFTIはコール首相の諮問会議と受け取られていて、勧告機関であるWR(独国:学術評議会)が持つ権威とは比べるべくもない。一方、CSTは、DTI(貿易産業省)大臣(首相の代理として科学技術を統括する立場にある)に対する補佐機能を中心として運用されていたが、今年になって機能が拡充され、それと同時に首相に対する助言機関としての役割も担っている。CSTはDTI大臣とCSA(主席科学顧問)が議長と副議長を務め、メンバーにはアカデミアや産業界の有識者の他にファンディングや評価に関わる"科学技術関連中間組織"の関係者等も含まれている。改訂前、会議は多くの場合討議や建議を通じて大臣の意思決定を支援する機能を担っていた。従ってこの限りにおいて報告書等の形で討議内容がまとめられることはなかった。しかし、改訂後は、首相への助言内容を中心に、公表資料が作成されることとなり、透明性が高められてきている。
このように我が国の科学技術会議の構成を参考にして構想された海外の類似機関は、行政責任者を長とする調整機関(NSTC,STPC等)か、長を含まない官民混在型の長への助言機関(RFTI,CST等)かに分けることができる。これに対して、科学技術会議は両機能を併せ持ち、省庁間にわたる総合調整事項に関する諮問・助言を一体的に担うべきことが規定されている(科学技術会議設置法第二条)。「総合科学技術会議」においては、さらに単独の府省に関わる事項であっても国家的観点からみて重要な事項はその所掌範囲に加えてあり、より広い意味で総合調整の実を挙げることが期待されている。従って科学技術会議の理念を継承し、"東洋の知恵"を活かしつつ、他方で助言内容の調整的形成とその責任所在の明確化を図れるシステムを考える必要がある。すなわち、「総合科学技術会議」の機能を助言内容(次項以下に述べる戦略的政策も含む)を含む総合的調整と位置づけその下部ないし関連機構のあり方を詰める必要がある。
3.戦略的政策の形成と補佐機能
戦略的政策は、上で考えたようなボトム・アップ型の調整的形成メカニズム(いわゆる各省各部署からの持ち寄り調整型)で作成することは、ほとんど不可能であろう。そのような機構ではなく、それは政権担当者が掲げる国家目標からブレイク・ダウンしていくトップ・ダウン型の展開的形成メカニズムか、権限委譲された責任部署毎のオートノミーに委ねられた自律的形成メカニズムによることになる。展開的形成メカニズムは、国家の大戦略の展開を担うために、また、自律的形成メカニズムは戦略の多様性を確保するために、いずれも重要である。しかし今回は「総合科学技術会議」に焦点を絞る都合上、後者については回を改めて触れることにしたい。
さて、「総合科学技術会議」のレベルで戦略的政策を形成するとすれば、どのような機関が必要となるであろうか。結論を先に述べれば、それは意思決定者と助言機関の関係ではなく、意思決定者と補佐機関の関係においてはじめて十分に展開できるであろう。
国家レベルの戦略的意思決定においては、科学技術体系に内在する個別専門的な深い知見と先見性を損なうことなく実に多様な科学技術を全体的視野のもとにおさめ、他方でこれまた多様な国民的ニーズを踏まえたうえで戦略を構想していく必要がある。これを実現できるシステムは並大抵のものではないであろうが、そのようなものを必要としているのが知識社会の現実でもある。一方、国家の意思決定者は、通常実現すべき目標や課題を胸中に抱いているであろうが、それを現実化する手段に関する知識や経験は必ずしも十分ではないであろう。そのような意思決定者としては、その意思を原点に据えその責任において政策を展開するとすれば、深い専門性や多様な経験に裏打ちされた真正な知見がその必要に合わせて提供される仕組みが必要となるであろう。さらにいえば、「科学技術」に対しては、「経済」現象に対してより、はるかに専門家の認識は奥深くにまでおよんでいる。従って、経済政策においてすらそうであるように、科学技術関連政策では一層強く、そのような専門家の深い認識を政策形成や意思決定に反映させる努力を払い、そのためのシステムを整える必要がある。そのシステムの機能中枢となるべきものが補佐機関である。
4.欧州主要国の補佐機構
意思決定者に対する補佐機構が最も整えられている国は米国であろう。一方、科学技術の戦略的な政策展開が行われている国は、米国を除くと、ほとんど他にない。戦略的な政策形成と補佐機構の有無とは密接に関係している。英国の、前政権時代のCSTは、高級レベルの「内在型」補佐機関であったが、会議密度が2ヶ月に1回程度とあまり高くなく、またCSTの支援事務局が弱く、全体的視野を十分に整理できる体制にはなっていなかった。欧州諸国の場合、独・仏に典型的に見られるように、多くは科学技術を統合的に扱う「研究・技術省」を擁する体制になっているが、省内に大臣に対する補佐機能はあっても、首相に対するものは無いか、あっても弱い「外在型」である。そして欧州諸国にとって深刻な問題は、研究・技術の統合的所管といっても、リサーチ・カウンシルに代表されるように、個別省庁のミッションに固有な研究開発を除く領域やステージにある「一般研究」を大括りにしたものであり、研究開発全体を統合する機構にはなっていない点である。特に産業競争力を強化するために、個別ミッションと研究ポテンシャルの連携が重要になってきているが、80年代後半以降、欧州各国で試みられた様々な改善は研究実施レベルに重点があり、首相に対する総合的な戦略的政策形成のための補佐機能の強化という観点からみるならば、まだほとんど整備されていない状態であるというべきであろう。
5.米国の補佐機構
一方、米国においては、科学技術担当大統領補佐官(APST)と彼が長を務めるOSTP(米国:大統領府の科学技術政策局)が補佐機能を担う要となっている。米国のシステムの特徴をまとめると次のようになる。政策対象の「全体性」を把握するための多様な情報網とその集約のメカニズムが完備され、また困難な「先見性」を得るために専属の調査分析機関を備えている。以上の点は極めて重要なので、多少詳しく説明しておこう。
米国のシステムにおいてはAPSTの役割が重要である。「Bill(Clinton)は、科学技術で困ったことがあると『Jack(Gibbons)、これはどういう意味なのか、これをどうしたらいいのか』と、ごく日常的に補佐官の意見を求めている」(Franklin D. Raines : Director , OMB)とあるように補佐官の役割は、①意思決定者の質問や疑問に答える、②意思決定者が提示する彼の直感的な意思表示(実現したいこと)を科学技術政策の枠組みにブレイクダウンする、③その政策の効果やインパクト、あるいは実現可能性の分析や検証を行う、④さらに、類似した政策や代替案を整理し、意思決定者のための選択肢をそろえる等にある。ここで強調したいことは、補佐官は自分の意見を述べる「助言者」ではなく、あくまでも多様な専門的知見を整理し、意思決定者の判断を補佐する黒衣役に徹すべき点である。とはいえ、国家の意思決定を補佐するその職責は、個人の能力だけで果たせるような軽いものではない。補佐官の手元に、整理された多様な情報が様々なルートを通して集積されていく仕組みが必要である。米国の場合補佐官を支援するその体制が次のように用意されている。
民間人からの意見や助言はPCAST(米国:大統領科学技術顧問会議)を通して得られる。 PCASTは補佐官以外はすべて民間人で構成されていて、民間からの意見を高いレベルで集約することを目指している。民間人からの議長(現在は、John A .Young)と共に補佐官がPCASTの共同議長を務める。メンバーは学界や産業界の高名な指導者達で(19名)、年4回の会議による提言や助言のほかに、毎年1回各自が個別に意見書を提出することになっている。また、このメンバーの多くは民間やアカデミーの、シンクタンクや提言機関の責任ある地位を占めていて、そこで収集分析された情報を橋渡しする役割も果たしている。
行政府からの情報はNSTCやOSTPを通して集約される。NSTCは複数の省庁にまたがる事項のみを調整する委員会形式の機関である。単独省庁に関わる事項は直接OSTPに持ち込まれる。NSTCは行政府のメンバーのみから構成され、行政機関からの意見が集約される。本会議は大統領が議長(補佐官が代理)を務め、副大統領及び各行政機関の長と各補佐官からなる委員によって構成されている。そのもとに、現在5つの常設委員会及びいくつかの特別ワーキング・グループが置かれ、さらにそれらの下部に小委員会やワーキング・グループが設定されている。これらは日常的に活動し、会議や電子会議がもたれている。各常設委員会は、それぞれその分掌事務に関連の深い行政機関の長とOSTPの4部門の各責任者であるAssociate Directorとが共同議長として充てられている。また、常設委員会のメンバーや、小委員会ないしワーキング・グループの責任者やメンバーの一部にOSTPのメンバーが充てられていたり加わっていて、それらのメンバーを介して行政機関の意見がOSTPに集約される仕組みになっている。また、それと同様に、大統領の意思が、同じメカニズムを逆行して科学技術政策にブレイク・ダウンされ、関連行政機関に受け渡され、実施に向け具体化されていく。
このように、メンバーの共有メカニズムを介して、民間、行政双方の意見や情報がOSTPに集められる。OSTPは、環境、国家安全保障国際、科学、民生技術の4部門と、NSTCとPCASTの共同事務局等、約40名の選び抜かれたテクノクラートからなる。OSTPの長官である科学技術担当大統領補佐官と4部門の責任者は、毎朝定例会議をもっている。また、部門内部の意思疎通は、各部屋を結ぶ内部廊下を利用して、随時図られている。定例会議は、部門により毎週ないし、2週間に1度の間隔でもたれている。このようにして、PCASTやNSTCで集約された意見や情報をOSTPでさらに煮詰め集積し、必要に応じて補佐官に伝達される仕組みとなっている。そして補佐官は週1〜2回の頻度で大統領と会見する。
またさらに、行政機関の分析能力を補うために、OSTPとNSTCを専ら支援する機関として、CTI(米国:クリティカル技術研究所)がRAND社内に設けられている。機密を要しない調査や分析支援に関しては、各行政機関からも民間シンクタンクやアカデミーに常時委託されているがCTIは、OSTPとNSTCの特命事項の調査や分析を扱っている。専任研究者の数は17名と少ないが、必要に応じてRAND社内の研究者がCTIの客員や共同研究者となって、それを補っている。またCTIは調査や分析に専念し、政策提言は行わないことになっている。
以上述べた強力な補佐制度は、柔軟な「主体内在型」に設計されていて、組織の壁を越えてメンバーを共有することにより、最も効率的な「内在接触型(inclusive - interactive)」で運営されているところに特色がある。なお、この特色あるメカニズムは、我が国で芽生えた組織論を参考にしたものでもある。
トップ・ダウン型の戦略的政策展開は、このように完備した補佐機関なしには実現できないであろう。しかしながら、実は、これだけではまだシステムとしては不十分である。可能な限りの妥当性を得るためのシステムとしてこれは整備されていても、そのアウトプットが完全なものである保証にはならない。我々には、さらにチェック機構や、バランス・システムが必要である。しかし、この点については回を改めて述べる事にしよう。
6.「総合科学技術会議」のあり方
トップ・ダウン型の戦略形成機能を備えた「総合科学技術会議」のあり方を想定した場合、ボトム・アップ型の総合調整機能との調和のさせ方や助言機能の強化のあり方を含め、さらに検討を深める必要がある。最後に、そのための論点を挙げておこう。なお、トップ・ダウン型とボトム・アップ型との比率については、ボトム・アップ型が従来通り主流を占めるべきであると考える。米国の例を見ても、上記のメカニズムによるトップ・ダウン型は、予算ベースで高々15%程度であることを付記しておく。
| ・ | 総合科学技術会議常勤議員の1人を首席常勤議員とし、首相に対する科学技術担当補佐官とする。 |
| ・ | 内閣府の「総合科学技術会議」事務局(またはその一部)に補佐機能を持たせる。 |
| ・ | 情報収集と分析を本務とする支援機関を行政府の内部(ないし外部)に設ける(形成的支援と分析的支援に機能分化する場合も考えられる)。 | ・ | 民間の支援機関を育成・強化する。 |
| ・ | 科学技術会議の政策委員会が担っていた機能を補佐機能と助言機能に分け、外部有識者から成る助言機関(科学技術顧問会議)を別途設けることにより内閣府への助言体制を強化する。 |
| ・ | 科学技術顧問会議は、外部有識者の代表と首席常勤議員の共同議長体制とすることも考えられる。 |
| ・ | 助言機関に、必要に応じて外部有識者から成る下部機構を設けることができる。 |
| ・ | 内閣府の「総合科学技術会議」事務局の一部を関連部局からの出向ポストとし、トップ・ダウン型プロジェクトの実施体制を確保する。 |
| ・ | 教育科学技術省の内部(あるいは内閣府ないしその中間)に科学技術関連政策と予算の調整機能を担う調整事務組織を置く(ボトム・アップ型の統合的政策形成の調整と予算の見積もり調整とを分離して配置する案も考えられる)。 |
| ・ | 「総合科学技術会議」に、課題に応じて、関連府省担当官と外部有識者から成る下部機構を設け、総合調整のための課題の解明やその具体化を図ることができる。なお、そのための事務は、上記調整事務組織が当たる。 |
なお、行政に対する知的支援システムを、ここではそれが担うべき機能と設置形態に従い、以下のようなカテゴリーに分け、その中心的役割が何であるかを定義した。
| 補佐機関: | 行政府の内部に置かれた部署のうち、意思決定者に対し政策形成とその運営全般に関わる補佐を行う者および組織 |
| 助言機関: | 行政府の外部に法律ないし行政手段に基づき設置された審議機関で、主として政策形成に関わる助言や、諮問に対する答申を行う機関 |
| 勧告機関: | 法的に勧告を義務づけられている機関のうち、主として事前評価を基にして政策形成に関わる勧告を行う機関 |
| 支援機関: | 行政府の内部ないし外部に法律ないし行政手段に基づき設置された機関で、情報収集や調査、あるいは、その分析や研究を深める機能をもち、政策形成やその運営のために必要な情報の提供を担う機関 |
| 提言機関: | 行政府の外部に民間の意思により設置された機関で、主として政策提言を行う機関 |
第4調査研究グループ
科学技術庁が1971年より約5年毎に実施しているデルファイ法による技術予測調査は、科学技術政策の立案や技術開発計画の策定に当たっての有効なツールとして、最近では世界各国にて実施されており、そのほとんどが日本の調査形式を踏襲している。昨年7月に当研究所より公表した「第6回技術予測調査」に関しても、海外から多くの関心が寄せられた。当研究所としても、「第6回技術予測調査」報告書の英語版の出版及びホームページへの掲載、国際会議での講演等、海外に向けて積極的に情報提供を行っている。今回、その一環として、去る5月20日(水)に、在京大使館のサイエンス・アタッシェで組織されている"Science and Technology Diplomats Circle of Tokyo"の方々を当研究所に招いて、「第6回技術予測調査」結果の説明会を実施した。
説明会では、以下の4つの視点から、今回の調査結果を中心に技術予測に関する説明を行った。
| ○ | 国内での各種技術予測活動の状況と科学技術庁予測調査の位置付け |
| ○ | 海外での技術予測調査の状況 |
| ○ | 第6回技術予測調査結果のポイント |
| ○ | 過去の予測調査の評価および今後の課題 |
説明後の質疑応答では、調査課題の設定方法や回答者の属性(会社員、大学関係、公務員、団体職員)により調査結果に大きな違いがあるのか等の質問があり、活発な意見交換がなされた。なお、この説明会への参加者は以下の方々であった。
| 氏 名 | 役 職 | 国 名 等 |
| Mr. Wolf Dietrich Heim | Cultural Attache | Austria |
| Mrs Peggy S.-L.Tsang | Counsellor, Science and Technology | Canada |
| Mr. Isao Kaneko | Technology Development Officer | Canada |
| Mr. Jiri Brabnik | Counsellor, Scientific and Economic | Czech Republic |
| Mr. Jens Uggerhoj | Technology Attache | Denmark |
| Mr. Bahaa Zaghloul | Counsellor Culture, Education and Science Bureau | Egypt |
| Dr. Henri Angelino | Counsellor for Science and Technology | France |
| Dr. Sandor Toth | Counsellor, Science and Technology | Republic of Hungary |
| Dr. V. T. Chitnis | Counsellor, Science and Technology | India |
| Mr. Carlo Errani | Science Attache | Italy |
| Mr. Sang ku CHANG | Science Attache | Republic of Korea |
| Mr. Magne J. Kalstad | Counsellor, Industry and Technology | Norway |
| Mr.Petre Stoian | Second Secretary | Romania |
| Mr. Leonid P. Sushin | Counsellor for Science and Technology | Russian Federation |
| Mr. Lennart Stenberg | Counsellor of Science and Technology | Sweden |
| Dr. Jean-Marie Rayroux | Counsellor for Science and Technology | Switzerland |
| Ms. Mutsumi Funayama | Assistant to the Counsellor for Science and Technology | Switzerland |
| Mr. Paul Lynch | Counsellor, Science and Technology | United Kingdom |
| Mr. James Hall | Minister-Counsellor Environment, Science and Technology Affairs | United States of America |
| Mr. Maurice Bourene | First Counsellor for Scientific and Technological Affairs | Delegation of the European Commission |
| Dr. Edward O. Murdy | Director, Tokyo Regional Office | National Science Foundation United States of America |
| Mr. Masanobu Miyahara | Director, Tokyo Regional Office | National Science Foundation United States of America |


東洋大学国際地域学部教授 長濱 元
(元第2調査研究グループ総括上席研究官)
1. 政策研への赴任と創設期の雰囲気
 政策研が昭和63年7月1日に発足する直前に文部事務次官から異動の内示を受けて、「科学技術政策研究所とはいったいどこにあるのか?」と人事課に駆け込んでしまった。政策研が発足することなど全く知らされていなかったからである。したがって、どんな仕事をするところかも分からず、白紙の状態で赴任したのであった。
政策研が昭和63年7月1日に発足する直前に文部事務次官から異動の内示を受けて、「科学技術政策研究所とはいったいどこにあるのか?」と人事課に駆け込んでしまった。政策研が発足することなど全く知らされていなかったからである。したがって、どんな仕事をするところかも分からず、白紙の状態で赴任したのであった。
しかし、職場の雰囲気は決して悪くはなかった。科学技術庁の職員数に負けないくらい外部からの出向者や新採用の職員がおり、前身の資源調査所の名残もほとんど感じず、創設期の組織らしい「期待されている」と言う気分が強く、川崎初代所長を仕掛け人とする「ノミニケーション」も志気の高揚に大いに貢献していた。
2. 政策研での仕事の思い出
各グループにはそれぞれ職務分掌としての研究領域が既に決定しており、私が総括を勤めた第2調査研究グループは「科学技術と社会との調和」と「技術予測調査」という二つの課題を与えられていた。ただし、最初の半年間はその領域の中では具体的にどのような課題を立てて調査研究を実施するかの議論に費やされた。「技術予測調査」については、既に実施の時期もその内容も一定の目途があったので、当面大きな問題とはならなかった。ただし、「科学技術と社会との調和」に関してはどのような課題を取り上げるかについて大いに悩み、議論を行った。私は過去に実施した調査研究の経験を下敷きに10に近い調査プランを作成して提出したが、次々と所長に却下され、結局最終的に「科学技術と社会とのコミュニケーションの在り方について」という課題を取り上げることとなった。
平成元年に入ってから白根禮吉氏を委員長とする「研究委員会」の設置や報告書の作成、「科学技術と社会に関する意識調査」の実施、米国のミラー博士や英国のデュラン博士らとの国際共同研究、「科学技術の理解と科学教育に関する国際シンポジウム」の実施、最終報告書(NISTEP Report No.17)の作成やグループの仲間たちとの協力によるその他のテーマによる多くの報告書作りなど、多忙ではあったが興味の尽きない仕事を手がけることができた。
また、任期の後半に「第5回技術予測調査」を実施したが、これも聞きしに勝る大調査で足かけ3年にわたり全速力で走り、最後のとりまとめのときには半徹、徹夜が連続するという思い出の多い約5年間の調査研究生活であった。
3. 現在の仕事への政策研への影響
私は政策研に4年9ヶ月在職したが、これは私がひとつのポストに在職していた最長記録である。それだけ影響も大きかった。この時の経験が現在の私の仕事の枠組みを形成している。
私の本来の学問領域は社会学であり、アンケート調査やフィールド調査をベースにした家族社会学や地域社会学が専攻であった。大学卒業後文部省に就職したので教育社会学や教育行財政論がそれらに付け加わったが、経済企画庁や総合研究開発機構にも出向したので、消費経済や世代論、生涯学習、人口問題などにも関心が向くようになった。政策研の仕事は、これらの雑多な領域の経験に一本の筋を通してくれるという結果となった。
政策研の次には信州大学経済学部で教鞭を執るようになったのだが、ここでは科学技術を軸とした産業経済論を主な講義科目とするようになり、東洋大学に移った現在は文明論にも手を広げているが、基本的な視野は変わっていない。現在、研究の面では科学教育システムに関する国際比較調査を課題としているが、これらの教育研究の基盤はいずれも政策研在職時代に培ったものである。
4. 外からみた政策研への感想
政策研から信州大学へ移ってから2年間ほどは客員研究官を兼ねていたので、政策研を訪れることもしばしばあったが、近年はご無沙汰することが多くなったので、政策研に関する情報も少し乏しくなっていることは否めない。しかし、私の古巣である第2調査研究グループについては、私が政策研を去って以降、次第にメンバーの交替が激しくなり、総括の空席状態が生じたりして、苦しい活動を続けていることが惜しまれる。
ただ、「技術予測調査」に関しては、私の時代には十分実現できなかった技術革新と国際的展開に成功して、第6回目の調査が成功裏に終了し、その後も成果を上げていることは喜ばしいことである。政策研の創立期は科学技術政策研究の社会的認知そのものに海外からのブーメラン効果を期待する戦略が採られたが、世界的な「技術予測ブーム」を起こすひとつの引き金として政策研の「技術予測調査」が貢献したことは誇って良いことだと評価している。
5. 今後の政策研の活動に対して期待すること
創設以来、政策研は国内的にも国際的にも科学技術政策研究のフィールドでひとつの顔を作り上げてきたと言える。また、それぞれのポストに優秀な人材を結集し、魅力的な研究活動を継続してきた。
科学技術のみならずさまざまな分野の政策研究は今後いっそう盛んになってくると予想されるが、政策研の存在感をその中に定着させていくことはこれまでよりもいっそう難しくなると予想される。行革の方針として打ち出された文部省と科学技術庁の統合は、政策研の組織と活動内容に大きな影響を及ぼさないはずがない。今後の政策研幹部の研究活動の方向付けは政策研の将来の死命を制することになろう。
私の現在の立場から具体的な政策研の将来像を予想することは困難であるが、あえて注文を二つほどつけておきたいと思う。その第1は、国立研究所としての宿命ではあるが、所管官庁の「政策方針」と研究者集団としての「研究の観点」という複眼的な視点とそこからくる緊張感とを常に失わないで欲しいということである。また第2は、グローバルな次元での活動、日本の目で海外の政策研究を刺激し、海外の目で日本の政策研究を刺激するというように、常に外部へ向けて刺激的な発言を続けていって欲しいということである。
6. おわりに
私が約5年にわたる政策研での刺激に富んだ仕事ができたのも、第2調査研究グループで一緒に働いてくれた仲間や所長を始めとする職員の方々の助力と協力があったからであり、現在の私があるのもそれらの方々のお陰である。この場を借りて改めてお礼を申し上げたい。
○ 機関評価委員会第1回会合を開催
去る5月25日(月)、科学技術政策研究所において科学技術政策研究所機関評価委員会(委員長:西島安則 京都市立芸術大学長)の第1回会合が開催された。第1回会合では、これまでの研究所の活動状況等についての研究所側からの説明の後、科学技術政策研究の評価の在り方や研究所の位置づけ、今後の委員会の進め方などが議論された。
評価に供された研究所の活動状況等に関する資料は、後日科学技術政策研究所ホームページ
(http://www.nistep.go.jp/)にて公表する予定である。
なお、次回会合は6月24日(水)に開催されることとなった。

▲ 第1回機関評価委員会の様子(写真中央が西島委員長)
○ 講演会等/Lectures at NISTEP
| ・ | 5/14 | 「次世代ビジネスモデルにおける科学技術の位置づけ」 前田客員総括研究官(ソニー株式会社) |
○ 主要来訪者一覧/Foreign Visitors to NISTEP
| ・ | 5/14 | Dr. Sadok Chithis(インド大使館参事官) |
○ 海外出張
| ・ | 4/28-5/4 | 平澤第2調査研究グループ総括主任研究官 | (米国) |
| ・ | 5/25-5/31 | 榊原第1調査研究グループ総括主任研究官 | (英国) |
編集後記
当研究所の機関評価委員会が開催された。委員会では、評価を行う側(委員)が評価終了後に、研究所側と意見交換することに十分な意義を感じるように、また、評価される側(研究所)にとっても、各委員のご意見により得るべきものが多かった、と感じることができるような運営を目指したいといったような発言があったように思う。
研究所からの発信情報が、受信側(読者)に活用され、その反響が発信側の調査研究活動に反映されることが、活力ある情報サイクルのあり方であろう。政策研の発信に対しても、読者のご支援ご協力に期待すること大である。
本号では「調査資料・データ」速報を掲載する。これは、各国別の科学技術関連の国際比較をまとめた、調査資料・データNo.55の紹介であるが、折りしも行革基本法が成立し、読者の関心も高いことから、当面する課題別に整理し、調査担当者の若干のコメントも含めた形で執筆依頼した。なお、科学技術関連の課題別国際比較についても同様、調査資料・データとして、引き続き刊行する予定である。
さて、当研究所では創立10周年を記念して、記念誌の刊行及び国際シンポジウムを開催する。記念誌については、これまでの科学技術政策研究10年の研究成果に立脚し、さらに、今後の科学技術政策全般を展望した論文を中心に構成されており、創立記念日である7月に刊行する予定である。
本政策研ニュースも創立10周年を機により見易く、より速報性を目指して、大幅な見直しを行う予定である。引き続きご支援を賜れば幸いである。(Y)