





| No.113 1998 3 |
| 科学技術庁 科学技術政策研究所
NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |
| 目次 [Contents] |
 | レポート紹介 Highlight of the New Report |
 | 研究会等紹介 Research Meeting | |
 | 海外事情 Oversea's Infomation | |
 | コラム Column | |
 | 最近の動き Current Topics |
Ⅰ.レポート紹介/Highlight of the New Report
第3調査研究グループ 坂田和徳
1.調査研究の目的
①本調査研究「地域における科学技術振興に関する調査研究」は、地域における科学技術活動について、その実態がほとんど把握されていないという状況下にあって、先ず、都道府県及び政令指定都市について、科学技術振興のための体制、施策及び経費を総合的に調査することが最重要、最優先であるとの考えから始められた。
本調査研究の第1回調査は平成2年度を対象年度とし、第2回調査は平成4年度を対象年度として実施された。今回の調査は第3回目の調査であり、平成7年度が対象年度である。
②本報告書は、各地方公共団体が地域に適した施策を企画立案し、また国が地域科学技術振興のための支援施策を検討する際、基礎資料として活用されることを目的として作成されている。
2.調査研究の方法
①本調査研究は、都道府県及び政令指定都市に対して実施した「科学技術関係経費に関するアンケート調査」の結果を基本データとし、これに都道府県及び政令指定都市への追加的調査、関連諸統計、ヒヤリング調査、文献調査等から得られたデータ、知見で補充するという方法により行った。
②アンケート調査の質問票構成:
| 問1 | 科学技術行政の総合的推進 | 問14 | 研究所・研究開発型企業誘致 |
| 問2 | 公設試験研究機関(機関別経費等) | 問15 | 技術指導・技術相談 |
| 問3 | 公設試験研究機関(再編整備) | 問16 | 公募形式研究開発制度 |
| 問4 | 公設試験研究機関(研究機能強化) | 問17 | 科学技術情報制度整備 |
| 問5 | 理科系高等教育機関 | 問18 | 知的所有権制度普及 |
| 問6 | 医療機関 | 問19 | 発明奨励 |
| 問7 | 財団法人・第3セクター支援(研究開発) | 問20 | 人材育成(専門的技術分野) |
| 問8 | 財団法人・第3セクター支援(その他) | 問21 | 人材育成(研究ポテンシャル向上) |
| 問9 | 基金(法人以外) | 問22 | 国際交流(拠点整備) |
| 問10 | 自然科学系博物館・科学技術系教育施設 | 問23 | 国際交流(交流推進) |
| 問11 | 研究交流推進(共同研究実施段階) | 問24 | 科学技術教育 |
| 問12 | 研究交流推進(その他研究交流) | 問25 | 住民理解 |
| 問13 | 研究所・研究開発型企業支援 | 問26 | 重点的研究課題 |
3.報告書の構成
| 要旨 | [報告書全体の要旨] |
| カラーグラフでみる地域科学技術政策 [ポイント事項をカラーグラフで説明] | |
| 第1章 | 調査研究の背景と目的 |
| 第2章 | 調査研究の方法 |
| 第3章 | 地域における総合的な科学技術政策の推進及び科学技術関係経費の状況 [アンケート調査回答に基づき、基本項目毎に記述] |
| 第4章 | 今回調査結果からみた地域科学技術政策の特徴
[第3章の内容から特徴的事項を選び、他調査、過去調査等の視点を追加して記述] |
| 第5章 | まとめと今後の課題 |
| 付章1 | 地域科学技術振興のための施策展開例
[積極的、独創的、典型的と思われる事業を個別に紹介] |
| 付章2 | 団体別にみた科学技術関係経費等の状況
[本調査から得られたデータを元に団体別状況を整理] |
| 資料編 | 質問票、回答内容 |
4.調査研究結果の概要
(1)総合的推進体制整備
①科学技術関係審議会を設置している団体数は、前回調査の10から、今回調査では18に増加した。
②科学技術政策基本指針を策定した団体数は、前回調査の12から、今回調査では20に増加した。この期間に滋賀県と神奈川県では基本指針の改訂が行われた。【グラフ参照】
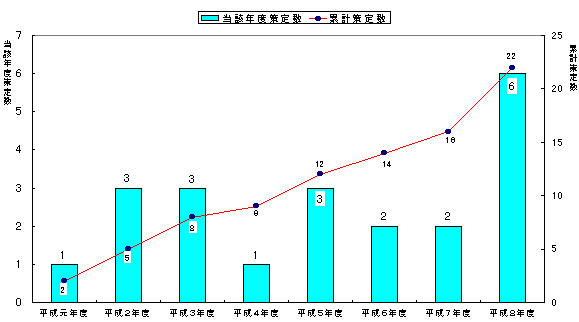
③科学技術政策担当専任部署を設置している団体数は、前回調査の9から、今回調査では12に増加した。
④以上の3点(審議会の設置、基本指針の策定、専任部署の設置)のいずれか少なくとも1つを実施している団体数は、前回調査の15から、今回調査では24に増加した。47都道府県の約半分が該当。全体として、科学技術振興のための総合的推進体制整備は着実に進んでいる。
(2)科学技術関係経費(総額)
①平成7年度における都道府県及び政令指定都市の科学技術関係経費は7143億円であった。これは、同年度の国の科学技術関係経費2兆4995億円に対し28.6%に相当する。【グラフ参照】
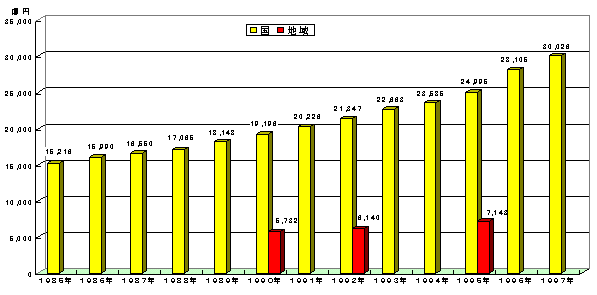
②この3年間の地域科学技術関係経費の伸び率は16.3%で、同期間の国の科学技術関係経費の伸び率17.1%にほぼ等しい伸びを示した。
③所管部局別構成をみると、農林水産系が最も多く32.1%を占め、次いで、商工系の23.4%、企画・総務系の17.4%と続く。国の所管省庁別構成と比べる農林水産系が多いのが特徴的である。
④目的別構成をみると、公設試験研究機関が最も多く51.6%を占め、次いで、高等教育機関の25.0%、財団法人等の5.4%、啓発普及の5.2%が続く。過去3回の推移をみると、公設試験研究機関の割合が減少し、高等教育機関、啓発普及などの経費割合が増加しており、地域科学技術関係経費は多様化が進んでいる。【グラフ参照】
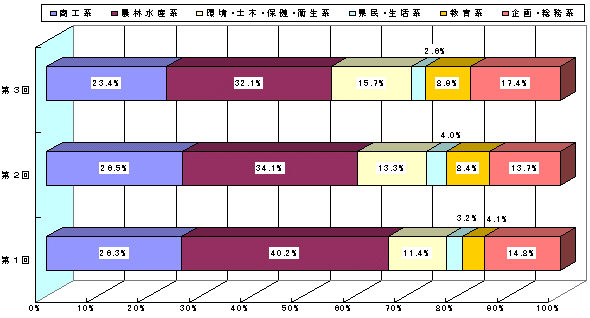
(3)科学技術関係経費の地域比較
①都道府県別(政令指定都市含む)に科学技術関係経費を比較すると、最大が大阪府の783億円で、北海道(526億円)、東京都(459億円)が続く。少ないのは、鳥取県(31億円)、香川県(38億円)。最大最小格差は約25倍。
②人口一人当たりの都道府県別科学技術関係経費(政令指定都市含む)を比較すると、最大が岐阜県の1万3307円で、滋賀県(1万2907円)、高知県(1万2489円)が続く。少ないのは、埼玉県(1412円)、愛知県(2806円)。最大最小格差は約9倍。【グラフ参照】
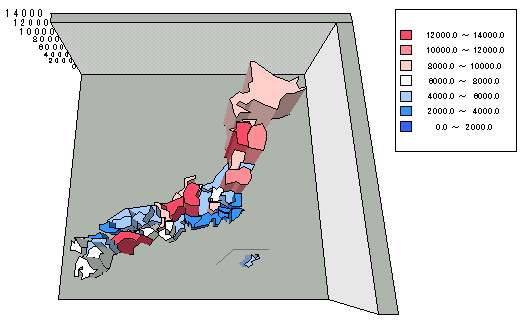
③財政支出に占める科学技術関係経費のシェアを都道府県別に比較すると、最大が岐阜県の3.35%で、滋賀県(2.74%)、福島県(2.21%)が続く。少ないのは、埼玉県(0.57%)、東京都(0.65%)。最大最小格差は約6倍。
④地域科学技術関係経費を事業性格別に整理し、農林水産系と商工系の合計(仮に「産業系」と呼ぶ)に着目して、都道府県別比較をすると、産業系割合の多いのは、鳥取県、鹿児島県、大分県。逆に、非産業系(産業系以外)割合が多いのは岐阜県、滋賀県、京都府。【グラフ参照】
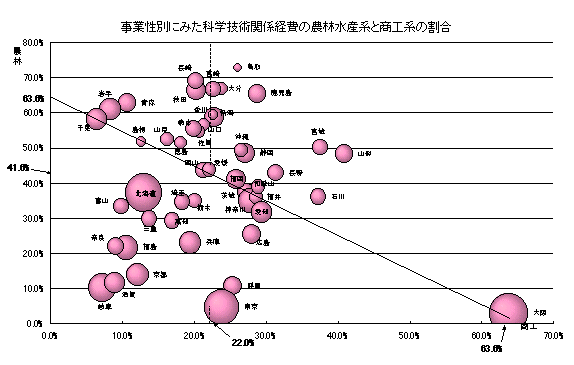
⑤事業性格別科学技術関係経費の割合を都道府県別の産業構造との対比でみると、農水産系(第1次産業)、商工系(第2次産業)とも全国平均値とはかけ離れた分布をする団体が多い。
(4)公設試験研究機関
①都道府県及び政令指定都市の平成7年度における公設試験研究機関は機関数572、研究者数は15,732人であった。同年度の国立自然科学系研究機関(大学関係機関を除く)については機関数73、研究者数9,157人であり、公設試の研究者数は国研研究者数の約1.7倍の規模である。
②公設試験研究機関の機関数、研究者数、運営経費を事業性格別にみると、農林水産系がいずれも5割以上の割合を占め、商工系と環境土木・保健衛生系が農林水産系の約半分でほぼ同じ割合で続く。
(5)理科系高等教育機関
①理科系高等教育機関として回答のあったのは117校である。このうち約半分は農業大学校である。
公設民営方式の理科系高等教育機関は2校あった(東北芸術工科大学(山形市)、高知工科大学(土佐山田町))。
②前回調査以降(平成5年度以降)の大学・短期大学の設立(又は計画)の回答総数28のうち19が看護系の大学・短期大学であった。公立の看護系大学・短期大学の設立は平成10年度以降も計画しているところがかなりあり、看護・保健系高等教育における公立大学・短期大学の果たす役割が大きくなっている。
(6)第3セクター、財団法人等の研究開発(支援)機関
①都道府県又は政令指定都市が出資・出捐した第3セクター、財団法人等の研究開発(支援)機関は、平成9年度までに183機関が設立されている。このうち国の制度関連が61、地方公共団体独自のものが122である。
②設立推移をみると、1990年に設立件数が26機関でピークとなったが、それ以降の新規設立は減少している。【グラフ参照】
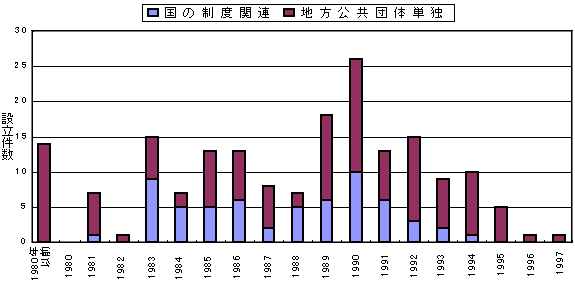
③平成7年度の都道府県及び政令指定都市から第3セクター、財団法人等への支出は約385億円であった(前回337億円)。内訳をみると、基金造成は減少(118億円→78億円)し、委託等の事業が増加(219億円→307億円)。
(7)知的所有権制度普及
①知的所有権制度普及と発明奨励に係る経費を今回調査から新たに加えた。知的所有権普及に関する事業として回答のあったのは18団体で、経費計3629万円であった。内容としては発明協会地方支部に対する補助事業が多い。
(8)研究開発人材の育成
①研究開発人材育成事業は、事業内容を「専門技術分野」と「研究能力向上」に分け、対象を「民間企業」と「県職員」に分けて聞いている。回答は、人材育成総額で205億円で、内訳は、「専門技術(民間企業)」195億円、「専門技術(県職員)」5億円、「研究能力(民間企業)」2億円、「研究能力(県職員)」3億円となっており、専門技術分野の人材育成事業が大部分を占め、研究能力向上事業は少ない。
(9)国際交流の推進
①平成7年度における国際交流に係る経費は「拠点整備」「交流推進」ともに、前回より増加している。(拠点整備:4億円→32億円、交流推進:9億円→10億円)
②今回調査では、姉妹関係提携の状況と近年における科学技術関係の交流実績を聞いた。姉妹関係締結件数と近年の科学技術交流実績件数を相手国別に整理してみると、姉妹関係締結件数では中国(42件)、米国(27件)、オーストラリア、ブラジル、フランス等の順になるが、交流実績件数では中国が圧倒的に多く(27件)、米国(5件)他は少ない。
(10)啓発普及(博物館、科学技術教育、住民理解)
①啓発普及に係る経費は、博物館等経費、科学技術教育補充経費、住民理解経費の3項目からなり、今回の啓発普及経費総額は406億円で、前回より29%増加している。内訳をみると3項目とも前回より増加しており、特に住民理解の伸びが大きい。【グラフ参照】
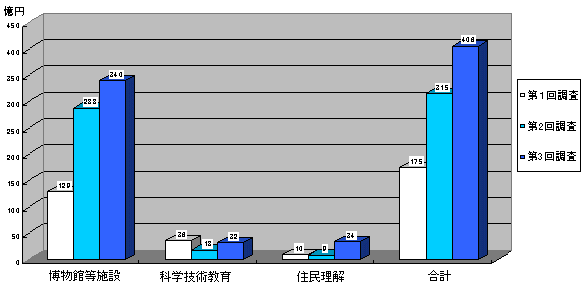
②自然科学系博物館(総合を含む)及び科学技術系教育施設は計画中の23施設を含め、計85施設の回答を得た。これらは、4つの類型に分けて聞いているが、全類型通じて平成元年以降の増加傾向が明らかであり、特にB型(自然科学系独立博物館)は最近の開館(予定を含む)が目立っている。
(11)重点的に取り組んでいる研究開発課題
①今回の調査で「特に重点的に取り組んでいる研究開発課題、技術課題」として回答のあったのは、課題数で177、経費総額は55億円であった。
②課題数、経費を事業性格別にみると、ともに農林水産系が一番多く過半を占め、次いで商工系が多い。
(1)講演会紹介
政策研においては、より広範囲な科学技術政策研究に資する為、外部の講師を招いて講演をお願いしているところである。本稿では、先日、慶応義塾大学の榊原清則教授にご講演頂いた「技 術戦略論の主な問題・情報技術と新たな企業モデル」の概要を紹介する。同氏は、一橋大学、ロンドン大学で長く技術戦略論を研究され、これまで数多くの論文を学会誌に発表されてきた。
慶応義塾大学教授 榊原清則
1 技術戦略論の主な問題きょうは、技術戦略論の主な問題、情報技術と新たな企業モデルという題でお話致します。最初は、技術戦略論です。技術戦略論というのは、経営戦略論の一つの領域で、技術を対象とした戦略論を指します。従来、日本の企業には、技術については戦略論は要らないというバイアスがありました。ところが、昨今、いろいろポテンシャルが多い技術成果、技術シーズが多いわりには、それを経営成果につなげることができないという現象が増えていますので、以下に申し上げるような技術戦略論の諸問題が企業の中でも重要になってきています。
1.1技術力と競争優位
技術戦略論のトピックの中で第一に問題となるのは、個々の企業の持つ技術力と市場における競争の上での優位性を獲得するという競争優位性とは別個のものである、という点です。そうすると、概念として技術力とは別個に競争優位とは何であって、競争優位をめぐる諸問題にどういう問題があるのかということを考える必要が出てきます。
技術力と競争優位が違うということを証拠づける事例は、たくさんあり、例えば、VTRにおけるソニーとJVC・松下陣営の競争が有名な事例として上げられます。この競争の勝者は松下陣営だったのですが、ソニーのベータ陣営が技術的に比較劣位だったという証拠はないでしょうし、また、逆に、別の視点から見れば、ベータ陣営のほうが技術優位だったという議論すらあります。したがって、技術力が競争優位をダイレクトに規定したという事実ではないでしょう。
少し昔の事例になりますが、東レが、ソフトコンタクトレンズの素材を開発して、素材開発、素材の技術をベースにして、自社独自でソフトコンタクトレンズ事業に参入したという事実があります。素材開発というのは、プロセスの中の一要素に過ぎず、付加価値で見ると、全体の売価の5%程度で、残りの95%は、素材以外の部分で発生しているそうです。したがって、全体の5%の部分で世界に冠たる差別化をして、技術的に優秀だと主張しても、残りの95%の部分で競争優位性を構築しなければ、利益を上げることはできません。現に、東レは、今でもこの業界における主要なコンペティターにはなり得ていません。いずれにせよ、技術力と競争優位は、すなわちイコールだとは言えない、技術力と競争優位はひとまず区別して考える必要があるということです。
1.2競争優位の源泉
そうすると、競争優位というのがどこから来るのかということを考えてみなければなりませんが、個別の事例調査をベースにした調査研究では、市場ニーズ、あるいはマーケティングファクターが競争優位のクリティカルファクターになっているという調査結果が多いと思われます。
例えば、1977年にMITのEric von Hippelは、社内ベンチャーあるいは新規事業を手がけた企業の事例を18(うち成功事例は11)集め、その成功要因を分析するために次の様な3つの質問調査を行いました。最初の質問は、既存の顧客に売っているか、かつ市場に精通した従業員がいるかという質問で、YESと答えるサンプルが7つあり、いずれも成功事例です。この質問にNOと答えた事例が残りの11で、そのうち成功事例が4つ残っています。2番目の質問は、市場に精通した人を社外からスカウトしたかどうかで、YESと答えた事例が2つあり、いずれも成功しています。NOが9つ残っていまして、成功事例はそのうち2つです。3番目の質問は、市場ニーズに基づくベンチャーか、それとも技術シーズに基づくベンチャーか。市場ニーズと答えた事例は3つあり、そのうち2つが成功事例。技術シーズと答えた事例は6つあり、全て失敗事例です。
この調査からも明らかなように、技術的に優秀な製品・サービスを作ったとしても、市場における競争で競争優位性を構築していくことは大変難しいということです。
このような事例調査とは別に、競争優位の構築に関する議論として、Complementary Assets(補完的資産)の議論もあります。一般に、事業の中枢を占めるような経営資源に対し、その周辺の機能に係わるような経営資源をComplementary Assetsと呼んでいますが、そのComplementary Assetsが、市場における成功には決定的に重要であるという例が結構多いようです。この場合、Complementary Assetsを強調する一連の議論も、技術力が競争優位の決定的に重要なファクターとは言えないということを示唆する例です。結局、競争優位の源泉が何であって、競争優位がどのように構築されるのかということは、ライバル企業との競争の分析をしなければ意味がないということです。
1.3利益の占有可能性
次のトピックの領域は、アプロプリアビリティーイシューと呼ばれる領域の話で、そもそも競争優位を構築できたとしても、そのこと自体が利益の占有を保証するわけでない、という話です。
現在は、業務システムを1社が単独で全部賄う時代ではなく、何らかの形で連携、ネットワークを構築しながらビジネスを作っていく時代です。そうすると、どういう部面にかかわる会社 が何の理由でもって利益を獲得するのかということ自体が独立の問題として登場してくることになります。
もちろん、このような業務システム自体は以前から存在していたのですが、昔は、業務システムが階層的な構造になっていて、加工組立型製造業でいうと、ファイナルアセンブラが業務システム全体のデザインも受け持つことが多く、結果として利益の分布も彼らが一義的に規定していました。ところが、最近では、ファイナルアセンブラが、だんだん付加価値の低い部分を賄うようになって、付加価値の高い部分が最終製品からワンランク川上のほうにシフトするという現象が起きています。
こういう現象が起きると、ファイナルアセンブラではなくて、どこに利益の占有可能性が移っているのだろうか、あるいは、そもそも利益の占有可能性は一体何によって規定されているのか、ということが大きな問題として出てきます。前者に関しては、最終製品組み立てからサブアセンブリーズへというのが1つの方向です。また、単純な部品や材料からサブアセンブリーズへという、つまり、個別のパーツや単なる素材から、それに付加価値をつけるために、中間品に意識的に付加価値を高めるという戦略が出てきました。
利益の占有可能性に関しては、基本的には産業の特性や、製品の特性を見れば、大体決まる変数だと考えられるのですが、一部では、完全にマナジリアルな変数たり得るという議論もあります。これは製品デザインの、あるいは業務システムのデザインの仕方で、利益の占有可能性が明白に変わるという事例です。
この問題を最も一般的に提起しているコンセプトは、タスクパーティショニングという議論だろうと思います。タスクパーティショニングとは、一つの製品を作り上げていく過程で、どの部分をだれに担当させるかという、意思決定のことを指します。そうすると、タスクパーティショニングを誰が決めるのかということによって、おそらくアプロプリアビリティーイシューは変わってくるでしょう。例えば、ジャンボジェット機は、おそらく何万品目という構成部品からできていると思いますが、巨大システムとしてのジャンボジェット機をデザインしているのはボーイング社で、どの企業がどの部分に何%参画するかは、ひとまずボーイングが決めているでしょう。したがって、日本の共同開発メーカーの利益が、仕事の請負量の増加に伴って増えるという事実はなく、最終的には、全体としてボーイング社にとって有利なようにアプロプリアビリティーが落着しているだろうと思います。
同様の事例は、ファミリーコンピュータにも見られます。ファミコンと、パソコンとの決定的な違いは、ハードとソフトの切りわけ方、パーティショニングにあります。任天堂はゲーム機本体を安い価格で売りたかったので、本体にメモリーを入れませんでした。メモリーは非常に高価ですから、そのことによって、ハードとしてのゲーム機を非常に安い値段で売ることができたわけです。
この例でもわかるように、全体のビジネスの組み立てをデザインしたのは任天堂で、どの部分で稼ぐかということについてのある特殊な製品概念の構築をしたがゆえに、大きな利益が一社に集中するという現象が起きたと言えます。つまり、パーティションのとり方を意識的に変えたということが、ファミコン産業全体の利益分布に影響を与えたということです。したがって、アプロプリアビリティーイシューは、明らかにマナジリアルな変数として操作の対象になっていて、しかも、それが経営成果にダイレクトに響いていると言えるでしょう。
1.4競争優位の維持
次に、競争優位の維持(サステナビリティーイシュー)のお話をします。競争優位を維持するということは、あるマーケットに出てトップシェアをとるとか、一番乗りを果たすということと同義ではありません。例えば、1年ぐらい前にMITのSloan Management Reviewに出た「First To Market, First To Fail?」という論文の中に、市場一番乗りを果たした会社が市場で最初に失敗するという事例が多かった、という話がありました。
ちなみに、日本企業で、全世界で市場一番乗りを果たした事例が一番多いのはソニーですが、そのソニーでも、ファーストムーバーとして市場一番乗りを果たして、なおかつ、それ以後もずっとトップシェアを維持している製品は、2つしかないそうです。一つはウォークマンで、もう一つは、放送局向けのプロフェッショナルユースの放送機材です。ソニーが自慢するファーストムーバーの中でも、ずっと競争優位を維持できている事例というのは、非常に少ないわけです。
ところで、これまで、新製品にかかわる調査研究の大部分は、個別の製品を分析単位とする調査研究でした。しかし、サステナビリティーという観点で言えば、個別製品の力・サービスの力・個別製品の戦略を、一種の連続的なあるタイムスパンを持った軌跡:製品トラジェクトリー(競争優位の維持にかかわる一連の調査研究の中で、この概念を提唱しているのは一橋大学の楠木先生です。)として捉え、新製品がどういう流れで、どういう順番で、どういうサイクルで出てくるのかという流れのデザインを議論の対象として検討する必要があるでしょう。
例えば、競争優位の維持について日産とトヨタの古くからの競争状況を分析する時、一つ一つの製品をピックアップして比較検討してみると、総じて日産の製品の方が優れているという結果が出ると言われています。では、なぜ一貫して系統的にトヨタのほうが、シェアが高いのでしょうか。
一つの論点は、製品群の製品ラインナップの全体としての並べ方と、新製品の時系列でチェックしたときの出し方(ある種の一貫したトラジェクトリー)がトヨタのほうにあるということです。そうすると、日産の場合には一つ一つの個別的な製品の製品力を強調するがゆえに、製品間の流れや、ラインアップのまとまり、製品を出していく時系列的な連続性などが少し弱いのかもしれません。また、かつてのビデオデッキ戦争を眺めても、新製品展開の一貫した取り組み方を見ると、ソニーよりも、JVC・松下の陣営のほうが、確かにサステナビリティーにかかわる戦略で、何らかの意味で巧みだったということが言えます。
このように、競争優位の維持という問題には、連続的な新製品展開、組織的な体制、あるいは組織的能力といった要素が係わってきますし、製品概念にある種の共通プラットホームのようなものを設けて連続的な新製品展開につなげるような、戦略の一貫性というか、戦略のとり方自体についての論点も出てきます。したがって、製品をたくさん出せばいいという、それだけの話ではないということが、競争優位の維持にかかわるサステナビリティーイシューとなります。
2 情報技術と新たな企業モデル
2つ目のトピックは、情報技術と企業経営、インターネット技術の浸透と国際比較上の論点、最後に新しい企業モデルの提起、の3本の柱からなっています。
2.1情報技術と企業経営
情報技術が一番本質的な使われ方をしているのは、加工組み立て型産業・エレクトロニクスなど世界的な競争力を持つ産業では、製品開発の部面と部材調達の部面においてです。これは、調達活動や、生産活動あるいは新製品開発が、このような産業領域では、重要なクリティカルファンクションですので、そういう部面でITがどの程度活用されているかということが、戦略上非常に重要な意義を持つことになると考えられるからです。
製品開発の世界では、エレクトロニクス系を例に取りますと、どこの会社に行っても、ITの高度活用を通じてコンカレントエンジニアリングを徹底させること、つまりITの高度活用を通じた開発リードタイムの短縮を目標としています。開発リードタイムが短縮できる2つの大きなファクターのうち、1つは、試作のバーチャル化による開発リードタイムの短縮、もう1つは、コミュニケーションの迅速化、透明化による開発リードタイムの短縮だと思います。
今、開発現場では、フルデジタルの開発作業を進めながら、同時にそれを、関係企業との間に張りめぐらせたネットワーク上で共同作業として効率的に行う、という例が普通になっています。
いずれにせよ、開発の現場でITの高度活用が進むことにより、マルチファンクショナルなチーム編成、濃密な人間関係に基づく高度な情報共有、あるいは非常にパワフルなリーダーシップ等、これまで日本企業の開発リードタイム短縮に大きく寄与したとされる社会的・組織的要素だけに依存した体制は、徐々に過去のものになりつつあることが一面では明らかになっています。
部材調達の世界でも、部材調達をIT高度活用で進めたいという動きが一般化しています。今や、部品・材料を外部調達にあおぐということは時代の趨勢ですが、各社とも海外調達の比重が高まっているため、それに伴って調達コストが急増する傾向にあります。そこで、比較的安い調達方法を工夫するいろいろな試みがあり、その中の1つがインターネットを通じた部材調達です。
ご存じのように、インターネットというのは、相手不特定のメディアなので、それがビジネスツールとして本当にどの程度役立つのかというのは、まだ試行錯誤の実験の段階です。しかし、従来では想定できないようなケース、例えば、南アフリカの会社や、旧東ヨーロッパ諸国の企業からの問い合わせがあったという事例もあり、インターネットを通じた部材調達も、いずれは、何か意味のある活動につながっていくのではないかという大きな期待を呼んでいます。
2.2インターネット技術の浸透と国際比較上の論点
情報技術の活用が進む過程でだんだんわかってきていることは、おそらく今後はコンピュータネットワーク技術の高度活用を各部面で目指しながら、全体としては、インターネット技術が浸透するというような形でITの活用が一般化していくだろう、ということです。
この図(図2)は私のところの大学院生が、ブラザー工業や横河電機で観察してきたことを概念的にかいた図です。この図の真ん中に観察対象の会社がありまして、彼らは今インターネットを使って、全世界に広がる会社(周辺メンバー)と部材調達の活動を実験として行っています。それから、従来から取引関係のある会社約45社とは、エキストラネットを通じて、さらに安定的なパートナーシップを構築しようともしています。もちろん企業内部では、イントラネットでいろいろな業務システムを再編整理する方向に来ています。
そうしますと、今仮に、ブラザーが南アフリカの会社と取引をインターネットで始めるとします。部材の取引を始めて、大変いい会社なので、それを中核メンバーとして、もっと関係を強化したい、ということになれば、周辺メンバーからコアメンバーへの取引パターンの変更は、極端な話、キーボードを1つ打てば済む、という技術的な条件ができたということになります。
このように、インターネット系技術に集約されるような形でITの高度活用が進むとすれば、日本型の取引関係の固定性・閉鎖性が、一方ではインターネットを通じた全世界に広がるような関係で払拭され得るでしょうし、他方で、コアメンバーは厳然として残りますが、周辺メンバーとコアメンバーとのシフトは少なくとも技術的には容易になるでしょう。そして、そのような企業間関係、即ち、当該企業の周辺にコアメンバーを中心とする安定的な取引構造があり、さらにその周辺に全世界に及ぶ企業との取引構造があり得るという関係は、星雲・ネビュラに例えて、ネビュラ型の企業間ネットワークと呼べると思います。
ところで、ITの高度活用がインターネット技術の浸透という形で起きるという話は、実は、日本でもアメリカでも、世界的に共通の話です。しかし、アメリカの事例と比較すると、日本型の取引構造はITの高度活用後も厳然と残っていることがわかります。例えば、ブラザーですと、このエキストラネットの対象企業は45社ぐらいですが、アメリカのGEでは、エキストラネットを構築した当初から2,500社がネットワークに参加しています。
したがって、ITの活用によって従来の企業間関係が一夜にして完全に変わってしまい、全世界的にある種の収斂傾向が起き日本もアメリカも同じになるだろう、という仮説は間違いで、日本型の階層的な取引構造は、ITの高度活用以後も依然として残るであろうというのが、私の見立てです。
2.3シリコンバレー型企業と国家超越型企業とネビュラ型企業と
最後に、日本の組織としての企業のあり方と将来の企業像についてお話致します。まず、世間で流布している議論に対する批判ということから一つ論点を提起したいのは、アメリカをベースにシリコンバレー企業が、いわゆる巨大企業システムに代わって、新しい企業モデルとなる、という議論は誤りだということです。
確かに、シリコンバレー企業がある特定の産業分野において新しい企業モデルを提起しているというのは事実です。しかし、他方において、従来考えられなかったような巨大な市場が国境の垣根を超えて存在していて、しかも、それを土台に大変アグレッシブな成長戦略を志向している世界企業が生まれつつあるということも、また事実です。
シリコンバレー企業モデルのオリジンはシリコンバレーに生まれる新生企業であって、彼らの目標は新しい市場の創造、焦点領域はコミュニティ単位、企業経営の基盤となるキートレンドはコンピュータネットワークの高度活用、企業間の連結の仕方はネットワーキングであって、エコノミー・オブ・スピードがキーワードになるような経営の組み立てを行っています。モデルとしてはサン・マイクロシステムズが適当でしょう。
片や、国家超越型企業は、あくまでも個別企業であって、オリジンはヨーロッパ系の多国籍企業です。彼らは従来の多国籍企業とは違う形で一層のスケールアップを目指していて、目標は世界市場支配です。焦点領域は最初から全世界であって、キートレンドは国際化です。彼らが取り結ぶ企業間の関係は戦略提携でして、企業間の安定的な連携です。そして強みは依然としてスケールエコノミーです。モデル企業としてはABBや、ネスレを挙げるのが正しいかと思います。
日本の企業は、個別企業では成り立たないという意味では、企業プラスクラスターとして存在しています。それから、オリジンは日本にあり、目標は、既存市場での新製品、新ビジネスの系統的な展開を通じた一層の市場浸透だろうと思います。ただし、日本の企業にとって日本という母国は特殊に大きいので、そこにある種の国際化戦略が加味されます。日本の企業に将来があるとすれば、それは情報化と国際化を足したようなものでしょう。また、企業間の関係は戦略提携プラスネットワーキングであり、キートレンドはスケールとスピードでしょう。しかし、実際には、スピードもスケールも必要だという点で中途半端になっているというのが現状です。おそらく、それを払拭する一つのかぎはITの高度活用、特にインターネット系技術の浸透を通じた業務システムの再編、統合ではないでしょうか。そして、企業間の取引関係・企業間関係は、将来的にはITの高度活用を通じたネビュラ型企業間関係になるだろう、というのが私の言いたいことです。
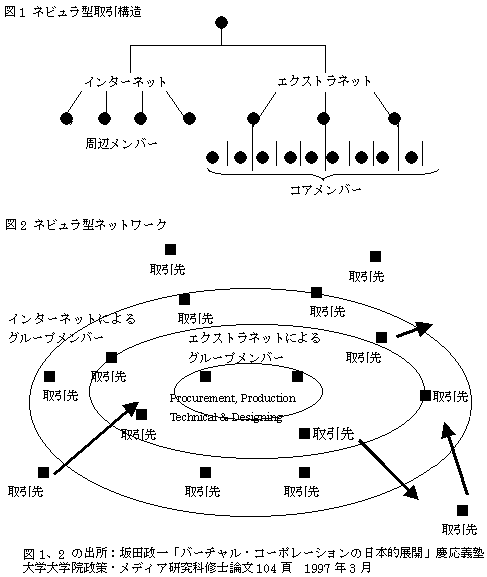
(2)平成9年度地域科学技術政策研究会の開催結果報告
第3調査研究グループ 坂田和徳
1.はじめに科学技術政策研究所は、2月24日、25日に砂防会館別館会議室(東京都千代田区)において、「平成9年度地域科学技術政策研究会」を開催した。この研究会では、地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)の科学技術政策担当者にお集まりいただき、「地域特性を生かした施策展開をどう進めるか」のテーマの下、最近の科学技術政策を巡る動向に関連する講演、当研究所における関係調査研究の報告、関係省庁の施策説明、地方公共団体からの施策展開の報告を行い、更には、出席者全員による自由討議を行った。本研究会には、42道府県及び10政令指定都市から65名の科学技術政策担当者の出席を得ることが出来た(総参加者約90名)。当研究所としては、本研究会を通じ地方公共団体の科学技術政策の状況や国への意見・要望を生きた形で吸収し、今後の当研究所における地域科学技術に関する調査研究の向上を図っていくこととしたい。
2.研究会の概要報告
−講演−
地域科学技術に関し、参加者に共通の認識を提供するため、学識経験者による2つの講演を設けた。
ひとつは法政大学総長清成忠男教授(日本ベンチャー学会会長)から「地域活性化と新産業創造」と題し、世界大競争時代における地域経済の現状から説き起こし、新需要拡大における問題解決型需要の重要性、技術対象としての既存要素技術集積の創造的応用の重要性等を強調、最後には地域おける産業振興政策推進の鍵となる点までご講演いただいた。
もう一つの講演は、平成8年8月に開館した滋賀県立琵琶湖博物館の嘉田由紀子総括学芸員・企画調整課長に「地域特性を自覚化するプロセスとしての調査研究−琵琶湖研究の経験から−」と題し、琵琶湖と地域住民生活との係わりについての調査研究等についてご講演いただいた。
−科学技術政策研究所からの報告−
権田客員総括研究官(東海大学教授)から、「国内外における地域科学技術政策及び政策研究の近況」と題し、特に知の創発メカニズムや産業の空間立地特性について報告があった。
この他、平成9年度において第3調査研究グループで進めてきた調査研究課題3つについて報告した。
柿崎主任研究官からは、現在進めている「研究・技術開発資源の空間的集積に関する研究」の中間報告、渡辺総括上席研究官からは、昨年7月に公表した「地域科学技術指標策定に関する調査」の報告、坂田上席研究官及び田中特別研究員からは、本年2月中旬に公表した「地域における科学技術振興に関する調査研究(第3回調査)」の報告が行われた。
−関係省庁施策説明−
関係省庁の地域科学技術関係施策について、文部省、郵政省、科学技術庁、通産省から説明いただいた。
郵政省、科学技術庁、通産省からは、主に平成10年度施策の考え方と内容について説明がなされた。
文部省からは、地域共同研究センター事業について最近の状況報告がなされた。
−地方公共団体からの報告−
5つの地方公共団体から最近の科学技術政策の具体的展開状況を報告していただいた。
初日には、埼玉県からは「埼玉県科学技術基本計画について」、神奈川県からは「科学技術政策と白書」について、高知県からは「高知工科大学設立と地域振興」について、2日目には、兵庫県から「播磨科学公園都市における研究活動」について、大阪市から「公設試の役割と機能強化諸施策」についてご報告いただいき、自由討議の議論へ展開させた。
−自由討議−
参加者全員により、地域科学技術振興施策について討議を行った。
テーマは、事前に行った自由討議用質問票への回答内容を基に関心の強かったものを選び、初 日は「基本指針・基本計画策定の狙いと効果」を中心に、2日目は「公設試の果たすべき役割」を中心に議論を進めた。
3.最後に
本研究会は、地方公共団体における科学技術振興施策担当者の協力の下、当研究所の地域科学技術政策研究活動の一環として、地域科学技術政策の抱える課題について報告と討議という形式で進めたものであり、会議の成果は研究会報告書として取りまとめ関係者の利用に供する予定である(4月末目途)。
○ 海外出張報告
(1)APEC技術予測センターの発足について
第4調査研究グループ 桑原輝隆
<「技術予測」と"Technology Foresight">
近年、ヨーロッパをはじめ、APECのメンバー諸国(economy)において、技術予測調査に取り組む国は急速に増えてきている。技術予測というと専門家を対象として将来の技術の実現時期などを調査するデルファイ調査が代表的な事例であり、特に日本語の「予測」には実現の時期を対象とするニュアンスが強い。しかしながら、最近海外で"Technology Foresight"という言葉が使われる場合その範囲はより広いものとなっている。例えばOECDの"STI REVIEW NO.17"においては、"Technology Foresight"を
| "Systematic attempts to look in the longer-term future of science, technology,economy and society with a view to identifying emerging generic technologies likely to yield the greatest economic and social benefits" |
例えばアメリカはデルファイ調査のような"狭義"の技術予測は実施していないが、NSFの支援によりRAND CooperationのCritical Technology Insititureが作成している"Critical Technology List"なども"Technology Foresight"に該当する。
我が国の技術予測調査においても、例えば最新の第6回調査の内容は実現時期の他に、重要度、経済・環境などへのインパクト、我が国と海外の技術水準、期待される政府の施策、懸念される事項など多岐にわたっており、1970年代の調査開始当初に比べて実現時期以外の項目が増えてきている。また、このような広い意味では、日本の場合も科学技術庁の技術予測調査のみでなく、各省庁における研究開発計画、指針あるいはこれらに関連して実施されている調査等で"Technology Foresight"に該当するものも多い。
<APEC諸国における技術予測活動 −センター設立の背景−>
APEC諸国における技術予測活動としては、まず、デルファイ法による技術予測調査を日本の他、韓国、タイが既に実施しており、インドネシア、中国が現在実施中である。
韓国の技術予測はほぼ日本と同じ規模のものであり、1994年に科学技術政策管理研究所(STEPI)から報告書が出されている。この調査では、韓国における実現予測時期と共に、世界における実現時期を調査し、世界の最も進んだ国と韓国の差を把握できるようになっている。なお、韓国では、生産技術研究院(KAITECH)が主に中小企業に関連する技術を対象とした10年程度のスコープの予測調査を実施し1993年に結果を公表している。
また、タイの調査はNSTDAの委託でチェンマイ大学により実施された100課題程度のものである。ここでは、先進国では既に実現・実用化している技術も対象として、それがタイで実用可能となるのがいつ頃かという観点から調査をしている。
オーストラリアの調査はオーストラリア科学技術会議(ASTEC)により実施された。オーストラリアは国土は広いが人口は少なく、当然科学技術に関する人的資源も限られることから研究開発の対象も絞らざるを得ない。このため、この調査では21世紀初頭において科学技術に対してどのようなニーズがあるかを調べることに焦点を当てている。その他フィリピンもデルファイではない調査に取り組んでいる。
中国は、次の5か年計画立案の資料として使うことを目的として、現在国家科学技術委員会が、まず、農業など3分野のデルファイ調査を実施中である。バンコクの会合に中国から参加した同委員会スタッフの話によれば、重視しているのは将来の中国にとって重要な技術を選定すること及びその開発の方法を決定すること(例えば、自主開発、国際協力、技術導入など)である。日本の第5回調査(1992年)及びこれをベースにしている韓国の予測調査などでは、技術を実現する上で何が阻害要因になるかも調査している。しかし、彼によれば、このような点は中国にとっては大きな問題ではなく、国家の方針が決定すれば、必要な資金や人材は調達できると述べていたのが印象的であった。
その他、今回のワークショップの関連では、台湾からの参加者は、台湾の場合中小企業が産業の中心であることから、これらの企業に適切な情報を提供するのに何が最適な手法かに関心を示していた。一方、シンガポールからの参加者は、政府の政策立案にウエイトを置いて、予測結果を政府内の政策過程に反映させていくためにどのような組織的対応をすればよいかに関心を持っていた。
このようにAPEC諸国は極めて多様性を持っているため、各国ともその科学技術の状況、国としての目的を何に置くかなどを踏まえてそれぞれの手法を模索しながら取り組んでいるというのが現状である。APEC技術予測センターが設立された趣旨も各国のこのような活動に対して情報提供、人材訓練、共同プロジェクト実施などを通じて支援していくことにある。
<APEC技術予測センターの概要と第1回ワークショップ>
技術予測センター長にDr. Greg Tegart(オーストラリア)、副センター長にDr. ChatriSripaipan(タイ)が就任した。運営を審議決定する機関としてSteering Committee(SC)が置かれると共に、センターの活動について助言する組織としてInternational Advisory Board(IAB)が設立された。メンバーは日本の他、カナダ、オーストラリア、韓国及びタイの専門家である。
1998年度の予算としては、APECセントラルファンドから5万USドル,NSTDAからの拠出700万バーツが予定されている。
1998年度の事業としては、今回の第1回ワークショップに続き、第2回及び第3回をタイ以外の国で開催する計画となっているほか、メンバー国等との協力拡大に向けたミッションをいくつかの国に送ることを考えている。また1999年度は、これらに加えていくつかの領域を対象とした技術予測調査を技術予測センターとして実施する予定となっている。
International Advisory Board(2月2日)では、このセンターの活動について、"foresight"のスコープをどう考えるべきかの議論があったが、APECはメンバー国等が非常に多様であるためOECDの定義にこだわらず、もう少し広くとらえていく方針となった。また、具体的予測プロジェクトの対象領域が議論された。
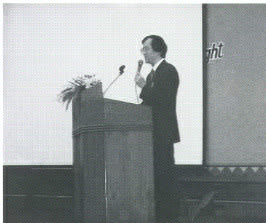 APEC技術予測センター設立式典が2月3日にあり、引き続き、パブリックセミナー "Introduction to TechnologyForesight"が約150名の参加の下に行われた。日本、カナダ、オーストラリア、韓国からプレゼンテーションが行われ、筆者は"Technology Foresight Application in the Government Sector: The Japanese Experence"のタイトルの講演を行った。
APEC技術予測センター設立式典が2月3日にあり、引き続き、パブリックセミナー "Introduction to TechnologyForesight"が約150名の参加の下に行われた。日本、カナダ、オーストラリア、韓国からプレゼンテーションが行われ、筆者は"Technology Foresight Application in the Government Sector: The Japanese Experence"のタイトルの講演を行った。
2月4日〜6日は技術予測に関するトレーニングワークショップで、出席者は33名(中国1,台湾2,インドネシア2,マレーシア2,シンガポール1,タイ25)であった。タイの出席者の大部分は科学技術環境省及びNSTDAの関係者である。第1日目は技術予測手法の概論、第2日はデルファイ法、第3日はシナリオ法の講義・演習をそれぞれ行い、筆者もいくつかのセクションを担当した。
科学技術政策研究所において第5回技術予測調査を公表した1992年以降、技術予測に関心を持ち実施する国が増大し、当研究所への海外からの訪問者もかなり多いが、この1,2年具体的に調査に取り組む国が増え、寄せられる質問なども変化してきている。当初はごく一般的な手法の質問が中心であったが、例えば今回の会議参加者からは、回答者の選定に関わるバイアスを避けるためには、分野の設定や回答する専門家の選定をどのようにしたらよいか、回答数がどの程度確保されれば結果が安定するか、ある種の質問について回答者の専門度あるいは属性(産・学・官の所属)による偏りが見られるかどうか等実践的なものが多くなってきている。我が国としても、今後これら新しい実施国の経験から学ぶところも多いと思われる。
(2)米国科学技術振興協会(AAAS)での講演
所長 佐藤征夫
本セッションは、米国NSFのジェニファー・ボンド女史(科学技術指標部門プログラム・ディレクター)とMogee Research & Analysis AssociatesのMary Ellen Mogee女史がオーガナイズしたもので、米国以外の主要国で科学技術のアセスメントや予測が政策のプライオリティ設定にどのように役立っているかを米国の政策策定者や分析者に知らせることを目的にしたものである。このため、英国からSPRUの所長とPRESTの所長、独国からISIの副所長、日本からNISTEPの所長がスピーカーとして招かれ、実績が考慮され、日・独・英の順にプレゼンテーションが行われた。
筆者からは、「Lessons from Japanese Foresight Studies」と題して、日本における技術予測実施の枠組(科学技術会議、科学技術庁等との関係も含む)、第6回技術予測の調査の枠組、主要調査結果等について説明するとともに、日本からの教訓としては、「広い範囲の科学技術分野でのトピックスの選択」、「専門度の高い協力的な回答者」及び「他のプライオリティ・セッティングシステムとのコンビネーション」の3つが重要である旨のべた。
独のフラウンホーファーISIのGrupp副所長からは、独におけるForesightは1990年までは活発でなく、1990年以降政策変更によりDecentralized national foresight活動が行われるようになったと説明があり、独の第2回調査である最新の調査の結果について、その概要や日独比較調査結果の説明があった。(2日後の2月17日に記者会見をして公表することになっているが、許可を得て紹介する旨説明有り。)
英のマンチェスター大学PRESTのGeorghiou所長からは、英の技術予測プログラム(Technology Foresight Programme,TFP)は、科学技術システムの新たな方向付けを目指した1993年の科学技術白書により開始されることとなった旨、また、TFPが科学技術に係る公的支出のプライオリティ付けに情報を提供すること及び科学と産業の間の新しい共同関係を作ることを目的としている旨説明があった。さらに、英のTFPの場合、Pre-ForesightとMain Foresightの段階があり、デルファイ法による技術予測は全体の一部であるなど、英国の技術予測プログラムの特徴について説明があり、成功点及び問題点が挙げられた。
最後に、技術予測研究の第1人者である英のサセックス大学SPRUのMartin所長から「Technology Foresight - International Experiences」と題して、「技術予測とは」から、その必要理由、米、日、欧及びそれ以外の国も含めた世界全体での技術予測活動の変遷、それぞれの国における技術予測の特徴の説明があった。また、技術予測は、技術の実現を当てることではなく、そのプロセスが重要である旨強調するとともに、技術予測のプロセスは、科学技術と社会との新たな関係の前ぶれではないかとの示唆に富む話がなされた。
4人のプレゼンテーションの後、米国のMogee女史から総括的コメントがあり、さらに米国のRAND研究所Critical Technology Institute(CTI)のWagner女史からCTIでの技術予測(Delphi法ではなくインタビューで小規模)の説明があった。その後、9時から12時までのセッションを20分延長して質疑応答やディスカッションが続けられるなど、日、独、英の科学技術政策研究機関の所長、副所長が顔を合わせただけでなく、内容的にも充実したものであった。
第3調査研究グループ 坂田和徳
当研究所において、地域科学技術政策は主要な調査研究対象分野の一つとして位置づけられてきた。NISTEP REPORTとして取りまとめられた報告書でみれば、現時点で56の報告書が作成・公表されているが、そのうち7つが地域科学技術政策に関する調査研究の報告書である。
以下、これらの主要な調査研究成果を中心にして、政策研における地域科学技術政策研究の活 動概要を整理してみる。
(1) 地域科学技術政策のフレームワークに関する基盤的調査研究(基本調査)。
初期において、大学や民間の研究基盤、研究活動及び地域研究開発事例等を調査した。その後、わが国の地方公共団体が実施している科学技術振興施策の実態を総合的かつ継続的に明らかにすることを目的に、都道府県及び政令指定都市における科学技術振興のための体制、施策、機関及び科学技術関係費等に関する調査を過去3回実施し、その状況を具体的かつ定量的に明らかにしてきた。
| [報告書] | 「地域における科学技術振興に関する基礎調査」(NISTEP REPORT №4) |
| 「地域における科学技術振興に関する基礎調査ー科学技術を基盤とした地域振興事例に関する調査研究ー」(NISTEP REPORT №11) | |
| 「地域における科学技術振興に関する調査研究」(NISTEP REPORT №23) | |
| 「地域における科学技術振興に関する調査研究(第2回調査)」(NISTEP REPORT №39) | |
| 「地域における科学技術振興に関する調査研究(第3回調査)」(NISTEP REPORT №56) |
(2) 地域における技術革新を誘発させるための新しい社会システムの構築に向けた産業・科学技術基盤についての調査研究
地域に展開する多様化しつつある科学技術機関・拠点(Science Institution) としてのサイエンス&テクノロジーパークの機能、形態、運営体制等について、総合的な調査研究を行った。
| [報告書] | 「サイエンス&テクノロジーパークの開発動向に関する調査研究」(NISTEP REPORT №38) |
(3) 地域に展開する中小企業の研究・技術開発活動の実態と技術革新過程における役割に関する調査研究。
中小企業における研究・技術開発活動を大企業との協力と競争の枠組みの中で捕え、その実態を日米比較することにより、日本の中小企業の競争力の強さの謎を明らかにするために、米国のヴァンダービルト大学と共同研究を行った。
| [報告書] | 「テクノロジーアセスメントとイノベーションの日米比較」
(Technology Management,Vol13,Nos,5/6,1997) |
(4) 地域科学技術指標の開発に関する調査研究。
地域における科学技術振興はそこに集積している科学技術資源や地域の伝統や文化に強く依存している。そのため地域の科学技術振興施策は地域に毎に異なっていることが予測されるが、その差異を計る方法が開発されていないために、指標開発のための基本調査を実施した。
| [報告書] | 「「地域科学技術指標策定に関する調査」(NISTEP REPORT №51) |
(5) 国際会議開催・国際共同研究等
1)RESTPOR:「地域科学技術政策に関する国際会議」
本会議は科学技術政策研究所が地域科学技術政策研究の意味とその重要性を世界に先駆けて提起し、経済のグローバリゼーションの進展の基で21世紀に向けて地域科学技術政策の果たすべき役割とその方向について議論を交すべく国際会議を開催したものである。第1回、第2回は政 策研主催で日本で開催(第1回:1993年6月、岩手県、第2回:1995年2月、神奈川県)。その国際的評価は高く、第3回会議はEU主催で1996年9月にベルギーのブリュセッルで開催され、第4回会議は米国のリサーチトライアングルの中核都市であるチャペルヒルで開催される予定(1998年10月)となっている。
2)ASCA Seminar:「科学技術と地域技術革新」(1994.3 埼玉県)
3)国際ワークショップ:「アジア圏における地域間科学技術協力」(1998.3 兵庫県)
(6) 地方公共団体の科学技術政策担当者参加の研究会開催
都道府県及び政令指定都市の科学技術政策担当者と一緒に地域科学技術政策の抱える課題について討議する研究会を1996年3月、1997年3月、1998年2月に開催した。
2.今回の報告書の位置づけと今後の課題
今回の報告書「地域における科学技術振興に関する調査研究(第3回調査)」は、都道府県及 び政令指定都市が、地域科学技術活動において、主要な活動主体者兼振興施策実施者であり、地 域科学技術振興においては極めて重要な役割を果たしていることに鑑み、その推進体制、施策内 容、関係経費等を総合的、体系的に把握しようとするものである。
所長 佐藤征夫
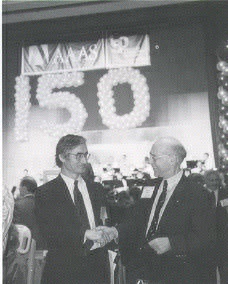 創立150周年記念の今年のAAAS年次総会には、クリントン大統領が出席し、スピーチを行った。大統領が出席してスピーチをするのは、1948年の創立100周年時のトルーマン大統領以来二人目とあって、5000人以上が本総会に出席するという盛り上がりであった。
創立150周年記念の今年のAAAS年次総会には、クリントン大統領が出席し、スピーチを行った。大統領が出席してスピーチをするのは、1948年の創立100周年時のトルーマン大統領以来二人目とあって、5000人以上が本総会に出席するという盛り上がりであった。
50年前のトルーマン大統領のスピーチでは、NSFの早期設立が呼びかけられたが(2年後の1950年設立)、クリントン大統領のスピーチでは、大統領科学顧問及び NSF長官の人事発表や科学技術者への信頼に基づく明るい将来社会への期待表明などがなされ、印象深いものがあった。
大統領のスピーチのほか、5つのPlenary Lecture, 20近くのTopical Lecture,数多くの分野にわたる130以上のセッションが行われ、アルビン・トフラー氏やクローン羊の「ドリー」のイアン・ウィルムット博士を初めとする有名人やノーベル賞受賞者など各分野の著名な専門家のスピーチがあり、専門家はもとより学生も多数参加していた。
クリントン大統領のスピーチの際、大ホールの前方左側の一区間が聴覚障害者用になっており、手話通訳者が手話でスピーチの内容を伝えるとともに、前方のスクリーンに大統領の様子とスピーチの文字(少し遅れ)が映し出されていて、多くの聴覚障害者が大統領のスピーチをその場で理解できるようになっていたのには感心させられた。大統領スピーチ以外でも、Plenary Lectureでは、他にも手話通訳付きのものがあった。
今回の年次総会は、AAAS創立150周年記念ということで種々のイベントもあり盛況であったが、日本からの参加者がほとんど見られず、多少、寂しく感じられた。また、1989年には「日本の科学」、1991年には「日本の工学」というセッションが設けられたことを考えると、米国側の日本の科学技術に対する関心も弱くなったと言え、その意味でも寂しく感じられた。米国側の日本に対する関心はともかく、日本側からもっとAAASに関心を向け発信していくべきであろう。次回のAAAS年次総会は、来年1月21日〜27日にカルフォルニアのアナハイム(Anaheim)で開催される。
○ 顧問会議/Advisory Meeting
3月9日(月)、顧問会議を開催し、当研究所より「研究評価の実施」、「平成9年度の研究活動」及び「平成10年度の研究計画」並びに当研究所の機関評価に向けての準備状況について説明した。顧問の方々からは、当研究所が今後取り組むべき課題などに関して貴重なご意見をいただいた。

○ 海外出張