







| No.112 1998 2 |
| 科学技術庁科学技術政策研究所
NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |
| 目次 [Contents] |
 | レポート紹介 Highlight of the New Report |
 | 研究会等紹介 Research Meeting | |
 | 海外事情 Oversea's Infomation | |
 | トピックス Topics | |
 | コラム Column | |
 | 主なプログラム Research Program | |
 | 最近の動き Current Topics |
Ⅰ.レポート紹介/Highlight of the New Report
(1)研究開発投資の活発な企業が求める高学歴研究者・技術者のキャリアニーズに関する調査研究
(NISTEP REPORT No.55)
第一調査研究グループ 和田幸男
前澤祐一
本報告は、企業が求める高学歴キャリアを有する研究者・技術者の実態について、わが国の研究開発投資を活発に行っている民間大企業28社の人事部門を対象に、インタビューを行いつつアンケート調査を実施しとりまとめたものである。
この調査研究の背景として我が国の科学技術基本計画において、日本の将来を担う科学技術人材確保のため大学院における人材の養成活動の強化を図っている。その結果、優秀な多くの学生が大学院修士課程へ、さらには博士課程へ進学するよう、在学中の経済的支援制度や博士課程修了後の経済的支援制度(いわゆる"ポスドク"支援制度)等の拡充がなされているところである。また一方では、この施策により増加する修士課程修了者や博士課程修了者の進路について、企業への就職が従来以上に期待されることから、企業サイドのキャリアニーズの実態を把握しておくことは、今後の科学技術人材の適切な育成、確保にとって重要である。調査項目は、
2.調査結果の概要及び考察
2−1 研究者及び技術者の採用
企業が求める研究者及び技術者のキャリアニーズとして、新卒(大学学部卒以上)採用、中途採用(以下本報告では経験者採用とする)及び技術系女性採用のアンケート調査結果について以下に示す。
2−1ー1 新卒者(学士、修士及び博士)の採用
(1)修士卒の採用比率
企業における技術系の新卒採用者に占める修士卒の割合の調査結果を表に示す。この表が示すように、修士卒者の採用は近年増加傾向にあり、その割合が20%以下の企業は約4%しかなかった。 特に高い業種は、その比率が90%以上の化学業界にみられる。
修士卒採用に係わる以下のような典型的な意見がある。
1)修士採用が高い企業
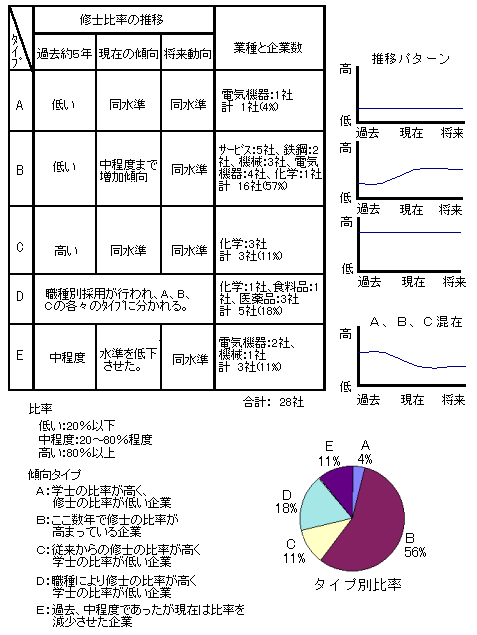
1)今後も積極的に博士を採用する。
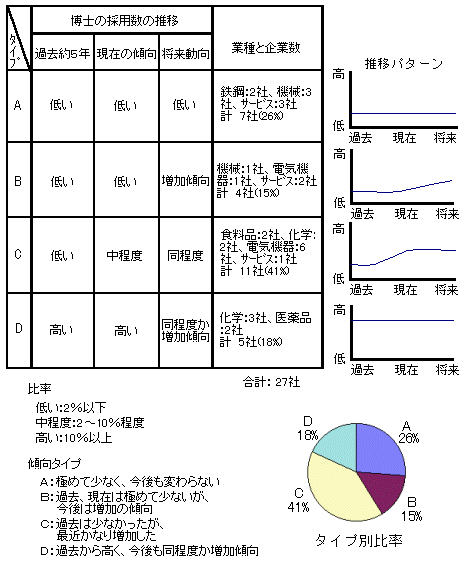
| ① ② ③ | 最近特に高キャリア採用化が進んだ、 修士卒採用率が非常に高いものの、博士卒採用率はあまり高くない、 博士卒採用率が高い、 |
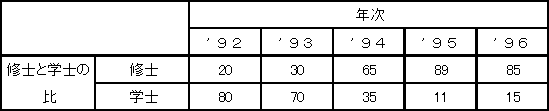
②修士採用率が高く、博士採用率は中程度(化学繊維メーカ)
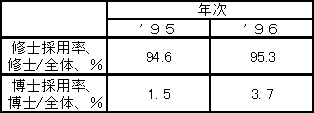
③博士採用率のもっとも高い(フィルムメーカ)
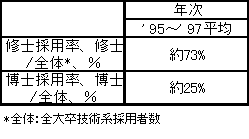
(4)本調査キャリアー比率結果と大卒就業者統計データとの比較
学校基本調査報告書(文部省)及び科学技術指標(科学技術政策研究所)による統計データを基に作成した、最近10年間の大卒者のキャリア別就業者比率を表4に示す。
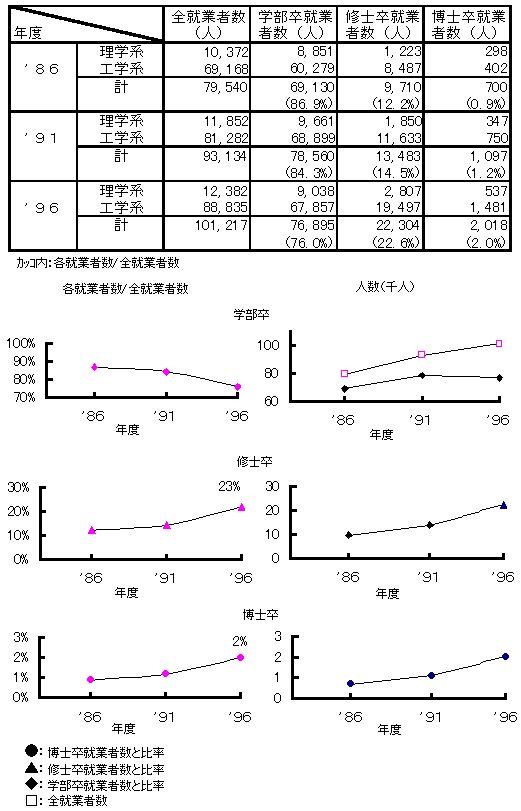
この表中の統計データ、96年理工系修士卒就業者率の23%及び博士卒就業者率の2%を基準として、本調査研究で得られたアンケート結果を比較検討すると以下のような結果が得られる。本調査研究結果によると、
(5)無業者問題
本調査研究のアンケート項目にはないが、大学側のキャリアと、採用企業側のキャリアニーズとの不整合を表す統計データの一つとして考えられるものに無業者がある。(学校基本調査報告書の定義:進学も就職もしていないことが明らかな者。家事手伝い、一時的な仕事に就いた者(大学院、高等専門学校のみ)はここに該当する。なお、研究生として学校に残っている者及び専修学校・各種学校・外国の学校・職業訓練校等への入学者も無業者とする)。
科学技術指標からの統計データの内、この最近10年間の大卒無業者率の推移の統計データを整理し、キャリア別無業者の実態を表5に示す。この表が示すように、各年度における景気変動によるバラツキもあるものの、学部卒及び修士卒者の無業者率は5%前後で、博士卒の無業者率はその5−6倍の20−30%である。
今後ますます大学においては高キャリア化し、博士卒者が増加することは間違いない。それに伴って博士卒者の無業者率が現在の比率で推移した場合、その数自体が一つの課題となっていく可能性がある。
そのため、博士卒者に対する国及び民間企業等の間の整合を積極的に検討する必要がある。すなわち、現在国が「ポストドクター等の一万人支援計画」を活用するなど、積極的な受け皿機構の適用と、博士卒者の質、量及び適正な活用のための流動化等、社会的な需要と供給の適合性を図ることについて、大学、国及び企業側がともに協力していかなければならない。
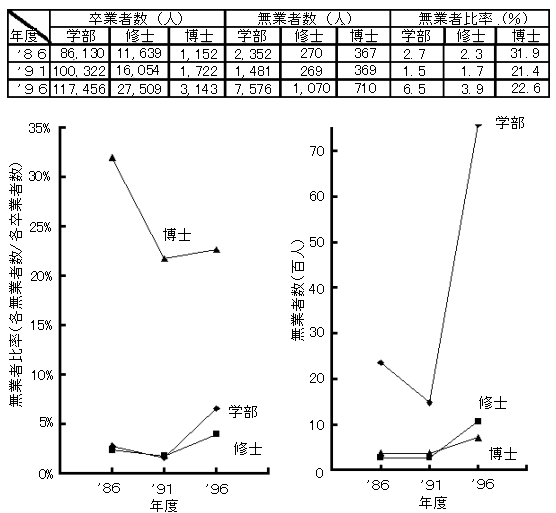
2−1−2 経験者採用
経験者採用の数については、バブルの崩壊により、ここ数年は大きく減少している企業もあったが、全体的に見れば、ここ数年で増加する傾向にある。そして、今後についても、バブルの時期のような大々的な経験者採用こそしないものの、積極的に経験者採用をしていきたいという企業がかなりあった。近年かなり経験者採用が多くなっている企業は、回答企業の4割近くになっている。
2−1−3 技術系女性の採用
技術系の採用者全体に占める女性の割合と今後の傾向性の調査結果を図1に示す。その結果、医薬品及び化学系企業の高い採用比率が特徴的である。
図2は、平成8年度学校基本調査報告書の統計データより作成した、大学の理工系及び化学、薬学系の女性就業者比率を示す。このデータが示すように、女性就業者比率は、薬学及び化学系の学科に特に多い。
本調査結果とこの図を比較検討すると以下のように考察できる。
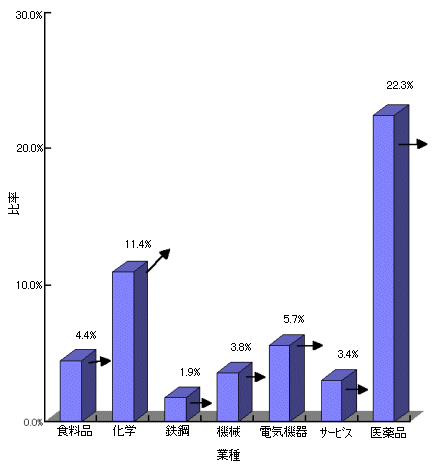
図2 96年度理工系の関係学科別女性就業者の比率*
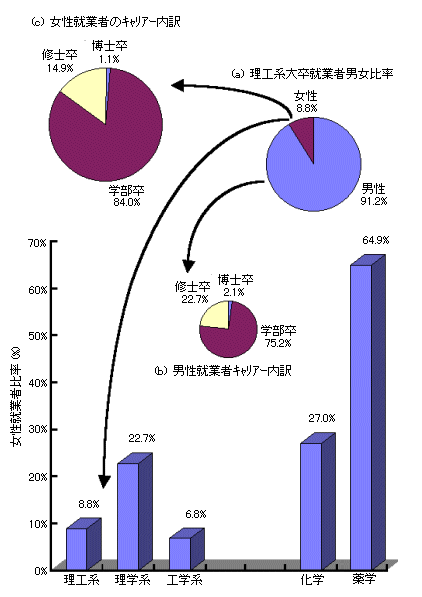
(1)基礎学力の充実
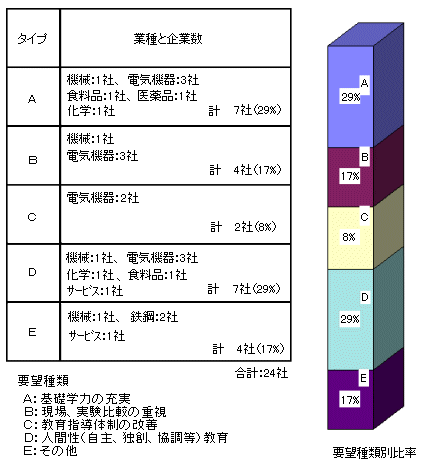
3.まとめ
本調査研究結果及び考察から、以下のように総括することができる。
第一研究グループ 後藤 晃
古賀款久
鈴木和志
研究費には、産業間で大きな差異がある。総務庁「科学技術研究調査報告」(1995)によれば、医薬品産業では売上高の8.03%(6,422億円)を、また、通信・電子・電気計測器工業では5.81%(22,407億円)を研究開発のために支出しているのに対し、石油製品・石炭製品工業の研究費は売上高の0.54%(678億円)、出版・印刷業では0.85%(312億円)にすぎない。研究費が技術進歩のインプットであるとすれば、産業の技術進歩のスピードは、投入される研究費に影響を受けるはずである。このような研究費の差異が、いかなる理由によって起こるのか、研究費を決定する要因はどのようなものか、という点を、個別企業レベルのデータを用いて、産業、および企業のレベルで検討することがこの論文の目的である。
企業ないし産業の研究費の水準、あるいは、研究費を資産、売上高等でノーマライズした研究開発集約度の決定のメカニズムについてのこれまでの研究は、大別すると次の二つに分けることができる。第一の流れは、シュムペーターに端を発するもので、イノベーションの決定因として、企業規模及び市場の集中を重視するものであり、このタイプの研究は今日、さらに進展し、専有可能性、技術機会、需要構造といった、より基本的な産業に固有の変数とイノベーションの関係に注目するにいたっている。第二の流れは、企業が研究開発投資を行う際の資金制約に注目するものであり、このタイプの研究では設備投資関数との対比あるいはアナロジーで研究開発投資関数をとらえようとするものが多い。我々の研究は、独自のサーベイに基づくデータベースを用いてこの二つの流れを統合する形で研究開発投資の決定のメカニズムを検討する。
2.推計モデル
本稿では、研究開発投資を、専有可能性、技術機会という研究開発投資のもたらす期待収益に関する変数と、研究開発投資のファイナンスに関わる変数(当期首のキャッシュフローおよび借入額)の両方を用いて説明することを試みる。さらに、研究開発投資は、市場における将来の需要条件にも影響を受けると予想されるので、需要の代理変数として当期の売上高を導入した。研究開発活動の結果生み出される技術を情報として、技術のみを販売することは困難であり、また、研究開発の結果、急激に売上高が成長することはないと見なすことができる場合には、この売上高が研究開発を規定する変数の一つとなる。計測されるモデルは、以下の(1)式で表される。
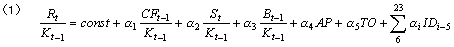
3.使用データおよび推計方法
研究開発費は、科学技術庁「民間企業の研究開発活動に関する調査報告」において集められたデータを基礎資料として使用した。また、有形固定資産残高、キャッシュフロー、総負債額、および売上高は、財務諸表をもとに作成された日本開発銀行のテープをもちいた。
専有可能性、技術機会は、科学技術政策研究所で実施したイノベーション・サーベイのデータを用いた(「イノベーションの専有可能性と技術機会」NISTEP REPORT No.48参照)。業種ダミーは、日本開発銀行業種分類基準に従って、標本製造業227社を17の産業に分類し設定した。標本製造業227社は、科学技術庁資料により1989-1994年の間継続的に研究費のデータがとれ、かつ開銀財務データによりキャッシュフロー、有形固定資産総額、総負債額が利用可能な企業である。本推計に際しては企業規模を考慮するために、各企業の1988年度売上高の中位値で、227社を大企業グループと中小企業グループに二分した。本稿では、OLS及び操作変数法(IV)をもちいて(1)式を推計した。OLSの推計結果は表1、表2に示されている。
4.結論
この推計結果から、以下の点が知られる。(1)OLSによる推計結果と操作変数法による推計結果にはほとんど差がなく、説明変数の外生性は保たれていると思われる。(2)モデルは個別企業レベルの計測にしてはきわめて当てはまりがよく、大企業グループについては、企業間の研究開発投資集約度の全変動の約70%を、中小企業グループでも約40%をこのモデルで説明している。(3)専有可能性、技術機会という産業固有の変数の係数は、有意に正の値を示している。ただ、専有可能性の係数の値は正であるものの、中小規模企業グループで有意性が低いものが多かった。(4)企業固有の変数については、大企業グループと中小規模企業グループで顕著な差異がみられる。すなわち、大企業については、キャッシュフロー、中小企業については売上高が正で有意となっているケースが多い。
キャッシュフローについては、従来は、いわゆるシュムペーター仮説のなかで「企業規模が大きいほどキャッシュフローが豊富であるから研究開発投資をより活発におこなう」とされ、大企業の研究開発投資の決定要因とされてきたが、最近ではこれとは逆に「キャッシュフローは、研究開発集約的な企業の中でも、小規模企業の研究開発投資に対し有意な説明力を持つ」とする議論もある。
我々の得た結果は、中小企業ではなく大企業の研究開発投資にキャッシュフローが影響を与えていることを示している。大企業は、相対的にキャッシュフローが豊富であろうが、他方で研究所を持ち多数の研究者を雇用し制度化された大規模な研究開発を行っている。さらに、研究開発能力は築き上げるのに時間がかかり調整費用もきわめて高いため、大企業においては、毎期の研究開発費支出は固定性が高く、金額も大きくなりがちである。その結果、キャッシュフローの制約が効くことになる。
これに対し、小規模企業では、研究開発の制度化の程度が低く、また企業として研究開発能力を長期的に維持しようとする性向は弱く、研究開発の規模も将来の売上高に応じてより柔軟に変動する。そのため、キャッシュフローの額は相対的に限られているにも関わらず、その制約が効くことは少なく、むしろ研究開発の結果得られる製品ないし製法に関わる売上規模の予想に影響されるものとみられる。
専有可能性、技術機会は、多くの場合、企業の研究開発投資に正の影響を与える。したがって、特許制度ならびにその執行を発明者の権利保護を強化する方向に改める等によって専有可能性を高めること、また、産学の連携を強める等により企業の技術機会を豊かにすることは、いずれも、研究開発投資を一層活発にするうえで有効な政策と言えよう。
大企業はキャッシュフローの制約が効いている可能性が高いため、その技術開発のケイパビリティを維持、強化するために、租税特別措置等は有効であろう。他方、中小規模の企業にとっては、そのような優遇措置の有効性は低いものと思われる。むしろ、中小規模企業の研究開発投資の促進には、特許には発明者の権利保護の強化などにより企業レベルでの専有可能性を高め、研究開発の成果が研究開発を行った企業に帰着する程度を高め、研究開発が自らの売上高の増加につながるという予想を事前に持てるようにすることが必要であろう。
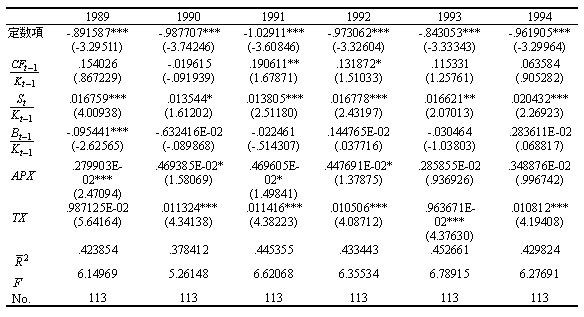
表2 大企業の研究開発投資決定要因 (最小自乗法)
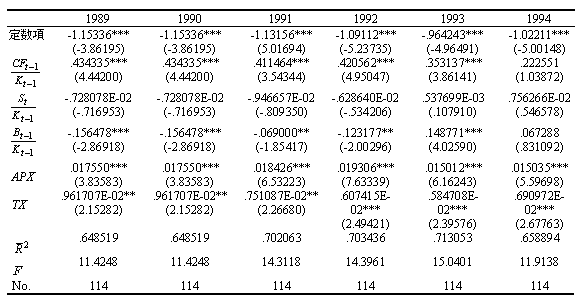
***:1%水準で有意(片側検定) **:5%水準で有意(片側検定) *:10%水準で有意(片側検定)
第4調査研究グループ
情 報 分 析 課
第2調査研究グループ
○ 海外出張報告
(1)「オランダアムステルダム大学主催EUプロジェクトとの連携研究の推進およびオランダ科学技術政策策定システムの調査」、「フランス鉱山大学イノベーション社会学センタとの共同研究の推進およびフランス科学技術策定システムの調査」
第2研究グループ 藤垣裕子
1)アムステルダム大学主催EUプロジェクトとの連携共同研究
EUの第12総局(科学技術政策関連)の第4次Framework ProgramのTSER部門(Targeted Socio-Economic Research)からfundingを得ている同大学主催で、欧州の6大学(ドイツのビーレフェルトの他イギリス、スイス、ギリシャなど)のプロジェクト(The Self Organization of the European Information Society)と当研究所との共同研究の連携についての打ち合わせを行った。このプロジェクトは主に、科学技術情報の自己組織化モデルおよび科学者行動・コミュニケーションプロセスのモデル化をメインの目的としている。政策との関連で言えば特に、科学技術政策の優先分野投資が、実際の研究活動へ与える影響(論文数とシェア)を考えた場合、その優先投資の投資効率を決める国ごとのR&Dシステムの差(National-dimension)を決める要因を探求することが挙げられる。科学者行動・コミュニケーションプロセスの差は、このnational-dimensionの1つの要素と考えられ、これについての分析を日欧比較の形で行うことで同意した。
2)オランダ科学技術政策システムの調査
上記のnational-dimensionを考える上でも参考となるオランダの科学技術システムについてのヒアリングをおこなった。
訪問先は以下の通り。現国連大学学長(兼ユトレヒト大学学長)van Ginkel氏、Ocenw(教育文化科学省)科学研究政策局長Tindeman氏、国際課長Broesterhuizen氏、EZ(経済省)技術政策担当局副局長Huijts氏、産業サービス局長Volman氏、NWO(科学技術財団)政策部門長Plompen氏、 化学部門長Hesselink氏、AWT(科学技術諮問会議)議長Heeringen氏、STW(応用技術財団)所長le Pair氏、プログラムオフィサーBoots氏ほか、VNSU(大学連合)所長van den Maagdenberg氏、同研究評価アドバイザBlaauboer氏、アカデミー(学術会議に相当)会長Moen氏、TNO(応用技術財団)技術政策研究センタSmits教授、研究者Jacob氏、Enzing氏、アムステルダム大学教授Blume氏(デンマーク、フィンランド、ベルギーのリサーチカウンシル設立の際のAdvising-committeeの長)、アムステルダム大学研究政策アドバイザVerkleij氏、ツヴェンテ大学科学技術社会研究センター教授Rip氏(オーストラリア、フィンランド、のリサーチカウンシル設立の際のAdvising-committeeメンバ、フランスOSTのboard-member.前欧州科学社会学会会長)および共同研究者van den Meulen氏(OCV:予測委委員経験:Foresightレポートは1分野につき一冊)
オランダの科学技術システムの特徴は、大陸ヨーロッパのなかでアメリカに対する責任を意識して行われており、国内の対立する現場の意見をボトムアップ的にすいあげて調整していくタイプである。多くの委員会や利益団体のなかでのチェック機構、バランス調整、透明性(transparency)、評価機構が働いている。ボトムアップを取ることのよい点として、A)組織自体の発展(organic-development)を大切にできる、B)次世代の育成に役立つ、C)各人が各自の労働にプライドをもって仕事ができる、の3点があげられている。他国のトップダウンのありかた(イギリスの資金配分に直結したforesight、ドイツのマックスプランク研の運営)などについては、次世代の潜在的可能性をつぶしている、という点で非常に批判的である。彼らは常に「How to create organic model for future generation?」という思想をもって動いている。
また欧州のなかでの科学政策先進国という評価が高く、欧州、豪州などでリサーチカウンシルや評価制度の体制整備が行われる際には、オランダに視察団が送られたりアドバイスの依頼が来たりしている。その報告書の一部は出版されており、科学技術政策策定システムについてのすぐれた比較研究がいくつか出版されている。(書籍、論文の双方)。科学技術白書、経済白書「Knowledge-in-Action」などで、知識をどういう政策に生かすかについて高度にintellectualな内容が書かれる。欧州のSTS(Science-Technology-Studies)のトップレベルの研究をしながら、かつ政策研究にもたずさわる研究者が存在する。政策作成行為(行政官の仕事そのもの、あるいは行政官と研究者の共同作業)を語る語彙が豊富である。また自らのシステムを語るときの語彙および枠組みが豊富である。
オランダでは、行政官(government-level)と研究者(research-level)との間をつなぐインタフェース的仲介機構(intermediate-level)が非常に発達している。ここには、文部省からお金をもらって研究費を再配分するresearch-foundation:NWO,研究者の集団でありながら研究評価もおこなうアカデミー(日本学術会議よりも評価や分野予測foresightをおこなう上でずっと政策へのコミットメントが高い)、各省庁にアドバイスをおこなうアドバイザリーカウンシル、セクタカウンシル,各分野の発展予測と社会との関係を議論するforesight-committee、大学連合(大学と教育文化科学省の仲介機関)、さらに大学のresearch-policy(教育文化科学省への対応と内部の予算配分)をアドバイスするプロのコンサルタントまで存在する。
重点投資の特徴としては、特別な投資分野を「選ぶ」のではなく、それらを「統合して」「再方向付け」を行っている。つまり、not choosing special target between the area, but trying to bring get together within the area, trough re-orientationという思想で動いている。何故なら、特別な投資分野を「選ぶ」( choosing special target between the area)を行うと、選ばれなかった分野が次世代を育てられないためである。次世代の成長の可能性を保つ(maintain the possibility of the next generation)ために、多くの分野が共同してできる分野を作る、あるいは共同による再方向づけ(specific-targetへのre-orientation)を行っている。
foresight(科学技術予測)については、イギリスのように予算に直結させず、各分野の将来の方向性を描く主旨で行われる。異なる分野をlinkして、バランスを取る、ことに進歩(progress)が見られる。またオランダの評価システムは20年ほどまえから根付いており伝統がある(もともと評価をしてさらに先をめさす伝統があり)。そのためオランダの評価システムはヨーロッパの人達からも高い評価を受けており、OECD、ユネスコ、欧州各国、時に米国から視察団が来る。評価の基本思想は、「Value for Money」(イギリス)に対し「Self-improvement」(オランダ)である。
日本がオランダの科学技術政策から学べることは以下のようにまとめられる。(1)他国への科学政策のadviseを行える実績をもつこと、(2)プロのコンサルタントがたくさん存在し、中間仲介機構が発達している点、(3)決定機構の多様性から多様な意見を反映できるシステムを持つ点(日本のシステムも、さまざまな意見を調整し、均衡をとっていく、という点で評価できるのでは。異なる点は、「不透明」「オープンでない」「評価が甘い」点だろうか。)(4)ボトムアップをいかにして充実させるかについて、独自の対話システムを構築している点、(5)対話を行う土壌:対話の習慣、透明性、情報をオープンにして議論する習慣。ネゴシエーションがオープン(密室判断でない)であり、ネゴシエーション、調整というものに対してプラスの評価をもっている点、(6)重点領域を「選ぶ」のでなく、重点課題解決のためにいくつかの分野を「統合し」「再方向付け」することをめざしている点。このことは技術予測→政策へのルートとしてユニークである。またこのことの根本に「次世代の可能性をつぶさない配慮」がこめられているのは特筆すべき点である、(7)評価に対して前向きである点、(8)民間の意見をたくみに取り入れるシステムの充実(評価の公表制度、NWO、STWへの民間人の参加。80年代からの議論の成果)、など。
3)フランス鉱山大学イノベーション社会学センタ(CSI)との共同研究
日本とフランスのサイエントメトリクス(科学技術活動の数量データを用いた分析)の研究現状の交換(日本側のプレゼンテーションと意見交換)および日本とフランスの公的研究機関研究室調査の方法論についての議論をおこなった。CSIのM.Callon氏、P.Laredo氏、フランスOST(Obsavatoire des Scinece et des Tecniques)のRemi Barre氏、CNRSのSerge氏らを交えた研究会におけるプレゼンテーションでは、(1)NISTEPにおけるS&Tindicatorについて、および(2)NISTEPにおけるサイエントメトリクスについて報告をおこなった。特に(2)では、まず政策志向研究としては、現在研究所において行われている政策ドキュメント(科学技術答申23号分)を用いた語分析および共語分析の内容、および科学技術優先分野投資と論文生産との関係を決定するnational-dimensionの分析について意見の交換をおこなった。また研究活動そのものを対象とした研究では、公的研究機関の研究室分析に用いた方法論R&D-dynamics-chartの内容について、および特定の分野を対象とした論文内容分析contents-analysisとimpact-factorのlinkについて議論をおこなった。またこの3月に日本において開催されるSTS国際会議でのサイエントメトリックス関連のセッションの内容についての議論もおこなった。
4)フランス科学技術政策システムについて
オランダと同様にフランスのnational-dimensionについて知るためにフランスの科学技術システムについてのヒアリング調査をおこなった。訪問先は以下の通りである。MENRT(国民教育研究技術省)国際局長Megard氏、同日本担当Bartoli氏、CNRS プログラム戦略局プログラムサービス課長Rubel氏、Crozet氏、OST(科学技術動向観察センタ)センタ長Barre氏、ADEME(環境エネルギー庁:Problem-solving Funding Agency)評価委Breitenstein氏他、INRA(生命技術研究所) 評価部Phillipe氏。
フランスの戦略的政策は主にCIRSTで1996年秋作られた。しかし1997年6月の首相交代(政権交代)で内閣改造、および省庁内再編がすすんでおり、これは実質動いていない。公的研究機関は以下の2つの面から分類可能である。1つは予算面からの分類である。(1)EPST=研究員の給与(全予算の約80%を占める)がすべて省から支払われる研究所、INRA(生命技術農業研)、INRETS(健康科学研)などがこれに相当する。(2)EPIC=給与の50%しか省から支払われない。あとはコントラクトから得る。CEA(原子力エネルギー研)、IFREMER(海洋研)などがこれに相当する。もう1つは評価面からの分類である。(A)純粋な科学的価値で評価(Excellency, Scientific-driven)される研究機関:CNRS、大学、INSERMなど。(B)社会への影響、効率で評価(Impact, Efficiency)される研究所。CIRADなど。(C)両方向から評価(1/2 scientific-driven, 1/2 impact, efficiency-driven)INRAなどがこれに相当する。
さらに評価については、フランスの評価の5本柱として以下が挙げられる。(1)CNE:大学評価(専門委):大学ごとに1冊(cf.オランダでは分野ごとに1冊)、(2)CNER:大学評価(一般のひとの参加)、(3)CNRS-CN:CNRSと関連のあるラボ(3階層に分類される)の評価、(4)国研の評価(国研ごと)、(5)公共事業評価(Problem-Solving-Funding-Agencyでの公共事業のモニタリングと事後評価)
(2) The Triple Helix of University-Industry-Government Relations: "Future Location of Research" Conference(「国家研究開発体制の新しいモデル」に関する第2回国際会議)出席及び発表
第2研究グループ 藤垣裕子
テーマは、「各国における科学技術政策の戦略動向」「国の研究開発システムにおける大学の役割の変化」「官産学連携の新しいモデルをめぐって」「技術移転」「政策形成の新しい担い手」「基礎研究から応用研究へのリニアモデルに代わるモデルは何か」「各国のfunding-systemの比較研究」、あるいは各種国際比較研究、など多岐にわたっており、決して日本語における産学官共同という狭い範囲の話しに限ったものではない。国家研究開発体制の新しい方向性を考える会議(97年3月のNISTEPワークショップ:Strategic Models for the Advancement of National R&D System:研究開発推進体制のための戦略的モデル)の国際会議版のような内容であった。
近年欧米で議論されている研究開発システムに関する話題である、(1)科学技術を経済発展に貢献させるために、大学の研究システムはどう変わってあるいは変えてゆくべきか、(2)同様にpublic-sectorの研究機関運営をどうしてゆくべきか、(3)同様の文脈でfunding-systemをどのように構築すれば研究のcompetitiveを増すことができるかなどが議論された。この議論においては、従来の産、学、官、の枠を超える必要があり(たとえば国の経済発展への貢献は「産」にまかせておけばよく、「学」には関係ない、とは言えなくなってきているなど)、その意味で本国際会議の名前の中でTriple-Helixという言葉が用いられている。日本では産業技術政策、学術政策、高等教育政策、科学技術政策、の4つがこれまで独立して各省庁で行われてきたが、この4つの境界を上記3つの文脈(科学に求められるものの変化、大学や研究機関に求められるものの変化)のなかで問い直し、再編(re-shuffle)を即すような志向をもつ会議であった。
同会議の第1回は1996年1月にアムステルダムにおいて開催されており、第3回会議は2000年4月にブラジルのリオデジャネイロで開催の予定。また当会議の成果は以下の4つの方法で公表される予定である。(1)単行本の発行、(2)Sicnece and Public Policy誌の特集号、(3)Industry and Higher Education誌(UNESCO助成)の特集号、(4)Latin American Studiesのシリーズのなかの本の出版
(備考:本会議の主催者の1人は本年3月にSTA国際客員研究官として2週間NISTEPに滞在する予定である。「The Triple Helix of University-Industry-Government Relations」という演題で、所内講演会が企画される予定。)
研究所からの個別発表に対する反応としては、(1)The Future Location of Knowledge Differentiation and Integration in Academic, Public, and Private Sectors: From the Point of View of "Validation Boundary" Problem. という発表については、OECDのS&T Policy Divisionの方から、「科学者共同体の特徴を記述する概念:policy-makingする際のguidelineとしてまとめたらどうか。」というコメントを得た。(2)Concept Evolution in Science and Technology Policy: The Process of Change in Relationship among University, Industry and Government. (科学技術答申36年間23号分のデータベース化と共語分析:新概念の出現と基本的政策概念の変遷)については、full-paperが上記の4つの公表方法のうちどれかで発表される予定である。
(3)「1997年度 技術・経営戦略 米国調査」
第3調査研究グループ 渡辺俊彦
先月1月13日〜25日の間、(財)社会経済生産性本部主催により主として民間企業人から成る総勢12名の調査団を編成して、米国の主要な機関を訪問し、経営戦略、技術戦略、産学官共同研究、ベンチャー・ビジネス等に関して意見交換の形式により調査を行った。訪問機関は、Industrial Research Institute, NSF, Bethlehem Steel(工場見学を含む), Chrysler(工場見学を含), アリゾナ州立大学リサーチ・パーク, Arizona Technology Incubator, Boeing(工場見学を含む), SDC(Strategic Decisions Group), Clarent Corp(ベンチャー・ビジネス), Center for Software Development(インキュベータ), Access Internet Solutions(ベンチャー・ビシネス)の11機関である。特に小生の任務は、産学官共同研究、ベンチャー・ビジネス、インキュベータ等に焦点を当てた実態調査であった。今回の調査を通して特に強く印象に残った点を挙げれば、まずベンチャービジネスが極めて容易に育てられる環境があるという点である。優れたアイデアがあれば、ビル・ゲイツのようになれるのは、決して夢ではない。魅力のあるアイデアに対しては、エンジェルをはじめ、ベンチャー・キャピタルはもとより、銀行までが、積極的に投資をする。企業や大学も惜しみなく手助けをする。特に、シリコンバレーは、ベンチャービジネスが起因となって発展してきた地域であるため、新規のベンチャーが容易に育つ環境ができ上がっている。その他の地域でも、インキュベータが、活発に活動し、起業家の能力等の不足部分を補うため綿密に診断し、手当をする。州や企業や大学がその地域の発展のために協力して、インキュベータを介して起業家を助ける。投資家が新規ベンチャーに投資し易い仕組みも作られている。「リスクを喜んで甘受し、失敗を恐れない。成功したら有名になれる」、これがシリコンバレーの文化だと、CSD(Center for Software Development)のSandy Herz社長は語った。
もう一点印象に残ったのは、企業の共同研究開発の取り組み方である。訪問したどの製造企業も、産・官・学の共同研究、産・学の共同研究及び産・産の共同研究を非常に活発に進めている。自社だけでは開発が困難と思われるアイデアは積極的に、共同研究テーマとして推進する。たとえ競争相手であっても共同研究をする。また、研究開発費を増加させない方策として、サプライヤーからの改善やコスト低減のアイデアを積極的に取り入れ、サプライヤーと共存共栄を図りながら、研究開発費を抑える努力をしている。Chrysler社のゼネラル・マネジャーのHoward Padgham氏に、出資した研究開発プロジェクトが失敗したときの対応は? と問いかけると、「リサーチは結果が見えないものだ。失敗は当然であり、失敗したことが分かっただけで、それで十分である。」との回答が返ってきた。ここでも、リスクに挑み、リスクをものともしない心意気を垣間見ることができたような気がする。
なお、今回の調査結果は、後日、(財)社会経済生産性本部から調査報告書としてまとめられる予定である。
日本東京の空の下で
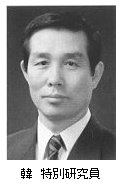 私は昨年8月、韓国科学技術処から科学技術分野の政策研究の為、日本に派遣されてきた韓亨浩(ハン ヒョン ホ:HAN,HYUNG‐HO)と申します。
私は昨年8月、韓国科学技術処から科学技術分野の政策研究の為、日本に派遣されてきた韓亨浩(ハン ヒョン ホ:HAN,HYUNG‐HO)と申します。
科学技術政策研究所の第2研究グループで、1999年8月までの2年間勤務することになりました。この期間中の私の研究対象は、祖国の政府出損研究機関に対する合理的な機関運営評価とその評価結果の効率的な活用のため日本・米国など先進国と比較分析し方案を探し出すことです。
最近の経済問題にもかかわらず、私を日本へ送ってくれた私の祖国と、日本語の勉強と研究が心地よく出来るよう配慮して下さっている日本科学技術政策研究所に心から感謝いたしております。 1998年2月で6ヶ月目を迎える日本での感想を簡単にお話いたします。
・ 科学技術政策研究所での生活
日本科学技術政策研究の産室である科学技術政策研究所!
わずか日本に来て6ヶ月間ではありますが、私の視野に写った科学技術政策研究所は夜遅くまで研究所の灯りが点いているほど所長、研究員が自分の分野で最善を尽くす真剣な眼差しが印象的でした。ある時は先に家に帰るのが申し訳ない時もあるぐらいでした。外国人を含め各機関に派遣された優秀な人材が共に熱心に研究し、その研究した内容を発表し、検討会議やセミナーなどを通じ優秀な研究結果を出すなど彼らの活発で積極的な研究活動に今の日本を見ているような気がしました。まるで優秀な研究所とはただ成り立っていくものではなく構成員たちの血と涙の結晶で無限に造られて行くものだと見せているように……。
研究で忙しい中でも私の下手でなれない日本語を誠意をもって聞いてくれてまた答えてくれる心温かさ・親切・丁寧さ・思いやりに感動しました。そして一つ間違えれば孤独しやすい外国人の私を気遣って下さった所長のご配慮は心やすらぐものでした。
私の研究所での毎日の生活は、午前中がこれからの研究に必要な日本語の勉強、午後には研究と関連した資料集めです。やはり一つの国の言語を覚えるということがどんなに大変で難しい事かを切実に感じております。この研究所での生活が私の公務員生活中一番の思い出になるよう甲斐のある期間にする事を心に誓いながら今年創立10年を迎える科学技術政策研究所のご発展を心からお祈り申し上げます。
・ 日本での生活
現在私は妻と東京韓国学校に通う二人の子供に恵まれ(長女:高校一年生、長男:中学三年生)東京都中野区に住んでおります。家族と長期間外国で生活するのは今回が初めてでいろいろな面で負担にはなりましたが、日本の方の親切と韓国駐在員の皆さんのおかげですぐ適応できました。今の生活が私の人生において良い経験になると思います。
日本人の親切は先天的なものでしょうか、後天的なものでしょうか。来て間もないころでした。ある地下鉄の駅のプラットホームで電車の乗り方が分からなく困っていた時です。急いで地下鉄に乗り込もうとしていたある日本の人が私を見てわざわざ私の目的地までついて来て教えてくれた事がありました。その他にも色々あって全部述べる事は出来ませんが、日本人は親切が体になれてて当然であり自然な事と思っているかもしれません。
今年1月にたくさんの雪が降りました。その日は帰りが大変で東京市民の足である電車が一部路線を除いてはすべて運行中止になり大きな障害をもたらしましたが、不平一言漏らさず秩序を守り譲り合い我慢する市民、そして翌日何もなかった様に正常な生活に戻っている彼らの生活で、先進国といわれる国の姿をみることが出来たように思いました。そのお陰で私は普段40分で帰れる道を5時間掛けて帰りましたが………。
韓国首都ソウルから2時間弱で付いてしまう日本列島。そして中心部東京!日本の現在と過去が息している所。最先端製品と素朴な手芸製品が方を並べている所。超高層ビルと庶民住宅が混在している所。夜のネオンと昼の忙しさ及び秩序が併存している所。ここが日本の首都東京の姿ではないでしょうか。科学技術の発展で更に短縮しているソウルと東京間の所要時間ぐらいもっと近くなれる韓国と日本になる事を切実に願っております。
(韓 特別研究員は日本語が堪能であり、本原稿は本人の日本語による記述を記事にしたものである。)
第一調査研究グループ 和田幸男
表1及び表2は、最近十年間の理工系修士及び博士進学率の推移を示している。これらの統計データが示すように、両者とも急激な増加傾向にあり、十年間で約二倍程度の増加率をみている。
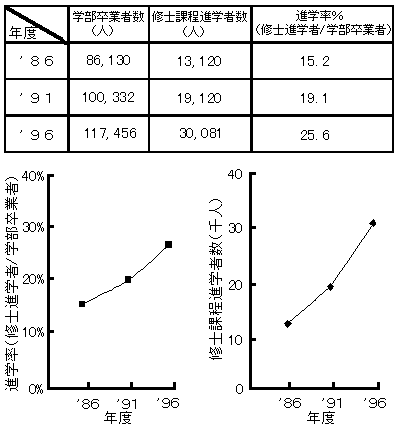
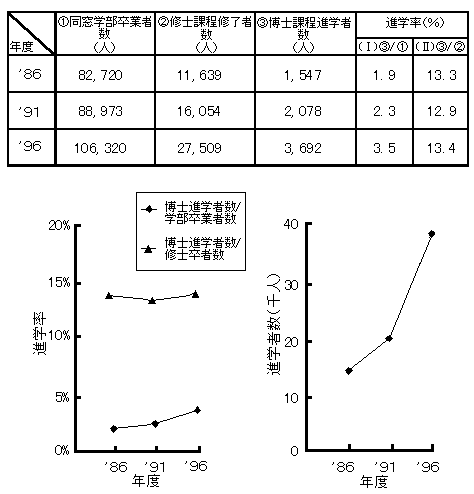
また、1996年7月に閣議決定された「科学技術基本計画」においては、科学技術系人材の養成確保が科学技術振興策の一つとして挙げられている。そして、このための具体的な施策として、「大学院の拡充」や「日本育英会奨学金の貸与人数の拡充」「ポストドクター等1万人支援計画の達成」等が挙げられている(科学技術基本計画)。すなわち、科学技術系人材の養成確保を図るために、大学院の学生数の拡充により、大学院による養成活動を一層強化しようとしている。そして、大学院への進学促進策として、在学中の経済的支援制度(例:日本育英会の奨学金制度、日本学術振興会の特別研究員制度(D.C.)等)を拡充するとともに、博士課程修了後の経済的支援制度(例:日本学術振興会の特別研究員制度、科学技術振興事業団の科学技術特別研究員制度等)の拡充を図り、より多くの学部学生が修士課程へ、さらにはより多くの修士課程の学生が博士課程へ進学すること促している。
しかし大学院の学生、中でも博士課程修了者の就職先機関側の実情については、十分には把握できていない。たとえば、大学や国立試験研究機関等のポストは今後の学生数の減少や行革等の実情を考えれば、採用人員が減ることはあっても増えることはないことが容易に想像できる。そのため今後、民間企業の大学院修了者の採用が、従来以上に増加することに期待せざるを得ないと予想される。
そこでどのような企業が、現在及び将来に亘ってどのような目的で、どの程度、高学歴者の就職が増えることを望んでいるのか、また企業にとって現状の大学院の研究及び教育内容がどのように改善のされることを望んでいるのか等、企業サイドの実情を調査する必要があった。
このような背景から本調査研究は実施され、その実態及び今後の将来動向を把握することができた。
第2調査研究グループ
平成10年3月16日〜22日、「科学技術と社会に関する国際会議(STS国際会議)」及びその一環として公開シンポジウム「遺伝子治療を考える市民の会議からの報告」が行われる。
第3調査研究グループ
1.開催日時 : 平成10年3月17日(火)〜18日(水)2.場 所 : 兵庫県公館(神戸市中央区下山手通4丁目4番1号)
3.招待講演者 : 14名(うち海外より12名)
4.開催趣旨
地域における科学技術の振興は国の政策としても明確に位置付けられ、着実に進展しつつあります。科学技術は産業競争力の基盤となっているため、地域における科学技術の振興が産業振興施策と密接な関わりを有しているほか、近年では地域社会のニーズに見合う科学技術の開発に向けて多様な科学技術主体の創出が行われています。
地方公共団体が支出した科学技術関係経費は国の科学技術関係経費の約3割に相当しているほか、その支出内容も科学技術の基盤整備のみならず企業支援、人材育成、国際交流など多様化の傾向を示しております。これは、地域における科学技術の振興が地域社会のニーズに応えるものになりつつあることを示しております。
特に、科学技術活動における交流事業については地域社会の特性にのみ依存するだけでなく、科学技術資源を共有し知的資産を共創するという外部経済効果が期待されることもあり、地域間連携、あるいは広域連携としての動きが見られるようになりました。一方、経済のグローバリゼーションの進展に伴い、地域における科学技術分野での国際交流の実績も着実に進展を見せております。こうした国際化の動きは同時に社会的諸活動のボーダレス化を加速しておりますが、すでに科学技術活動については国境を越えた新たな「地域間連携」が進展しつつあります。この新たな国際地域間連携は、特にアジア諸国との密接な関わりの中に見出される可能性があり、科学技術活動の拠点形成あるいは経済活動の相互依存関係に大きく寄与する可能性を内在しています。
今回の国際ワークショップはこうした国際的な新たな地域間連携について、地域科学技術の振興の視点から、現状の認識と今後の可能性について理解を深めることを目的としております。このため、アジア地域を対象に、伝統地場産業間における技術開発協力、天然資源の有効利用、地域間で共通した環境保全問題等に関する地域間科学技術協力、地域におけるインキュベータ・サイエンスパーク間での企業創出や技術開発に向けた国際協力のありかた、企業化プロセスの地域での展開、ならびに地域の科学技術行政における国際的連携に関する事例等々の紹介、あるいはその課題についての報告及び討論を通じ、地域間連携の国際展開についてそのあり方と課題について模索します。
| プログラム | ||
| 3月17日(火) | 9:00 |
開会セレモニー 佐藤征夫 科学技術政策研究所 所長 貝原俊民 兵庫県知事 |
| 9:20 |
基調講演 山野大(関西経済連合会 科学技術委員会委員長) | |
| 10:00 |
基調講演 Young-Ho Kim(韓国、慶北大学学長) (10:40〜11:00 休憩) | |
| 11:00 |
セッション1 国際地域間科学技術協力の枠組み 権田金治(科学技術政策研究所、日本) Kong Deyong(中国、国家科学技術委員会) H.Campbell(ニュージーランド,研究科学技術省) | |
| 12:00〜12:30 ディスカッション | ||
| 12:30 | 昼食 | |
| 14:00 |
セッション2 企業化プロセスの地域での展開 Lee Kink Ting(シンガポール、科学技術審議会) Kobkeao Akarakupt(タイ、科学技術環境省) K.Thirucheluan(マレーシア、科学技術環境省) James Langridge(オーストラリア、イラワラ・テクノロジー) | |
|
15:20〜15:50 ディスカッション
(15:50〜16:10 休憩) | ||
| 16:10 |
セッション3 地域科学技術資源の活用 Ashok Jain(インド,国立科学技術開発研究所) Nguyen Van Hieu(ベトナム、国立科学研究センター) NikolayKondrikov(ロシア、極東州立大学) 柿崎文彦(科学技術政策研究所、日本) | |
| 17:30〜18:00 ディスカッション | ||
| 3月18日(水) | 9:00 |
セッション4 技術開発と企業創出のための場 J. Moersito(インドネシア、技術評価応用庁) Nuna Almanzor(フィリピン、産業技術開発研究所) 千川純一(兵庫県先端科学技術支援センター、日本) |
|
10:00〜10:30 ディスカッション
(10:30〜10:50 休憩) | ||
| 10:50〜11:50 総括討論 −国際地域間連携のあり方− | ||
| 11:50 |
閉会挨拶 國谷実 科学技術政策研究所 総務研究官 | |
| 12:00 | 播磨科学公園都市視察へ | |
企画課
科学技術政策研究所では、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月7日内閣総理大臣決定)を踏まえた研究評価を行うため、「科学技術政策研究所における研究評価のための実施要領」を策定いたしました。
○ 海外出張