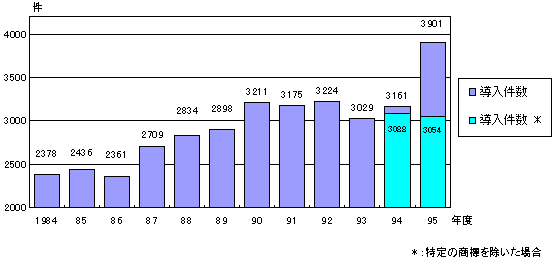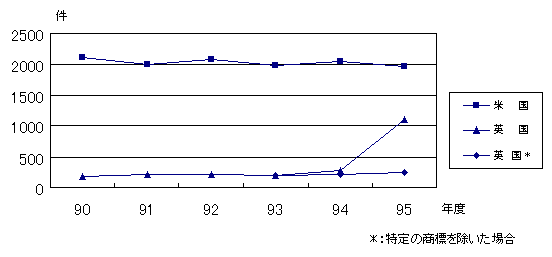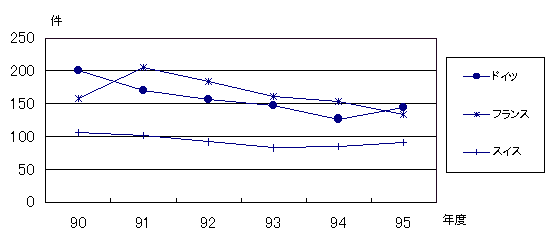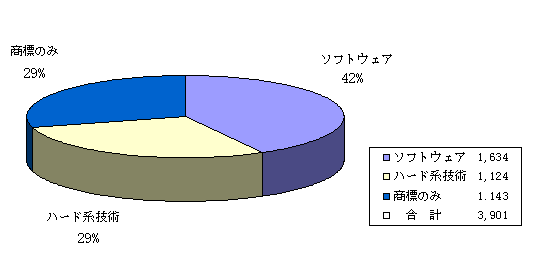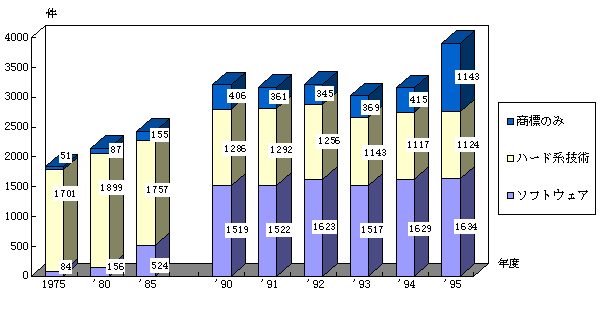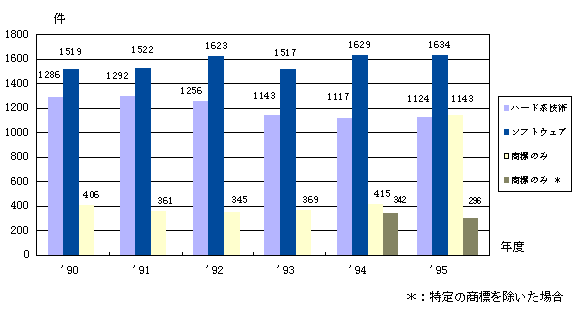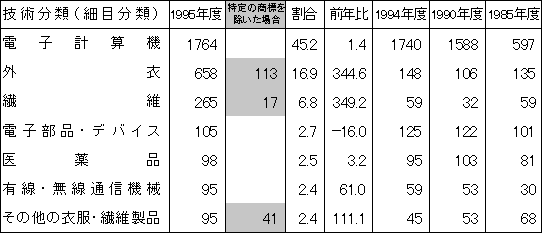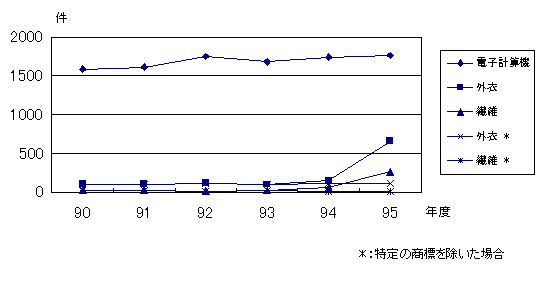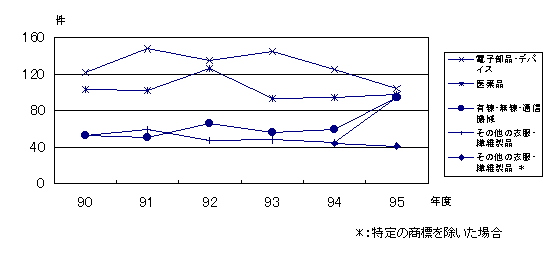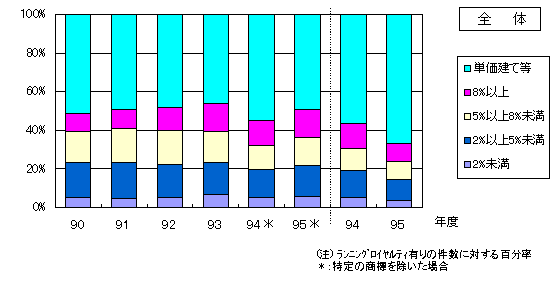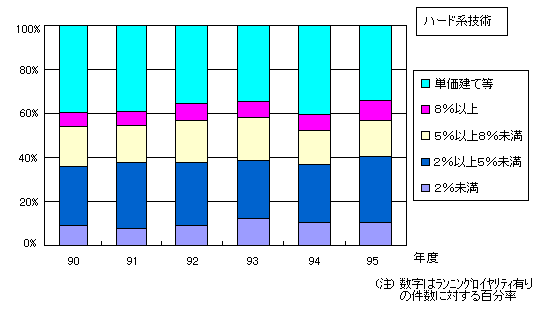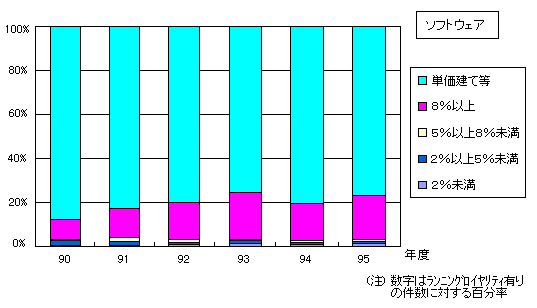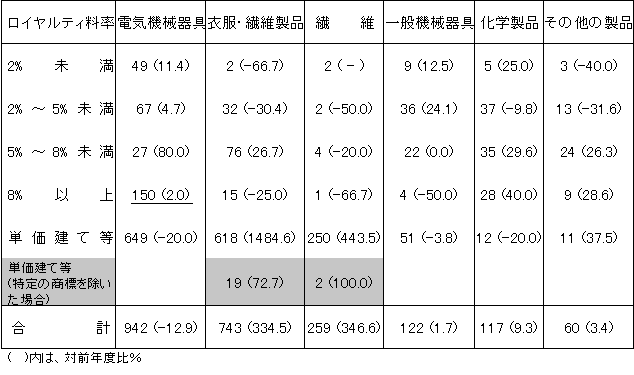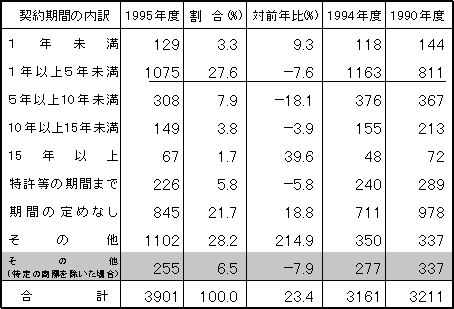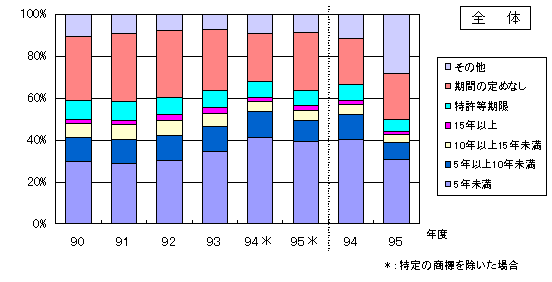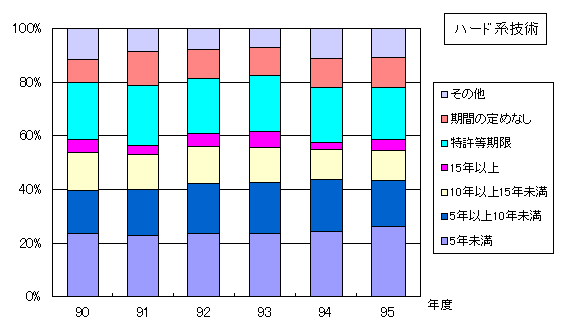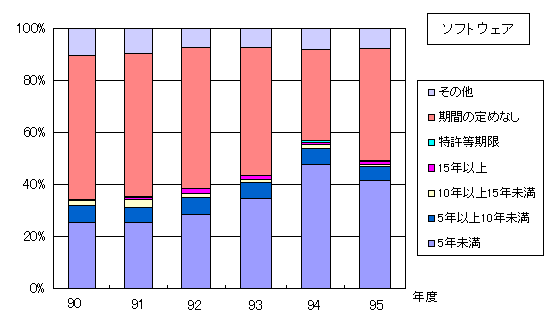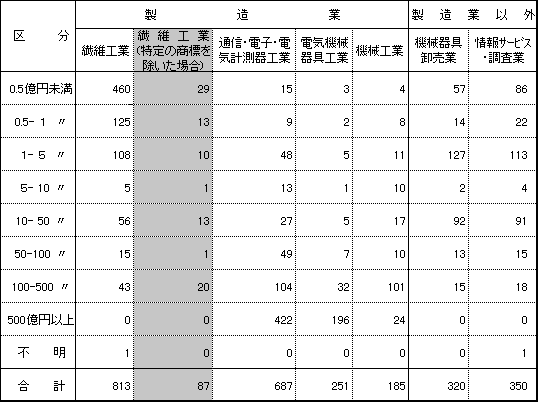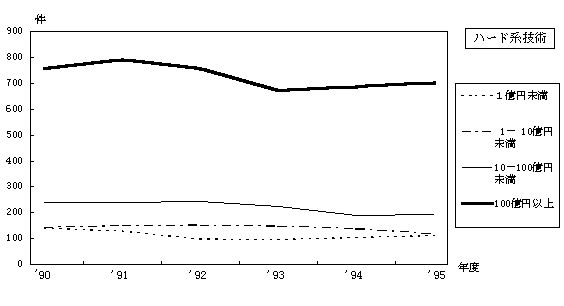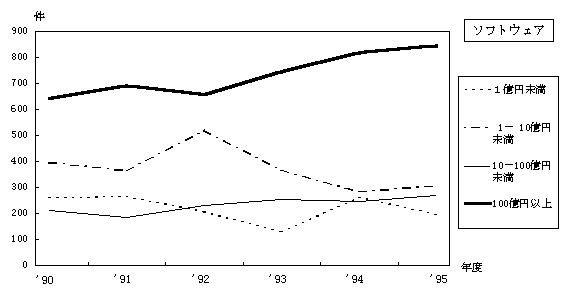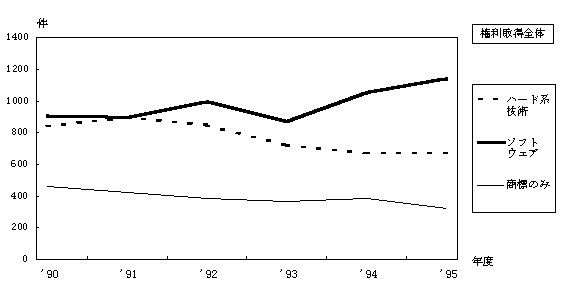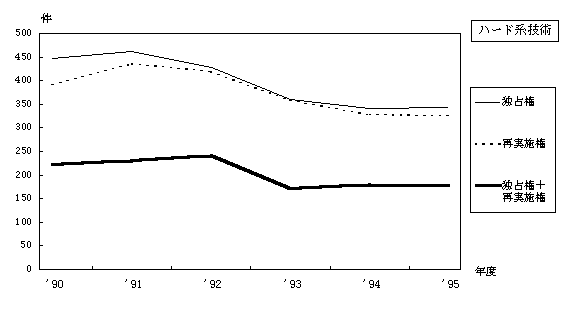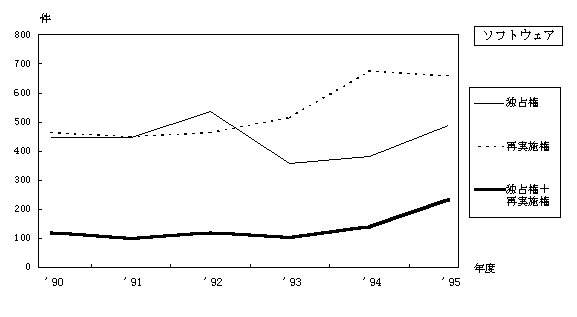| No.111 JAN 1998
|
科学技術庁科学技術政策研究所
NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY POLICY
|
平成10年を迎えて
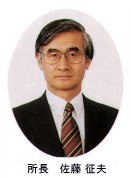 新年明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
7月に創立10周年を迎える今年は、科学技術政策研究所にとって大きな節目の年と考えております。
科学技術基本法の成立、科学技術基本計画の閣議決定、昨年の行政改革会議の論議を経ての総合科学技術会議及び教育科学技術省の設置決定等、ここ数年の科学技術政策の枠組みに関する大きな動きは、経済社会システム全体の大変革の一環であり、とりわけ、情報通信技術、ライフサイエンスに代表される科学技術の新たな展開により科学技術と社会との結びつきが質的に変わりつつあることの反映と考えます。このように、当研究所創立時とは、社会経済情勢や科学技術政策の枠組みが大きく異なっておりますが、戦略性を持った総合的な科学技術の推進の必要性が指摘されており、当研究所に対する期待も益々大きなものとなっております。
このような認識の下、夏から秋にかけて予定しております10年誌の発行や国際シンポジウムの開催においても、単にこれまでの10年間を総括するだけでなく、今後10年あるいはそれ以上先を展望するものにしたいと考えております。また、今年は、昨年8月に内閣総理大臣決定された研究評価に関する大綱的指針に沿って、外部有識者による研究所の評価を受ける予定でありますが、研究評価そのものが当研究所の取り組んできた研究課題の一つであることを踏まえ、新たな発展の契機ととらえております。さらに、従来から進めております国内外の政策研究機関との連携関係を強化拡大し、多様な政策課題に関する調査研究が政策提言として結実するよう努めていきたいと考えております。
今年も、様々な調査研究分野での研究成果を報告書としてまとめるとともに、国際ワークショップ、所内セミナー、講演会の開催を積極的に行うこととしております。政策研ニュースでこれらについて御紹介して参りますが、政策研ニュースを内容のより充実したタイムリーなものにさせていきたいと思っております。
今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
Ⅰ.レポート紹介/Highlight of the New Report
外国技術導入の動向分析(平成7年度)
(NISTEP REPORT 54)
情報分析課 山口 治
1.調査目的
本調査は、「外国為替及び外国貿易管理法」による技術導入契約の締結(変更)に関する報告書等に基づき、我が国における平成7年度の外国からの技術導入の実績をとりまとめるとともに、最近の技術導入の動向の分析を行っている。(なお、本調査の対象技術については、「ソフトウエア」及び「商標」が含まれている。)
2.調査対象
-
- 対象総数 3,901件
-
- 対象期間 平成7年4月1日〜平成8年3月31日
3.調査結果の概要
本報告書における、ここ数年の特徴的事項をいくつか挙げると、
| ○ | 米国からの技術導入が多く、ソフトウェア、ハード系技術がともに6〜7割を占める。
|
| ○ | ソフトウェアに関して、100億円以上の資本金規模の企業の導入が、増加傾向。
|
| ○ | 権利取得を伴う技術導入がソフトウェアでは増加傾向に対し、ハード系技術では減少傾向。
|
| ○ | 契約期間の「1年以上5年未満」の技術導入割合が増加傾向。
|
である。以下に個別の状況を示す。
(1)新規技術導入件数
新規技術導入件数は、3,901件であり、前年度に比べ23%(740件)の増加である。ただし、1994年度及び1995年度は、英国から導入されている繊維関係の特定の商標について既存契約が解除され、新たに新規技術導入されており、これを除くと、3,054件であり、前年度(3,088件)に比べ実質ほぼ横這いである。
<技術導入件数契約の推移>
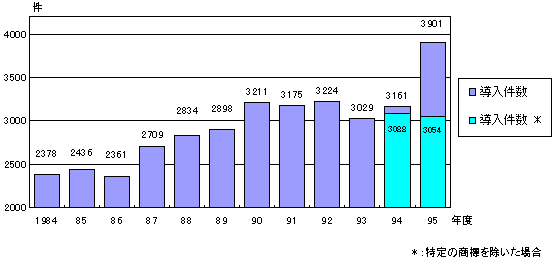
(2)国別導入件数
国別導入件数は、米国からの導入が、1981件で前年度と比べやや3.8%と減少(2,056件)しているものの全体の半数を占めている。第2位は、英国であり、1099件と前年度に比べ3.9倍(283件)であり、全体の約3割弱を占めている。ただし、本年は、(1)に示す事情があり、これを除くと、252件であり、前年度に比べ実質1.2倍(210件)である。
<主要国別導入件数の推移>
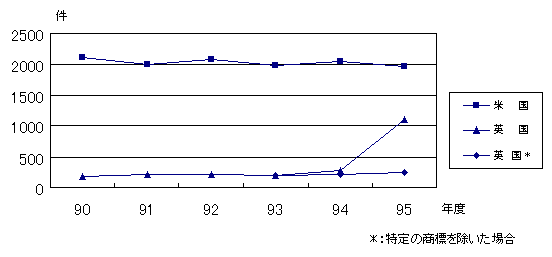
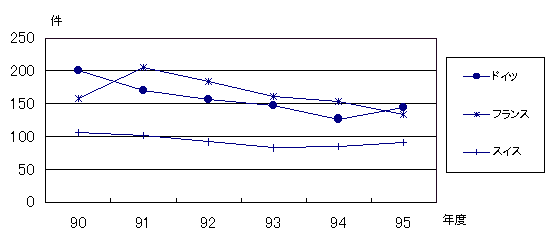
(3)技術形態別導入件数
技術形態別(ハード系技術、ソフトウエア、商標のみ)では、「ソフトウエア」が1,634件となり、全体の約4割を占めており、最近3年間でやや増加傾向である。一方、「ハード系技術」は、1,124件で全体の約3割弱を占めており、最近3年間でほぼ横這いである。
<技術形態別導入割合>
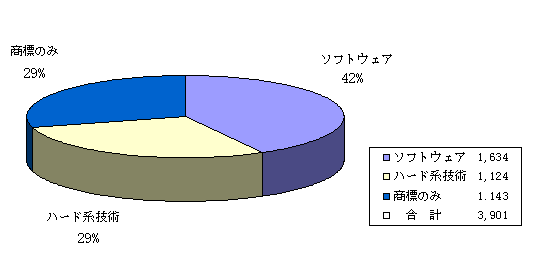
<導入件数の推移>
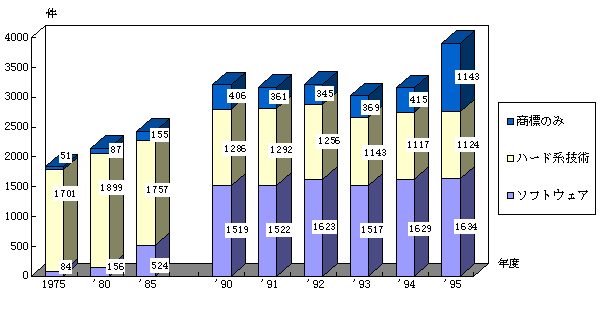
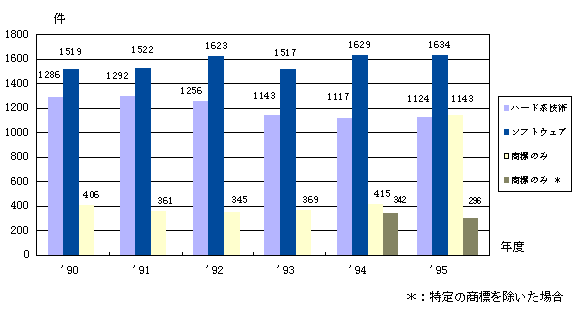
(4)技術分類別導入件数
技術分類別では、「電子計算機」が全体の4割を占めており、「電子計算機」主導の技術導入が続いている。特に、米国からの導入が7割を占めており、毎年高率で安定している。また、電子計算機に関する導入のほとんどがソフトウエアに関するものである。
<上位7技術分類別技術導入数の推移>
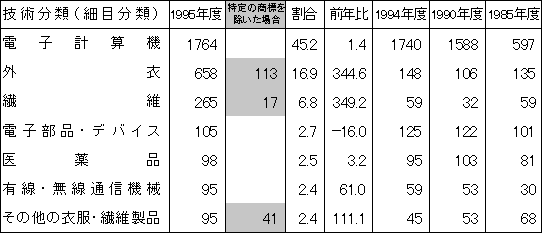
<主要技術分類別導入件数>
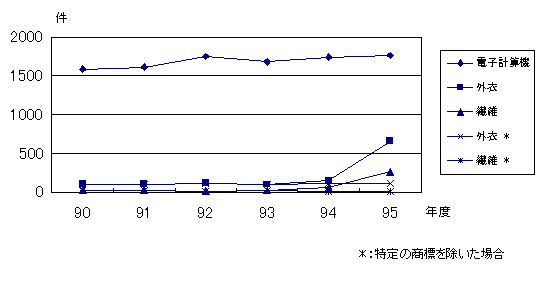
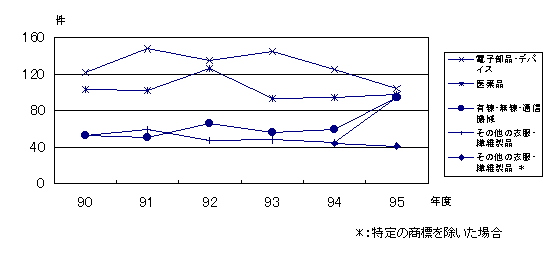
(5)対価の支払条件
対価の支払条件を技術分類別にみると、電気機械器具において、単価建て等が69%、ランニングロイヤルティ料率8%以上が16%を占めている。これは、電気機械器具の8割弱を占めるソフトウェアで、単価建てや高率のランニングロイヤルティのものが多いためである。
<ランニングロイヤルティの料率>
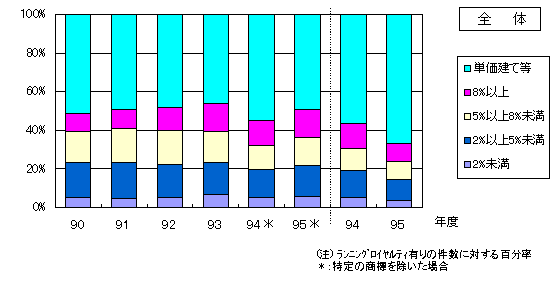
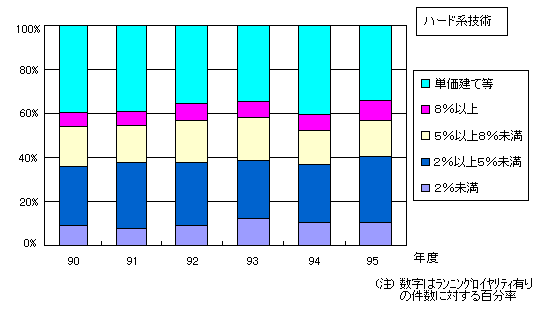
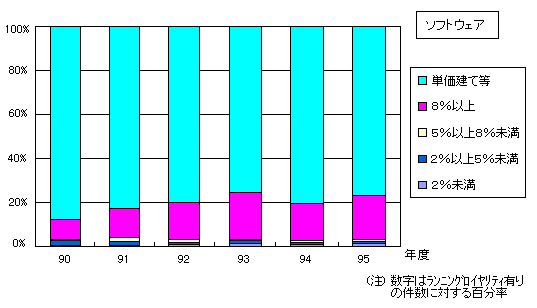
<技術分類別ランニングロイヤリティー>
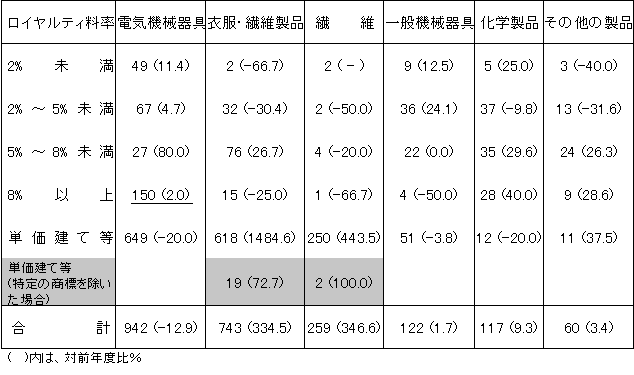
(6)契約期間
契約期間では、「1年以上5年未満」が最も多く、全体の28%を占めており、5年前に比べ1.3倍となっている。
また、ここ数年間の変化では、「1年以上5年未満」が増加傾向にあったが、1995年度は横ばいとなっている。
<契約期間の状況>
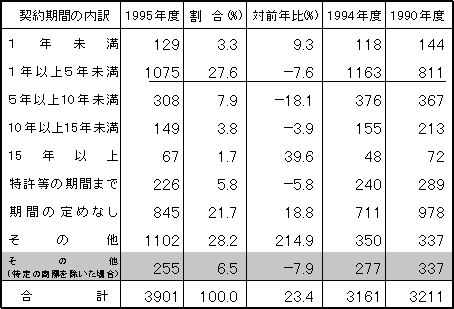
<契約期間の推移>
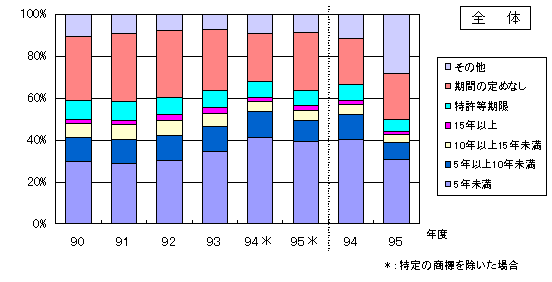
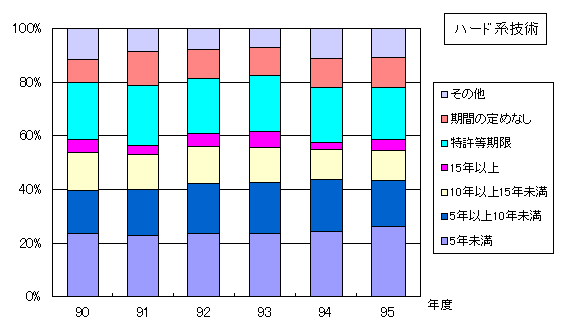
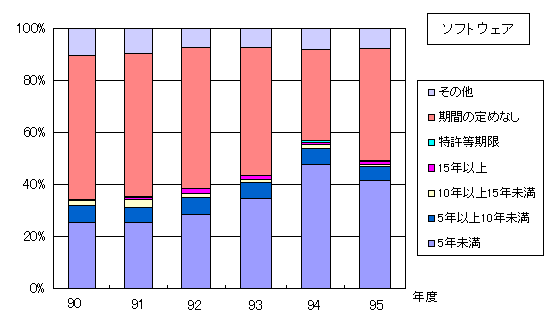
(7)資本規模の業種別導入件数
本年は、(1)に示す事情があり、衣服・繊維製品、繊維に関する0.5億円未満の小規模企業の件数が、約半数を占め、前年に比べて急増している。
<主要業種別資本金別導入割合>
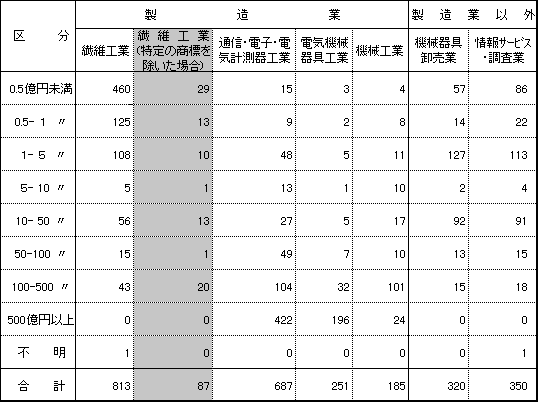
(8)資本金規模別導入件数
技術形態別に導入企業の資本金規模をみると、ハード系技術では、ここ数年横ばいであるのに対し、ソフトウエアでは、資本金100億円以上の企業の導入が、ここ数年増加している。
<資本金別導入件数の推移>
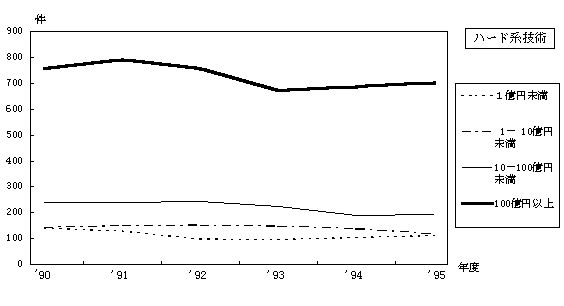
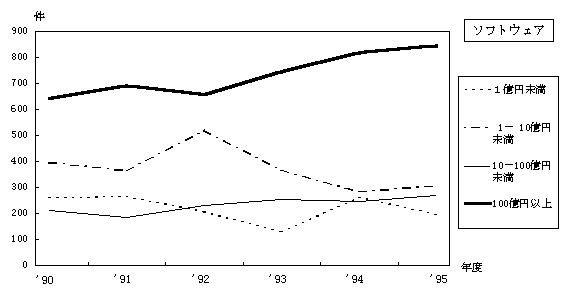
(9)技術形態別権利取得件数
技術形態別権利取得状況については、ソフトウエアに関し、権利(独占権または再実施権)を伴った導入が、ここ数年増加しており、ハード系技術に関しては、ここ数年減少傾向にある。
<権利取得件数の推移>
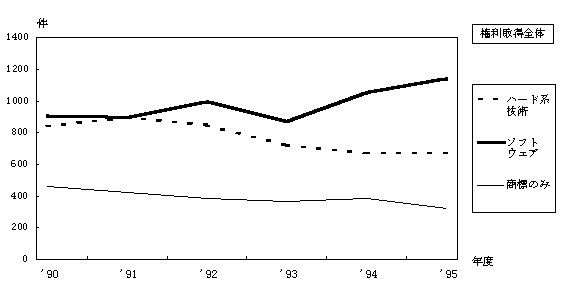
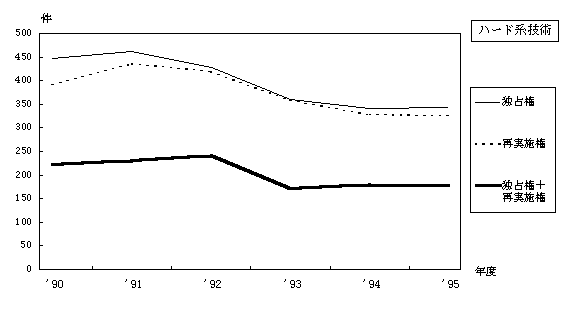
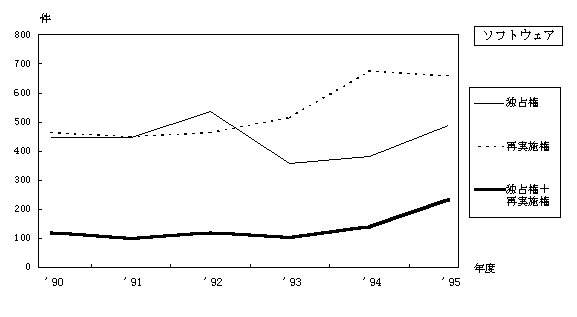
| 参考 :
| 本報告書の入手方法
|
|
本報告書は、大蔵省印刷局より発行。
販売所等の問い合わせ先 :大蔵省印刷局業務部普及管理官室
Tel 03-3587-4283〜4
|
Ⅱ.研究会等紹介/esearch Meeting
第 7 回国際技術経営会議
| 1997年11月3日より7日まで『第 7 回国際技術経営会議(7th International Forum
on Technology Management)』が国立京都国際会館(京都市)において開催された。国際技術経営会議は、主として欧州で開催されてきた技術経営に関する国際会議で、欧州を中心とした企業の技術担当役員、マネージャー、コンサルタント、経営学やR&Dマネジメントの研究者らで構成されている。今回のテーマは「21世紀への挑戦―東西のネットワーク形成(Challenges
for the 21st Century - Networking East and West)」というもので、アジアで初めての開催であり、研究・技術計画学会が主として日本側の世話役となって運営が進められた。科学技術政策研究所からは、平澤泠・第2研究グループ総括主任研究官(東京大学大学院併任)がプログラム委員長を務めたほか、佐藤征夫所長が運営委員として、また、何人かの所員がいくつかのセッションの座長や事務局メンバーとして参加した。 |
|
技術経営には、技術革新の進展につれて従来のシステムでは対応し難い領域が拡大してきている。米国企業を中心に技術経営革新が進む一方で、我が国の企業ではマネジメントシステムへの情報技術の導入の遅れ、マネジメントスタッフやその活力の不足、マネジメントスキルや新しい状況に適合するコンセプトの開発の遅れなどが目立ってきており、このような遅れは最近の日本企業の活力の後退と符合しているとの指摘もある。一方で、1980年代後半に日本企業による市場指向の技術経営が米の企業に参考とされたことを思い起こすと、各国の関係者が相互に学ぶ意義は大きいと言えよう。なお、技術経営の新しいコンセプトは、企業経営ばかりでなく科学技術政策の領域においても重要となっており、参加者のなかにも科学技術政策の研究者が多数見受けられた。
本会議では、海外からの発表や講演約110件を含め、約130件の発表が行われた。全体の参加者は300名ほどで、従来より本会議を構成してきた欧州や米国からの参加者の他に、韓国や南米からも多数の参加があった。
|
| 11月3日にはウェルカム・レセプションが開催され、同4日は会議議長の中原恒雄氏(住友電工技術特別顧問)の歓迎挨拶、および水野幸男(日本電気特別顧問)、崔亨燮(韓国科学技術協会総連合会長)、尾身幸次(経済企画庁長官)(代読)各氏による基調講演があった。引き続いて11月6日まで、五つの会場に分かれて発表が行われた。また、「R&Dマネジメントのための適切な基本概念」というテーマでのラウンドテーブル・ディスカッションや「新しい知識とイノベーションの出現に関する科学技術政策の新たなパラダイム」および「技術経営のツールとテクニック:実践と理論」のテーマでのパネルディスカッションも行われた。 |
| 各セッションのテーマは、「成長のためのイノベーション―東西の展望―」、「技術政策の評価」、「電子商業取り引きのビジネス事例」、「知識のマネジメント」、「R&D資産の最大化」、「サービス産業の技術経営」、「複雑系におけるイノベーションの展望」、「グローバル連携の形成とネットワーク組織」、「イノベーターセッション−研究マネジメント」、「持続性をめざして」、「技術経営の教育−国際的トレンド」、「複雑系のイノベーション・マネジメント」、「技術予測と新市場への機会」と多岐に渡ったものであった。 |
| また、『アカデミック・ペーパー・セッション』として「中小企業におけるマネジメント」、「ネットワーク化と学習」、「R&Dのパフォーマンスの測定」、「コンピタンスの構築」、「技術移転」、「イノベーション・プロセス」などのテーマのもとで多数の発表が行われた。さらに、『ファクト&ケース』のセッションとして「ヒューマン・ファクターとヒューマン・プロセス」、「地域と中小企業」、「複雑系」、「マネジメントの概念とツール」、「教育/国際協力」などがあった。他に、11月3日、6日、7日には関西地区の、また10日には関東地区の研究開発現場を訪問するツアーがあり、海外からの参加者を中心とする見学とディスカッションが行われた。 |
|
会議は、初めてのアジアでの開催にもかかわらず関係者の尽力により成功を収めたが、一方で、日本の参加者から、我が国における技術経営の研究者の層の薄さ、専門教育の不足などを指摘する声も聞かれた。
|
Ⅲ.海外事情/Oversea's Infomation
○ 海外出張報告
(1)韓国工学アカデミー主催シンポジウムでの講演
所長 佐藤征夫
去る10月21日、韓国工学アカデミー主催のシンポジウム「Perspectives
in Engineering & Technology Policy」に招待講演者として出席する機会を得た。
本シンポジウムは、科学技術が国民経済発展の原動力という認識の下に、将来に向けて韓国の科学技術体制をどう改革し効率的なものとするか、また、技術の普及及び技術革新のためにテクノパークが重要であり、韓国で計画中のテクノパークをどう進展させるかをテーマとして開かれた。
オープニングセッションでは、仏の工学アカデミー会長で、(世界)工学アカデミー会議副会長でもあるLavalou氏が基調講演を行った。
セッション1「政府の科学技術体制の進展」に於いて、最初に筆者から日本の6大改革を促している世界情勢の変化の特徴を"borderless"とし、その主要なファクターと科学技術との関連に言及しながら、最近の日本における科学技術体制、政策の変化を説明するとともに、簡単に戦後から現在までの体制・政策の変遷について紹介した。次に、廬(Rho)ソウル大学行政大学院長から、韓国は現在、量から質への大きな社会経済転換を経験しつつあり、この社会変化の評価が政府の科学技術開発マネジメントシステムの改革に反映されるべきであるとして、同システムの特徴と問題点の指摘、改革のための4つの代替案の紹介等があった。
セッション2「技術普及とテクノパークの役割」では、英国Surrey大学学長Dowling教授の講演の後、白(Paik)韓国通商産業エネルギー省技術政策局長から、韓国政府は、1995年の「産業及びエネルギーのためのインフラストラクチャー整備に関する法律」に基づき、技術革新環境の改善のため種々の政策展開を行っているが、その中でも重要なテクノパークについて、13の計画があり、100以上の大学、2000以上の企業がこの計画に参加しており、2兆3000億ウォンが投資されるであろうなどの説明があった。
本シンポジウムは、12月18日の大統領選挙、日本の行政改革の動き等を意識しつつ、21世紀の韓国科学技術体制のあり方を考えるという意欲的なものであったが、その後の急激な経済悪化は科学技術振興にも大きな影響を与えるものと思われる。何れにせよ、2月25日発足の韓国新政権による科学技術体制がどのようなものになるか注目していきたい。
(2)International Foresight Conferenceへの出席
第4調査研究グループ 古閑知明
去る11月18日,英国OST主催のInternational Foresight Conferenceに出席した。
英国は1994年から1995年にかけて技術調査を実施し,1999年から次の技術予測調査に着手する予定である。このため,Foresight Steering Committee及びOSTを中心に,前回の予測調査の評価を行うとともに,海外の技術予測の調査を行っており,今回の国際会議はその一環として開催され,日本をはじめ,アメリカ,韓国,シンガポール及びドイツの現状が報告された。参加者は約150名におよび,英国の各国駐在のアタッシェ,British Council関係者等が中心であったが,在ロンドンの外交官等も多数参加しており,国際色豊かな会議であった。会議の最後にChairmanのBen Martin(PREST, Sussex University)が全体を総括して,
| ① | 近年多くの国でForesightが実施されている背景には,国家予算が制約される中で国際的な競争力を高めなければならないという状況がある。
|
| ② | Foresightはそのプロセス自体に大きな意味がある。
|
| ③ | 他国の経験をいかに自国の状況に適応させるかが重要である。
|
| ④ | Foresightは省庁の枠を超えた将来像を提供するものである。
|
| ⑤ | National Innovation Systemにおいては,あるKey Playerが単独でInnovationをもたらすことはまれであり,いかにリンク・ネットワークを形成するかが重要となってきている。この意味でもTechnology Foresightが果たす役割は非常に大きい。
|
と締めくくった。
5年おきに実施している日本の技術予測調査も今回で6回目(昨年7月 科学技術政策研究所より発表)である。最近ヨーロッパをはじめアジア各国で技術予測調査が実施されるようになったが,そのほとんどが日本の調査形式を踏襲してことからも分かるように、これまでも国際協力に努めてきた。今後も、科学技術政策の立案や技術開発計画策定に当たっての有効なツールとして、「技術予測調査」が活用されることが予想される。日本の果たすべき役割もさらに増大するであろう。
Ⅳ.コラム/Column
外国為替・外国貿易管理法及び関係法令等の改正について
情報分析課 田村泰一
日本における国際金融取引を取り巻く環境の変化に対応し、金融市場等の活性化を促進するため、「外国為替及び外国貿易管理法」と関係する法令等が改正された。今回の改正では、
| ○ | 資本取引等について許可又は届出にかかる制度を原則として廃止すること
|
| ○ | 外国為替公認銀行制度等による外国為替業務に係る規制を廃止すること
|
が大きな変更点である。
「外国為替及び外国貿易管理法」では、外貨を伴う取引に関し、各種の報告等を義務づけていたが、今回の改正に際して、報告に関する規定について整備するとともに、技術導入契約の締結に伴う報告及び届出について簡略化するため「対内直接投資等に関する政令」も改正された。この改正により、
| 1) | 指定技術(航空機、武器、火薬類、原子力、宇宙開発)に係るもの
|
| 2) | 技術導入契約の対価が確定していないもの
|
| 3) | 技術導入契約の対価の額が確定している技術導入契約であって、対価の額が主務省令で定める額(三千万円)を越えるもの
|
のいずれの条件にも該当しない技術導入契約については、報告及び届出が不要となる。
なお、本法律及び政令については、平成10年4月1日から施行される予定である。
これまで、科学技術政策研究所では、「外国為替・外国貿易管理法」に基づく技術導入契約の報告及び届出に基づき、NISTEP REPORT「外国技術導入の動向分析」を発行してきたが、平成10年度調査より調査対象が変更されることになる。
<「外国為替及び外国貿易法」の構成>
- 第一章
- 総則
- 第二章
- 支払等
- 第三章
- 資本取引等
- 第四章
- 対内直接投資等・・含む(技術導入契約等の締結等の届出及び変更勧告等)
- 第五章
- 外国貿易
二 報告等・・・・・・含む(技術導入契約等の締結等の報告)
三 外国為替等審議会
- 第六章
- 行政手続き法との関係
二 不服申し立て
- 第七章
- 雑則
- 第八章
- 罰則
|
| 注) | アンダーラインは、今回構成が変更された部分。なお、旧第二章「外国為替公認銀行及び両替商」は、削除され、法律名も「外国為替及び外国貿易法」と改称された。 |
Ⅴ.主なプログラム/Research Program
平成9年度地域科学技術政策研究会の開催について
第3調査研究グループ
科学技術政策研究所は現在、第3調査研究グループを中心にして、都道府県等の地域における科学技術振興政策に関する調査研究を実施しています。
近年、地域科学技術政策を巡る動向の変化は大きく、例えば、都道府県では、ここ1、2年、科学技術振興のための基本指針を策定するところが急増しており、平成9年末現在で、47団体のうち20団体において策定され、指針に基づいた総合的施策展開が進められています。また、国においても平成7年11月に制定された「科学技術基本法」では第4条で地方公共団体の責務を規定しており、平成8年7月に決定された「科学技術基本計画」では第2章第7節で地域における科学技術の振興の重要性を強調しています。
こうした動きの中、当研究所の今後の地域科学技術政策関連の調査研究をより適切なものにすることなどを目的として、下記内容の研究会を、来る2月24、25日(火、水)に開催することしました。この会議には、都道府県及び政令指定都市において科学技術振興施策の総合的推進を担当している方々にお集まり頂き、地域科学技術政策の抱える問題点について共に議論する予定です。
本研究会での討議すべき課題についての意見、また傍聴希望等がありましたら第3調査研究グループまでご連絡下さい。
平成9年度地域科学技術政策研究会
1.日時
平成10年 2月24日(火) 10:00〜17:30
2月25日(水) 10:00〜16:40
2.場所
砂防会館別館2階「穂高」
〒102−0093 東京都千代田区平河町2−7−5
【最寄駅:地下鉄永田町駅】
3.参加予定者
都道府県及び政令指定都市の科学技術振興政策担当者
講演者、関係省庁説明者
科学技術庁科学技術振興局、科学技術政策研究所等
4.プログラム ※プログラム内容については変更の可能性があります。
テーマ 「地域特性を活かした施策展開をどう進めるか」
1日目 考え方・理論からのアプローチ
(1)所長挨拶
(2)講演Ⅰ
・法政大学総長(日本ベンチャー学会会長) 清成忠男
「地域活性化と新産業創造」
(3)科学技術政策研究所からの報告及び討議Ⅰ
・「研究・技術開発資源の空間的集積に関する研究」 柿崎
・「国内外における地域科学技術政策及び政策研究の近況」
権田客員総括研究官
(4)参加者による討議Ⅰ
・地方公共団体からの報告(3団体)
①「基本計画策定の意義と課題」(埼玉県)
②「科学技術政策と白書」(神奈川県)
③「公設民営大学設立と地域振興」
・自由討議
(5)関係省庁施策説明Ⅰ
・国土庁 「第5次全国総合開発計画について」
・文部省 「地域共同研究センターについて」
・郵政省 「地域提案型研究開発制度の創設について」
2日目 施策展開からのアプローチ
(6)講演Ⅱ
・琵琶湖博物館企画調整課長 嘉田由紀子
「地域特性を自覚化するプロセスとしての調査研究
−琵琶湖研究の経験から−」
(7)関係省庁施策説明Ⅱ
・科学技術庁 「科学技術庁の地域関連施策について」
・通商産業省 「通商産業省の地域関連施策について」
(8)科学技術政策研究所からの報告及び討議Ⅱ
・「地域科学技術指標策定に関する調査」 渡辺総括
・「地域における科学技術振興に関する調査研究(第3回調査)」
坂田、田中
(9)参加者による討議Ⅱ
・地方公共団体からの報告(2団体)
①「テクノポリス事業の現状と課題」
②「公設試の役割と機能強化諸施策」
・自由討議
(10)閉会挨拶 総務研究官
|
Ⅵ.最近の動き/Current Trends
○ 講演会等/Lectures at NISTEP
- 12/8 「関西学院大学総合政策学部について」
尾藤 隆(関西学院大学教授)
○ 主要来訪者一覧/Foreign Visitors to NISTEP
- 12/4 苑廣増(Yuan,Guangzeng)(中国国家科学技術委員会訪日団長ほか)
- 12/12 Kerstin Cuhls(独国ISI研究員)
○ 海外出張
- 11/14-12/8 藤垣第2研究グループ主任研究官(蘭国、仏国)
編集後記
つくばカピオで「Digital Libraryに関するシンポジウム」が開催され、高速・広域ネットワークを利用した情報の蓄積、通信、提供の方法等の議論がなされました。このようにインターネットのような電子媒体での情報の発信・収集については議論される場合が多いようです。
また、本ニュースのように電子媒体でも発信しておりますが、印刷媒体による情報の提供もメリットが多く、「紙で見たい」というフアンが多く見受けられるので今後もまだまだ継続して刊行する必要があるのであろうと思われます。
政策研ニュース編集委員会では、創立10周年という節目の年に新たな気持ちでという意味を加えて本号から本誌の顔である表紙の題字を変更しました。
できるところから変更していきたいと考えておりますので、記載記事のテーマに関して、題字に関して、レイアウトに関して読者の皆様のご意見ご感想を事務局までお寄せ下さい。(Y)
トップへ
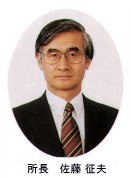 新年明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。