






No.110 DEC 1997科学技術庁科学技術政策研究所
|
| 目次 [Contents] |
 | 研究会等紹介 Research Meeting | ||||||
 | 海外事情 Oversea's Infomation | |||||||
 | コラム Column | |||||||
 | トピックス Topics
|
|  主なプログラム Research Program
|
|  最近の動き Current Topics
| |
第2研究グループ
本ワークショップは、「科学技術の形成過程における評価をどう取り扱うか−研究評価から政策評価まで−」というテーマのもとに、海外の専門家2名をお招きしご講演を頂くと共に、国内外の有識者54名を交えて評価に関する方法や問題点を議論した。
「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」が策定され、その本格的な運用が目前に迫っている。研究現場をかかえる研究実施機関では,研究評価の方法に関して、現在その見直し作業が進められている。
科学技術政策研究所では、京都で開催された第7回国際技術経営フォーラムのEvaluation of Technology Policy Sessionに外国から講演者として出席された2名の専門家、ルエッグ女史、ラレード教授をお招きし、ご講演を頂くと同時に、評価に関するお互いの経験や悩みを交換し合うことを目的としている。
講演要旨
ルエッグ女史(Rosalie T. Ruegg)
〔米国 国立標準・技術研究所 経済性評価室長兼先端技術プログラム経済性評価スタッフ〕
 今日は、簡単に、NIST(国立標準・技術研究所)の役割についてご紹介し、私が実際に関わっていますATP(先端技術プログラム)についてお話したいと思います。
今日は、簡単に、NIST(国立標準・技術研究所)の役割についてご紹介し、私が実際に関わっていますATP(先端技術プログラム)についてお話したいと思います。
NISTの研究開発予算から見ますと、米国連邦政府の研究開発予算( 740億ドル規模)の非常に限られた部分ということになります。軍事用、医療以外の科学技術研究開発予算というのは 200億ドル規模で、そのうちNISTは5億ドル強ということになり、連邦政府から支出される研究開発予算というのは、かなり限られてしまいます。
米国には、幾つかの国立研究所がありますけれども、その中でNISTは、例外的な立場にあり、米国民間企業と協力して研究開発を推進していくという役割を担っています。1901年に設立され、それ以後、民間企業に対応する形で、測定サービス、規格化・標準化サービスを行ってきました。
連邦政府から民間企業に供与される研究開発予算、補助金というのは、ほとんどが国防省、エネルギー省経由で供与され、具体的な研究テーマ、研究プログラムというのは、連邦政府が指定したものを民間企業に委託という形式で行われてきたわけです。
1988年に、米国議会は、NISTに、3つの新たな役割、製造力強化のためのパートナーシップ[Manufacturing Extension Partnership](各地域に、中小企業と協力するためのセンターの設立)、[Quality Program](全国規模で、マルコム・ボルドリッジ賞の選定と授与)、先端技術プログラム[Advanced Technology Program](約半分のコストを民間企業と分担して、民間企業が提案する先端技術プロジェクト、研究プロジェクトに対し資金供与)を与えました。1901年〜1988年までは、NIST Labsの機能(秤量・計器類の規格のサービス−当時は[National Bureau of Standards]国立標準局という名称)を役割としてきたのですが、1988年に、国立標準・技術研究所と改名するに至ったわけです。
ここでATPを実施することによって、米国民間企業が先端的な研究開発を行うのに対して、政府から資金供与するという一番明快な方法が確立されたわけですけれども、実は、1993年までは、このATPというのは大変規模が限られていました。
1993年に、クリントン政権が誕生し、軍事用の研究開発、技術開発に力をおくかわりに、民間部門、民生用の研究開発に力を注ぎたいという意欲を示し、ATPが民間部門に、より力を入れて研究開発を促進していく絶好の手段であると着眼したわけです。ただ、1994年の米国議会選挙によって議会内多数党が逆転し、政府の役割、議会内における科学技術政策に対する見解もだいぶ変わり、民間部門の研究開発よりも、軍事用の研究開発に力を入れ、さらに政府全体の研究開発予算の規模を縮小して行くべきであるという見解に立ったわけです。
ここで評価が関わってくるわけですが、そのプログラムの評価、あるいは技術政策の評価というものが、特にこのATPにおいては、お互いに関わりを持ち、収斂交錯していくということになります。何故ならば、この評価結果というものがプログラムの存続に関わっているからです。数億ドル規模のプログラムというのは、米国政府ではかなり小規模のプログラムであるといわざるを得ませんが、最も徹底して評価が行われているものであると思います。
1993年に、米国議会は業績成果法(Government Performance and Results Act)を通過させ、各政府省庁が自ら、その業績を評価し、今までのインプット評価のみならず、成果物、アウトプットも評価していかなければならないということが義務づけられました。これによって政府の全省庁が自らの業績、出来映え、パフォーマンスを評価していかなければならないことになっているわけですが、均等にどこの省庁もくまなく評価しているかといいますと、いろいろとばらつきがあります。これがまさに、クリントン政権においてATPを推進していく1つのきっかけになったわけで、評価というものを米国政府レベルで話をする場合、特に米国のサイエンス・プログラムの評価の場合には、このATPの評価をお聞きすることが一番良いのではないかと思います。というのは、ATPが一番評価を行っているところであると自負しておりますし、また他のところでは、間違いなくATPほどの評価が行われていないと思いますので、米国での評価の実情を理解するには、ATPが一番良いと思います。
民間部門と軍事部門の研究開発分野における意思決定プロセスというのは、かなり対照的なものとなっています。軍事部門の意思決定では、政府のその特定技術分野における専門化というものをまず明確化し、それをベースとして何が具体的に研究開発として必要なのか、それが研究開発テーマであった場合、どの民間企業と委託契約を結び、政府が顧客になり、委託された民間企業が要求された研究開発を行っていくことを決定するにあたって、いろいろと自由裁量という余裕が残されていますが、そういったモデルは民間部門の場合には直接適用できません。従って、ATPが採用したモデルは、ATPが後押しし、民間企業側がどういった研究開発が必要なのかを政府側に自らの意見を明確にし、それを明言化させた上で、どういった分野で研究していくかを確定していくというモデルを採用しています。従って、意思決定プロセスのモデルは、対民間企業のために採用しているモデルの方が、非常に微妙な複雑なモデルの内容になっています。このモデルでは、必ず民間企業と委託契約を結ぶ場合に、コンペを行わせ、お互いにどういった内容について研究したいかを提案させた上で、審議会[board]を設置し、ピアレビューで審査し、どの企業に補助するかを決定します。
このコンペには2つあり、1つ目のコンペ、[general competition]は、企業側からプログラムのアイデアが提案され、評価されますので、イニシアティブは企業側が握っています。それをATPの選定基準に基づいて評価します。このモデルは、産業界に対して、意思決定プロセスに透明性が付与されているので、政治的に物議をかもし出すということはほとんどないと思います。一方2つ目のコンペは、既にプログラムが決定していて、そのプログラムに対して企業がプロジェクトを提案するというもので、いろいろと物議をかもし出すことが時々あります。従って、この2つのモデルでは細心の注意を払って選定を行っています。
まず、産業界、一般市民の方達、大学などの研究機関の方達から、どのようなプログラム・アイデアがあるかという提案が寄せられ、選定を行っています。米国にとっての経済的利益を提供するもの、技術力があること、産業界として十分に力を入れてコミットメントしていること、何故ATPの関与が必要なのかという4つの基準でふるいにかけ、最良のアイデアを最終的に抽出します。ただ、ATPのスタッフが関与した上でふるいにかけると、物議がかもし出されてしまいますので、ワークショップを産業界と共に開催し、透明性、中立性を訴えるようにしています。また、やりとりの情報はパブリック・レコードという形で開示しています。ワークショップ開催後に、審議会を設置して、州政府からも委員を募り編成し、どういう領域が良いかの選定が行われ、プログラムの優先順位付けが行われます。
このような形で決定されたプログラムに対して、1企業、ジョイント・ベンチャーの両方の形態でプロジェクトの提案があるわけですが、こういった提案はピアレビューにかけられ、評価されます。ここでも先ほどと同じ基準が採用されますが、学術的・科学的な観点、ビジネスおよび経済性の観点から、より厳密に具体的な基準に基づいてピアレビューが行われます。
ATPの資金を得るためには、非常に重要な原則があります。1つは、この選定プロセスの中で企業にリーダーシップを発揮させながら選定していく点、もう1つは、何かを開始させ、それを終結させる期日を最初から明確にし、各プロジェクト、プログラムの提案書の両方に開始、終了期日が記述される点、そして、その対象企業にATPスタッフが実際に訪問し、活動中の資金用途について監視します。また、期待された進捗が得られない場合、何らかの問題が生じた場合に、ATP側、企業側の判断で、中止する権利があります。もう1つは、厳しい競争にさらされた形で選定されるということです。
次に、プロジェクトの全提案書が提出されましたら、その内容についてふるいにかけるのですが、そのときにどのような技術タイプであるのかということをまず識別し、そして提案書の品質レベルを評価します。その上で、ふるいに残った提案書の技術的、ビジネス的なレビューを行います。技術的なレビューはその各専門分野の専門家、ビジネス的なレビューはそのビジネスおよび経済性の専門家によって行われるわけですが、利害衝突の発生しないような中立な立場の人々を選んで行います。このレビューでスコアリングがなされ、高得点の提案書に関してのプレゼンテーションの場が設けられます。ここでは、審議会委員と企業の方も参加し、審議会の方からレビュー中での不明点、疑問点が質問として企業の担当者に寄せられます。そして、最終的な選定がなされ、どの提案書にファンドを割り付けるかを決定します。そして、その選定された提案書の企業、ジョイント・ベンチャーと共同契約を締結し、締結されたならばマネジメント段階に移り、その後は評価、追跡段階に移るわけです。
では、選定されなかった場合は、その企業、企業グループには却下報告を受ける権利があります。各段階でのコメントなどの情報が開示されます。その内容を踏まえて、再び内容を調整した上で、再度後日、コンペに参加する権利を持っています。
ところで技術政策目標というのは、政府の助成金を使うことによって、政府からのてこ入れがない限り、恐らく企業単独では立ち上げに非常に時間がかかってしまう、それがなかなかできないと思われる技術の立ち上げに貢献していこうという観点です。どのような種類の技術かといいますと、スピルオーバー効果(経済的波及効果)があるものです。多くの技術開発プロジェクトというのは、革新者だけでなくより広いところまで利益が及ぶものですので、そのようなプロジェクトに絞って、より大きいイノベーション・プロジェクトに着目していかなければならないと考えています。
その見極めを行うために、まず技術そのものの特徴を十分考えていきます。そもそもスピルオーバー効果といった性質を持った技術であるかどうかを考えると同時に、技術開発が行われるその企業が属している産業構造とはそもそもどうなっているかを考慮に入れ、さらに提案を行っている革新者の企業がどういった意図、計画を持って最終的にその技術普及を果たしていこうと考えているのかの側面も考慮に入れて見極めを行います。ATPプログラムは、非常に課題が大きい、それを解決するのが困難に見え、非常にリスクの高いプロジェクトを対象としているということです。例え経済的波及効果が大きいと考えられても、大変リスクが低い、企業が単独で実施しても大変容易であると思われるものは、ATPプログラムの対象とはなりません。挑戦的であり、リスクが高いことが選定基準となります。
政府の研究施設を充実し、その施設で民間企業が研究できるようにするということは一切しておりませんし、むしろ民間企業に全体的に委ねて、ただATPが後押ししなければ恐らくこんなことはリスクが高過ぎてやらなかったであろうと思われるもので、国益にとって非常にプラスであると考えられるものを、民間企業を刺激することによって研究させる。そして、できるだけ官僚主義的な指導を行わないで、あくまでも資金を民間企業に提供し、後は民間企業に任せる体制を取っていますので、ATPのスタッフは大変人数が少ないわけです(約65名)。
以上、米国政府の政策は現在、技術開発を通じて米国の経済成長、景気促進を果たしていこうという意向があります。ここで、こういった政策の実現手段となるプログラムが確定されているわけですが、ATPプログラムではまず、原則ピアレビューにより、どのプロジェクトをATPプログラムの一環として推進していくかを事前に選択します(事前評価)。その後言ってみれば事後評価が行われます。事前に設定されたプロジェクト独自の目標が達成されたのか、あるいはATP全体としてどういったプロジェクトを対象としていくかという基準もあるわけですから、本当に基準に則ったプログラムであったかどうか、所定の成果が生まれたのかどうか、それを検証、確認、測定していくということも行われるわけです。
ラレード教授(Philipe Laredo)
〔仏国 鉱山大学 イノベーション社会学センター教授〕
 今日は、フランスにおける評価の過去10年間の経験ということでお話したいと思います。
今日は、フランスにおける評価の過去10年間の経験ということでお話したいと思います。
最初に欧州諸国全体にわたって80年代半ばに実際に起こりましたいろいろな評価の制度化についてお話しします。これは、行政府の要望を満足させるばかりでなく、議会の政治家、議員の要望に対応するための解決策でもあります。そして、評価を制度化していくことは、当然、政策立案過程の中で評価をしっかりと位置付けることが必要となります。しかし、政策立案過程そのものが、欧州各国でバラバラの状況である中、全ての欧州諸国で異なった政策立案過程の中に評価プロセスを埋め込んでいく方法として、3つのモデルにまとめることができます(イギリスモデル、フランスモデル、EUモデル)。
この3つのモデルを、誰が意思決定権を持っているか、どこに責任権限が委ねられているか、組織はどうなっているか、具体的なマネジメント体制はどうなっているか、アプローチはどうか、またそれをまとめていく責任にどういった組織があるか、どうやってその効果を普及させていくかということで見てみると、モデルによって全て違っています。つまり、唯一無二の最良の方法というのはないわけですが、大事なことは、1つのモデルが他のモデルでやっていることを参考として、自分がやる方法をさらに詳細化し、それに磨きをかけていくということが必要と思われます。
ルエッグさんのお話の中で実際に評価していく中でも、第3者によるギャランティー(保証)が非常に重要であるという旨のご指摘があったと思いますが、まさにその考えがフランスのモデルに反映されています。フランスのやり方は、その評価の中核に[guarantor model]と呼ばれる第3者による保証を持ってきています。それから、評価の対象として、オペレーターと呼ばれる存在があります。このオペレーターとは、一方には研究を行っていく研究者、科学者の集団があり、もう一方に政策を立案し実施していく政府があるわけですが、その中間に、民間研究機関、国立研究機関、政府省庁、あるいはいろいろなプログラムといった、様々な政策に対して一部責任のある存在があるわけです。
科学技術関係予算の出資形態には2種類の方法があり、1つ目は、繰り返し資金が供与され半永久的に供与していくもので、大学などの高等教育研究機関、国立研究機関に対して、教育科学技術を管轄する政府省庁を経て提供されるものです。もう一方は、テーマに対して基本的には1回限りの目的指向で供与するもので、基本的に教育科学技術の省庁以外から、特定の国家プロジェクト、手続きに対して資金を供与していくという手段です。これは、単独で教育科学技術以外の省庁が管轄する場合、複数が共同で管轄する場合もあります。
オペレーターの存在を厳密に説明しますと、まず国立機関で要員を採用している組織体として、国公立大学には研究室がありますし、国公立の研究機関がありますが、ある一定のミッションを担って、その分野におけるいろいろな研究を行っているわけです。その両者の間に、非常におもしろい存在として、CNRS(国立科学研究センター)、INSERM(国立保健医学研究所)という2つの組織があります。CNRSは、従来の基礎研究を機能として行い、INSERMの方は医療分野の研究を行うという位置づけにありますが、CNRSの要員の75%が実は別の研究機関で実際の活動を展開していて、INSERMの方では90%以上が国立大学病院の方に勤めていて、そこで研究を行っています。しかし、実際に予算配分され、資金供与されるのはCNRS、INSERMであるという実情があります。
科学技術分野である特定のプロジェクト、テーマに対して政府から資金供与する場合には、3つの主要活動主体があります。国家のプログラムで国民全体に影響を及ぼすような分野、医療分野、環境分野などのプログラムに対して、直接資金供与されるという場合、それから国家技術プログラムに対して供与される場合、もう1つが企業のイノベーションに対して援助するという位置づけで供与される場合があります。
ここで、欧州各国政府の科学技術政策に対する対応を理解するためには、ただ単にその国内政府の対応を見るだけでは不十分であり、EUレベルでの科学技術政策の方向性を踏まえた上で、どのように各国特有の政策に反映させているかとういうことを見ていかなければならないということです。
ここで、フランスの国家レベルでの科学技術政策の推進は、それに関わっていくオペレーターとして現在、全ての大学合わせて約120校があり、またそれ以外に、研究機関、政府省庁などが約60あり、これらが全国レベルでの科学技術政策推進の担い手となるわけです。
過去、政府が1980年代始めに、研究機関のそれまでの出来映えを見ていこうという計画を持ち、最初に取り入れたやり方が、監査、日本の会計検査のような手法でした。この監査は、大臣から直接指令が下り、その分野の非常に著明な人物、影響力を持った人、1人に依頼がいって、3ヶ月以内に報告を提出こととなっていました。ただ、これは完全に失敗に終わってしまいました。
1つの理由としては、当然1人でこなすには作業量があまりにも多過ぎることです。また、その報告に対して被監査部門の政府部局から異議申し立てが盛んに行われるようになりました。その異議も、しっかりとした根拠のあるものがかなりあったわけです。評価を行うにあたっての1つの要件として、評価結果はしっかりとした非常に堅固なもの[robustness]でなければならないということが明確になってくると思います。評価対象者からの抵抗、異議をもはねのける、しっかりとした根拠のある評価結果でなければならないということです。
もう1つの理由は、大臣がその要請を行うということで、政策責任者の考え方を代弁するという捉え方をされてしまったわけです。評価結果を用いる人々にとって、評価は信憑性[credibility]のあるものでなければならないということが2つ目の要件です。
これによってフランスに残された評価方法は、フランス国内のオペレーターに対して、体系的で定期的な評価を行う独立した機関を設ける必要があるという方法です。この機関として、大学を評価するのためのCNE(大学評価国家委員会)と、残りの研究機関、国家プログラム、手続きを評価するためのCNER(研究評価国家委員会)が設置されました。
両方の評価委員会とも共通の特徴を有しています。政府省庁から独立した機関であることと、大統領に単に報告するという関係が存在しているということ、そして委員の選定にあたっては、非常に厳しい基準のもとに任命されるということです。委員には、必ず大学の研究者、学会の代表、議会の代表、産業界の代表で構成され、任期は6年で、在任期間中の除名はありません。法律で規定されているのは、「この2つの委員会でもって、体系的で定期的な評価が全てのオペレーターを対象として行われる。この委員会はそのことに関する全ての責務を有する。」ということとなっていて、自らのプログラムの確立、いろいろな評価のための技法や方法論について工夫を凝らすということ、それを流布するための政策の採用といったことにも責任を持っています。
既に10年にわたって活動が行われています。大学を対象としたCNEは、CNERよりも歴史的に早く、1984年に設立され、最初の10年間をかけて、全ての大学117校の訪問および評価が行われました。委員会としては、ちょっと時間がかかり過ぎると評価しましてプロセスの見直し作業が行われ、今では1年間に約20大学の評価が行われるようになってきています。もう1つのCNERは、1990年に設立され、1996年末までに13オペレーターに関しての評価を終了しております。
それでは評価プロセスに関して、この2つの委員会がいかに行っているかをご紹介したいと思います。実は、この2つの委員会はとても類似した評価プロセスを有していますが、しかし、そもそも違ったところからスタートしました。
評価プロセスは4段階で行うわけですが、第1段階が最も重要であるといっても良いかもしれません。つまり、評価対象を当初の段階での目標と照らし合わせるのではなく、今現在の疑問、課題と照らし合わせて評価することです。今現在利害関係となっているのは何かを識別し、評価対象者であるオペレーターと共に利害関係の識別をするだけでなく、利害関係の当事者も含め、単に政府の利害関係者だけでなく、全部の利害関係者に照らし合わせて同定していきます。その上で、どのような課題があるかということについて、評価の参考となるものを書き記します。この利害関係に関する同定作業は情報収集を多く必要とするので、情報収集が重要で、時間がかかるということが分かっています。この同定作業の中で、政治家が当初投げかけた主要な疑問点に関しての答えが自ずと導き出されることも良くあります。
第1段階での同定作業が完了したならば、専門知識段階へと移ります。この第2段階では、2つの委員会のやり方が違っています。CNEでの専門知識を有する専門家というのは、通常その他の大学での同様な立場、大学教授で、1大学当たり10名〜20名が平均値です。大学教授の総数は、そんなに多くないので、結果としてみんなが評価対象者、評価者の両方の役割を果たすこととなります。個別に出た報告書の内容は全て守秘義務を伴い、完全に機密事項となります。一方CNERでは、フランス国外の専門家を幅広く集めて評価が行われることが時々あります。ここでの評価報告書は、CNERが当初収集した情報に添付されます。以上の段階を経て両委員会は、評価報告書の取りまとめ作業になります。CNEでは委員自身が取りまとめ、一方CNERでは評価を行った専門家が共同して取りまとめます。
評価報告書が書かれますと第3の段階「矛盾ならびに対立の段階」に移ります。つまり、この評価報告書の内容を揉んで、その堅固性を実証する段階となります。CNEではこの評価報告書を評価対象大学へ送付し、CNE委員が大学を訪問し、その場で会議を行います。大学側からは、理事会の委員、大学の代表者などが出席し、この評価報告書の内容について討議が行われます。一方CNERは、この段階でどこを対象とするかといいますと、1つは評価対象の研究機関、オペレーターの経営陣、2つ目は研究活動を対象とした場合は労働組合、3つ目はその研究機関を管轄する政府省庁の責任者となります。この対立段階でいろいろとやりとりがなされて、評価対象機関からのいろいろなコメントが吸い上げられ、それらを考慮した上で第4段階に移ります。
両委員会は以上の3つの段階の結果を考慮した上で勧告書を取りまとめます。CNEでは、専門家が取りまとめた評価報告書、委員会がまとめた勧告書、評価対象の大学側のコメント類を全て文書化し、体系立てて編集します。この編集された文書をフランス中の約5,000名の当該関係者に配布します。一方CNERでは、委員会が最終的にまとめた勧告書は公開文書として出版していますが、その他の情報は、問い合わせがあれば開示しています。
ということで、結果はどうなったのか、効果はどうだったのかということですが、まず第1の効果として、最も重要なものですが、評価結果が極めて堅固性を伴うということが実現されました。第2の効果は、非常に学習効果が直接的にあがり、オペレーター・レベルでの学習効果が非常に強く、刺激効果があがったということであり、ときには新しいマネジメント・ツールが採用されたということも含まれています。評価の情報収集段階で随分いろいろなツールが開発され、最初情報収集で使った後で、継続的な評価に強力な力を発揮し使い続けていくことができるツールです。それからまだ評価対象となっていないオペレーター、研究機関でも、非常に大きな間接的な効果があがっております。1つの理由は、まだ評価対象となっていないオペレーターも、今後起こる評価等の準備のために組織自体を見直し、組織だった形で準備を行い、組織内に内部評価プロセスを設定するという間接効果もありました。
ここで、この評価結果を実際に政府内の政治家や議員が、どのように活用していくかということについてですが、1つ明確にしておきますと、政策立案部分でこれが活用されている度合いは、自ずと制限されております。依然として、報告書があまりにも技術的過ぎるという認識が存在しています。また、政策立案レベルで展開される討論だけでは、やはり十分満足のいく結果が得られないという認識もあります。そこでこの2年間、実際に国が政策を策定していく上で本当にこの評価結果を役立てていくために、まだ欠落している部分をいかに補ったらば良いかという議論が展開されてきました。その結果、1つは、OTA(技術評価局)を利用していくということで、OTAを橋渡し機関とし、被評価対象機関、利害関係者がどのような見解を持っているかという意見調整を行っていくという方法と、2つ目は、他の政府機関を頼らずに、この2つの評価委員会が自らの討論を喚起する責任を持つべきであるというアプローチが導入されています。つまり、どこが欠落しているかといいますと、評価と戦略的マネジメントとの間のつながりがはっきりと確立されていないということです。評価から円滑に政策へと戦略的に使っていくというつながりの問題は、フランスに限らず現在の欧州諸国全体の共通問題と言えます。
この10年間の評価経験から、少なくともオペレーター・レベルで、この評価制度が非常に効率的な手段であるということが少なくとも実証されたと思います。しかし、国家全体の科学技術政策実施の一翼を担う個々のオペレーターにとって有益であると考えられていたことが、当初考えられていたほど十分に活かされていません。日本において評価システムの話をよく伺いますが、システムとして体系化されたアプローチを取っていくということは、少なくともこの10年間EU、および加盟諸国レベルにおいて展開されてきた活動を見てみると、政策立案を体系化して行っていくということは、非常に難しいといわざるを得ません。
この体系化されたループの中で、今日お話しできなかった非常に重要な問題が2つあります。研究者自身をどのように効果的に評価していったらば良いかという問題で、これはピアレビューであるとか、そのための委員会を設置するであるとか、いろいろな方法が提唱されていますが、実は具体的にどう評価していったらば良いかは、まだ明確になっていないと思います。もう1つは、実際に研究が行われる場、これを我々は「ラボ」と呼んでいますが、この「ラボ」の評価の問題です。
こういったような現在フランスでまだ続行中で、あくまでも試験段階の評価の問題もあります。
| なお詳細は、研究評価論シリーズ・講演録−53:NISTEP研究評価ワークショップ「科学技術の形成過程における評価をどう取り扱うか−研究評価から政策評価まで−」に掲載してあります。 |
○ 海外出張報告
企画課 根本光宏
行政改革会議の報告で、国立試験研究機関のエージェンシーへの移行が盛り込まれた。日本と英国とでは、行政制度、研究開発体制、社会慣習等が異なっているうえ、日本版エージェンシーとそのモデルとなった英国のAgencyとでも違いがあるため、研究開発関係について、英国のモデルがそのまま日本に当てはまるものではない。1.研究開発Agencyへの移行に伴う制度の見直し
| ① | 基本的枠組み
Agencyの基本的枠組みは、研究開発関係のAgencyも、基本的に他のカテゴリーのAgencyと変わるわけでない。所管大臣は、Agencyの設立に当たって、その基本方針と割り当てる資源を定め、Agencyと所管の省庁の役割と責任、Agencyの運営の具体的目標等の枠組みを定めなければならない。この枠組みを決めた文書は公開され、Agencyの長は、通常3〜5年の任期で原則として幅広い公募を経て所管大臣により任命される。毎年、業務計画が所管官庁とAgencyとの間で合意され業務目標が設定される。その上で、民間企業と同様な形で、財務状況、業務目標の達成状況等の情報を含んだ年次報告書の作成が義務づけられている。研究機関の場合、その運営コスト以上の歳入の確保、マイルストーンの目標達成、ISO等の認証の取得、ランニング・コストの目標達成、依頼分析等の外部サービスの1件当りの時間削減等が管理目標となっている。 なお、Agencyは組織的には中央省庁の一部であり、職員も公務員(civil servant)である。このため、Agencyの設立にあたって特別な立法措置が行われるわけではない。 |
| ② | 予算・会計
予算は本省庁に計上され、Agreement(契約に類するものであるが、本省庁とAgencyは異なる法的主体ではないので、契約でなくAgreementの形式で双方の権利義務を確認している。)により、Agencyに必要な研究開発費が渡される。本省庁側では、傘下のAgency以外の研究所と契約を結ぶことも可能である。市場原理を利用して最善の研究成果を得るという理論的観点からは、本省庁に計上された研究開発費は全て競争入札にかけられるべきであり、研究開発Agencyも全て自由競争を通じて研究開発費を賄うべきということになる。しかしながら、省庁によっては、競争入札にかける割合の方が低いこともある。 支出の方は公務員である職員の人件費、事務所経費等を含め固定費が発生している。このような固定経費も当初から配賦されるわけではないので、契約に当たってoverheadとして加算される。研究開発分野のAgencyでは他のカテゴリーのAgency(例えば、印刷局)と異なり、サービスの対価を支払う者が政府自体となっていることが大きな特徴である。このような研究開発サービスの価格づけに当たっては、Agencyが、その業務目標を達成すれば、独立採算を達成できるような形で設計が行われる。 会計は独立採算に近い形式がとられる。例えば予算以上に契約で研究費を獲得できたり、知的所有権による収入が増加すれば、その分だけ、Agencyの予算(収入)が増加することになる(厳密な意味でいえば、年度当初に政府予算が配賦されているわけではないので、「予算が増減する」という言い方は正しくない)。Agencyは省庁の一部であるので、もし赤字となれば、その分は省庁が補填することになる。 会計に当たっては、cost itemsのような規制は課されない。むしろ契約ごと、プロジェクトごとの管理を受ける。また、行政機関の一部となっていることから、年度主義のコントロールを受け、原則、年度をまたがった予算の支出は認められないと考えた方がよい。一部のAgencyではTrading Fundという銀行口座のようなものを国庫に持っており、その口座を通じて、年度にまたがるプロジェクトについて弾力的な資金管理が可能となっている。但し、研究開発AgencyでTrading Fundを持っているところは少ない。 なお、英国の大学の場合、教育雇用省からのグラントで人件費等が支払われているので、政府関係の研究開発に関して契約を結ぶ際、大学は人件費等を差し引いて、Agencyより安い値段で請け負うことができる。その不公正を指摘する関係者もいる。 |
| ③ | 組織・人事
中央省庁の定めた政策や予算の範囲内で、Agencyに管理権限の委譲を行い、公務の能率を上げるというのがAgency化の一つの狙いであり、人事、組織についてはAgency側に裁量権が与えられる。Agencyの最高責任者及びそれに次ぐ階級の職員の人事権は中央省庁側にあるが、その下の階級の職員の人事はAgencyによって行われる。職員はcivil servantであるので解雇は簡単ではない。Agencyの組織見直しを行っていく上で、通常、早期退職のための退職金の割増、同じ省庁内での配置転換の措置がとられた。 なお、Agencyであることによって、職員の身分が中央省庁にいるよりも不安定になるものではない。人員削減が起こりうるのは中央省庁でもAgencyでも違いがない。 |
| ④ | 研究開発の企画・立案
研究所を省庁から独立した存在として運営させるため、省庁サイドで、自ら研究計画や予算を策定するスタッフを抱えることになる。人的なコストを抱えることになるが、長期的にはそのほうがコストが割安になるということである。Agency化が進む過程で、省庁側で科学者をパーマネント・スタッフとして抱えたり、研究所の人間が移ったりしている。なお、Agencyあるいは民営化された国立研究所から研究プロジェクトを中央省庁に提案するということも行われている。 |
2.Agency以外の公的研究機関について
英国の自然科学分野の公的研究機関(Public Sector Research Establishments)については、大学は別として、大別して各省庁に付属する国立研究所と、Office of Science and Technologyの下の6つの研究会議傘下にある研究所に分けることができる。国立研究所についてはAgency化の傾向にあるが、研究会議傘下の研究所は、以下の理由により組織の法的な位置づけについてまで見直しが行われているものは少ない。
| a) | Agencyというのは省庁から切り離されて独自の運営ができるという意味を持っている。研究会議傘下の研究所は、もともと独自の法人格を持ち、省庁から切り離された運営主体であったので、組織的な変革を加える必要がなかった。英国のAgencyは政府機関の一部であるので、研究会議傘下の研究所をAgency化することは行政改革の点からはむしろ逆行することとなる。 |
| b) | 民営化というアプローチは可能であるものの、既に土地は国の財産でないので、売却によって収入を上げることが期待できなかった。 |
| c) | 逆に、職員を新会社に移す際に、その職員の年金を国庫から移管しなければならず、その財源を手当てできる目処が立たなかった。(職員はcivil servantではないが、研究会議の職員となっており、その年金が財務省によって管理・運用されている。) |
| 位置づけ | 機関数 |
|
公的機関として存続している 機関(Agencyを除く。研究会議 傘下の研究所を含む。) |
27 |
| Agency化された機関 | 9 |
| 運営委託された機関 | 1 |
| 民営化された機関 | 9 |
【訪問先他】
本報告を作成するに当たって、訪問させていただいた機関及び日本において講演をいただいた機関のリストは以下の通りです。快く訪問をさせていだいた方々、訪問先を紹介いただき、また、講演に当たって御協力いただいた英国大使館に改めてお礼を申し述べる次第です。
・Cabinet Office/Next Steps Team
・Office of Science and Technology
・Department of Trade and Industry(DTI)/National Measurement Directorate
・Ministry of Agriculture,Fisheries and Food(MAFF)/Research Policy Co-ordination Division
・Laboratory of Governmental Chemist(DTIのAgencyを経て民営化)
・Central Science Laboratory(MAFFのAgency)
・Defence Evaluation and Research Agency(国防省のAgency)
・Biotechnology and Biological Sciences Research Council(BBSRC)
・Institute of Arable Crops Research(BBSRC傘下の研究所)
第1研究グループ 後藤 晃
永田晃也
第4調査研究グループ 斉藤 均
| 6%削減 |
|
温暖化防止京都会議は、焦点の温室効果ガスの削減目標について、2008年から2012年にかけて1990年に比べ先進国全体で5.2%(日本6%)の削減と、併せて総排出量から森林の吸収分を差し引くネット方式、先進国間での排出権取引及び共同実施を認めることなどで合意し終了した。
今後、各国はその目標を達成するため具体的な行動段階に移り、我が国も早急にCO2排出削減対策に総力を挙げて取組む必要がある。
|
| 技術予測調査にみるCO2固定化技術 |
|
2025年までの技術を展望した「第6回技術予測調査」においては、環境分野をはじめ、資源・エネルギー分野等各分野で基礎から応用までの環境関連課題が調査されている。
地球温暖化の主原因であるCO2の削減方策としての固定化技術については表1に示すように6分野から11課題が設定されている。「世界のCO2の排出量が20%減まで低下する」のは2022年とされているが、約3割の専門家がこの目標の達成は不可能と考えている。また、この課題に対しては、多くの専門家が「大幅なエネルギー源の転換が必要」、「世界的なコンセンサス、南北間対話、相互信頼が不可欠」、「社会的諸施策を並行して実施すべき」等のコメントを加えている。 「世界的な地球環境保全対策の普及」については重要度指数が87と高く、全課題の中でも41位と重要度が高く評価されている。政府のとるべき有効な手段としては研究資金の拡充が高率となっている。「深海でのCO2貯留技術の開発」は、比較的早い2014年の実現が予測されているものの、「深海環境への影響評価がカギ」という新たな環境問題が提起されている。京都会議では森林の吸収分を差し引くネット方式の採用が合意されたが、生物の機能を活用したCO2固定化の課題は5課題と多く、大部分は2010年代後半に実現すると予測されている。その技術課題の推進方策として「政府負担研究資金の拡充」「人材の養成・確保」を挙げている専門家が多い。
|
| 技術専門家も経済的・倫理的対応を重視 |
|
今回、新たに資源・エネルギー分野及び環境分野では、地球環境に関連する長期シナリオ等に関する質問として温暖化ガスの排出に関するIPCCの30年後の3つのシナリオである、排出量が増大するケース、減少するケース、中間的なケースを提示し予測を求めたところ、約8割が中間的なケースを選択している。また、今後の地球環境問題に最も有効な対応策については、環境分野の専門家は、規制を含む経済的対応が有効と答えた者46%、ライフスタイルの変更など倫理的対応の35%をあわせると8割強の専門家が技術以外の対応が有効と回答している。資源・エネルギー分野の専門家は経済的対応が有効とする回答が多く、技術的対応を有効とする者は23%にとどまっている。
|
| 今後、何をすべきか |
|
地球環境問題に有効な対応については、技術よりはむしろ規制を含む経済的対応やライフスタイルの変更などの倫理的対応が重要であると専門家は考えている。そこには我が国の省エネ技術などが既に最高水準にあり、これ以上の効率性の改善等は困難との専門家の現状認識が指摘されている。また、地球環境問題の根元には途上国の人口増大問題、南北問題等の政治問題がある。
豊かな生活、快適性の追求という人間本来のニーズの実現のため、関連技術を駆使し、その使命や期待にも十分応えていく必要があることは言うまでもない。現在、私達は膨大なエネルギー消費に支えられた快適な消費生活を享受しているが、まず、先進国の個々人の意識の変化とともに、ライフスタイルの変更を受け入れる心のゆとりが産業界の省エネ対策を一層促進し、CO2の大幅な削減が実現されることを肝に命じるべきだろう。
|
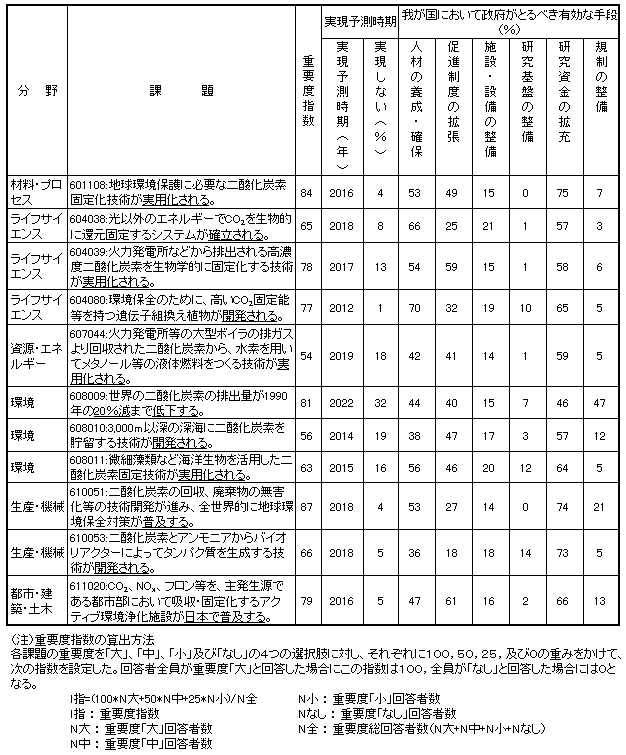
第3調査研究グループ 特別研究員 申 淳浩
 私は、科学技術政策研究所第3調査研究グループの申 淳浩(SHIN Soon
-ho)と申します。今年の9月初めに、大韓民国気象庁から派遣されてきま
した。現在、科学技術政策研究所で日本のテクノポリスの現況を調査してい
ます。
私は、科学技術政策研究所第3調査研究グループの申 淳浩(SHIN Soon
-ho)と申します。今年の9月初めに、大韓民国気象庁から派遣されてきま
した。現在、科学技術政策研究所で日本のテクノポリスの現況を調査してい
ます。
「科学技術政策研究所での生活」
一日は短いが6ヶ月はあんまり長い!
これが私の毎日の科学技術政策研究所第3調査研究グループへの出勤と退勤の独り言です。
なぜならば、故国で日本へ渡った時、少しずつ休みながら、仕事もするし、人生哲学とか、個人的な趣味生活等も持とうという夢を抱いてきたんですが、今まで3ヶ月が過ごしても一度も心の易い時間はないです。
それは、この第3調査研究グループの職員たちが朝の8時半からほどんと毎日の午後10時くらいまでに、前でも、横でも、遠い総括までも、一度もわき目もふらず、彼らの仕事だけをするからです。
そして、私も彼らと一緒に私の義務をしなければならないですから、私は夢もないし、趣味生活もないし、故国でのように仕事だけをしなければならないのです。
それでも、彼ら職員たちが、だれにも平素の親切性、勤勉性、誠実性等を見るながら先進国らしい面貌を習って身に付けようと思います。
「日本の生活」
現在、私は東京都江戸川区一之江に住んでいます。
この回りは田園のように静かだし、特に、新中川があるから、この川辺は私の散歩コースとして、毎週の休みは流れる江水を見ながら故国のノスタルジアを紛らすし、家族とか仕事とか等を思い出しています。
一方、日本では都市の美観とか休息空間等を図る様々な施設が整備になっているが、その中でも小さな児童公園から歴史的な上野公園に至るまで沢山あるし、特に都市交通の条件は予想よりもよくなってあったから、どこへでも行ける便利な地下鉄、速い新幹線等が、料金が高いけど正確な時間、自由な都市生活をすることができるようになっている。
こんな社会基盤施設は偉く備えているけど、いやな実状も沢山ある。たとえば、市民の休息空間の公園とか川辺等には精神的な障害者が沢山暮らしているから、市民の嫌悪感とともに都市美観を害するとか、家族の外出時とか、子女たちの教育にもかなり悪いことをかけているからです。
| プロフィール | |
| 出身地: | 大韓民国全羅南道高興郡過駅面老日里 |
| 最終学歴: | 延世大学行政大学院卒(専攻:都市行政、行政学碩士) |
| 職歴: | '85.8 科学技術処大徳研究団地管理所開発課(行政事務官)
'87.12 科学技術処研究開発調整室動力資源研究官室 '90.12 '93大田EXPO世界博覧会組織委員会科学技術局技術一課長 '93.3 科学技術処研究開発調整室基礎研究調整官室 '96.8〜現在 気象庁総務課(書記官)
|
○会議開催
第2調査研究グループ
「STS国際会議」の開催
|
組織委員会事務局 〒182 東京都調布市調布ケ丘1−5−1 電気通信大学大学院情報システム学研究科 小林信一気付 STS国際会議事務局 Eーmail:sts@kob.is.uec.ac.jp Fax:0424−85−9843 |
○ 研究会等/Research Meetings
○ 講演会等/Lectures at NISTEP
○ 主要来訪者一覧/Foreign Visitors to NISTEP
○ 海外出張