
 |
No.107 SEP 1997 | |
| 科学技術庁科学技術政策研究所 | ||
| NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE | ||
| AND TECHNOLOGY POLICY |
| 目次 [Contents] |  | レポート紹介 Highlight of the New Report |
 | 最近の動き Current Topics |
Ⅰ.レポート紹介/Highlight of the New Report
| 技術予測調査研究チーム |
| 桑原輝隆、鈴木宏二、西本昭男、田口正路、古閑知明 |
| 佐藤寿守、楠瀬文子、成毛理恵、辻亜紀子 |
1.調査の目的
科学技術庁では、長期的視点に立って我が国の技術発展の方向を探るため、科学技術分野における技術予測調査を1971年以来これまでに5回にわたり約5年間隔で実施してきている。本調査はその6回目として、科学技術振興調整費により平成7年度から8年度に実施したものである。
2.調査の方法
(1)調査の実施体制
科学技術政策研究所に技術予測委員会を設置し、調査の全体計画、実施方針などを検討するとともに、これに沿って、財団法人未来工学研究所に技術予測委員会の委員を主査とする13の分科会(「資源・エネルギー」及び「環境」は一つの分科会で扱った。)を設置し、各分野における課題の設定、調査対象者の選出、調査結果の分析などを行った。また、科学技術政策研究所において、全分野を対象とする分析等を行った。
(2)予測期間
1996年(調査時点)から2025年までの30年間。
(3)調査対象分野(課題数)
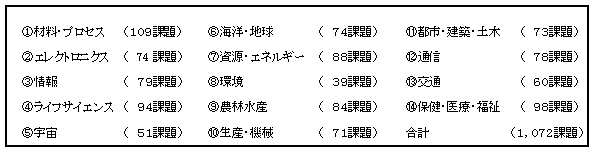
合計1072課題のうち、前回調査との同一課題が380,修正課題が233あり、その他の459課題が新規課題である。
(4)調査手法
調査は前回までと同様デルファイ法により行い、2回のアンケート調査により回答を収れんさせた。
(5)調査項目
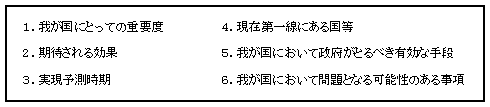
(6)アンケートの実施
調査対象者は、各分科会の委員の推薦等により選出し、事前に協力依頼を行い、了解を得られた人に第1回アンケートを送付した。アンケート調査票の発送時期は次のとおりである。
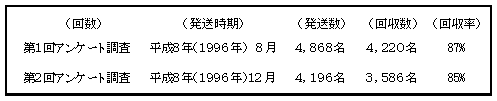
また、第2回アンケートの回答者の属性は次のとおりである。
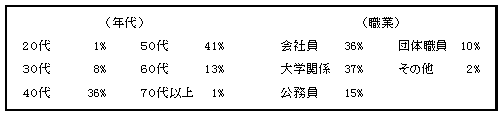
3.調査の結果(概要)
(1)重要度が高く評価された分野
分野毎の傾向は、図1のとおりであり、環境、エレクトロニクス及びライフサイエンスの各分野で重要度が高い。
| 図 1 重要度指数(分野別) |
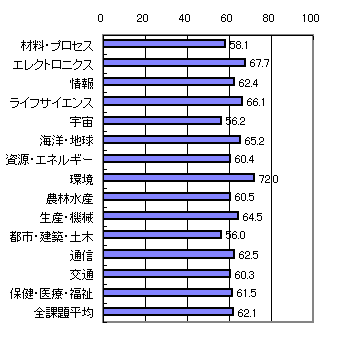 |
| 今回の調査における重要度上位100課題と第5回調査の重要度上位100課題を内容に応じて、 | |||
| ① | 地球規模の環境問題から身の回りのごみ処理までを含む環境関連技術 | ||
| ② | メモリなどの半導体及びインターネットなどのネットワークを含む情報関連技術 | ||
| ③ | 遺伝子技術、病気の治療など生命関連技術 | ||
| ④ | 地震その他の自然災害の予知・防災に関する災害関連技術 | ||
| ⑤ | 太陽エネルギーの利用など非化石エネルギーの利用に関する新エネルギー技術 | ||
| の5つに区分をしてみると次のとおりとなる。 | |||
| 区分 | 第6回 | 第5回 |
| 環境関連技術 | 25 | 28 |
| 情報関連技術 | 24 | 10 |
| 生命関連技術 | 17 | 37 |
| 災害関連技術 | 11 | 9 |
| 新エネルギー関連技術 | 11 | 6 |
| その他 | 12 | 10 |
注目されるのは、情報関連技術が大幅に増加し、生命関連技術が減少していることである。また、新エネルギー関連技術も増加している。
①環境関連技術の内容を見ると、リサイクルしやすい製品設計概念の定着、プラスチックのリサイクル技術の実用化などの「リサイクル」関連技術が9課題(前回4課題)と増えている。一方、二酸化炭素固定技術、フロン・ハロン代替品の実用化等の「地球環境」に関する技術は7課題(前回13課題)と減少しており、環境関連技術としてより身近で具体的な取り組みが重視されるようになっていることが示されている。
②情報関連技術については、セキュリティーの高い次世代インターネットの実用化、プライバシーや機密が保護されるネットワークの普及等の「ネットワーク」システム技術が12課題(前回2課題)、256ギガビットメモリの実用化、10ナノメータの寸法のパターンの量産加工技術の実用化等の「半導体等」関連技術が11課題(前回6課題)と共に増加している。前回調査以降の5年間に我が国を始め世界的にインターネットが急速に普及し、サービスの多様化、安全性の向上などが強く意識されるようになってきていることがこの背景として考えられる。
③生命関連技術については、がんの転移を防ぐ手段の実用化等「がん」関連の課題は9課題(前回10課題)とあまり変化はないが、アルツハイマー型痴呆の治療等の「脳」関連課題が1課題(前回8課題)となり、また動脈硬化等各種の病気の治療に関連した課題の数も減っている。今回の調査においてもライフサイエンス分野の重要度指数の平均値は高いので、生命関連課題の上位にくる課題の数が相対的に減少したのは、必ずしも重要度が低下したというわけではなく、情報関連技術が今回強く重視されるようになったこと等が原因とみられる。
④災害関連技術については、「地震」に関連した技術課題が8課題(前回4課題)と増加したことから全体としても数が増えている。
⑤新エネルギーについては、「太陽電池」関連の技術が4課題(前回2課題)と増加し、かつ、いずれも上位の10位前後になっている。原子力等その他の技術については大きな変化はない。
各課題の重要度を「大」、「中」、「小」及び「なし」の4つの選択肢に対し、それぞれに100,50,25及び0の重みをかけて、次の指数を設定した。回答者全員が重要度「大」と回答した場合にこの指数は100、全員が「なし」と回答した場合には0となる。
| I指=(100*N大+50*N中+25*N小)/N全 | |||||
| I指 | : | 重要度指数 | |||
| N大 | : | 重要度「大」回答者数 | |||
| N中 | : | 重要度「中」回答者数 | |||
| N小 | : | 重要度「小」回答者数 | |||
| Nなし | : | 重要度「なし」回答者数 | |||
| N全 | : | 重要度総回答者数(N大+N中+N小+Nなし) | |||
(2)期待される効果の大きな技術の動向
| 各課題についてどのような効果が期待されるかを、以下の4つの項目を取り上げ、複数回答で調査を行った。 | |||
| 社会経済発展への寄与 | : | 革新的製品の開発、新産業の創出、経済フロンティアの拡大、社会経済基盤の整備等 | |
| 地球規模の諸問題の解決 | : | 地球環境、食料、エネルギー、資源問題等 | |
| 生活者ニーズへの対応 | : | 疾病の予防・克服、生活環境の向上、高齢者・身障者の支援、防災・安全の確保等 | |
| 人類の知的資源の拡大 | : | 新しい法則・原理の発見、独創的理論の構築等 | |
| 各課題についてのパーセントを分野毎に平均すると図2のとおりである。社会経済発展への寄与が高いと考えられているのはエレクトロニクス、通信、材料・プロセス、生産・機械、情報などの分野であり、地球規模の諸問題の解決に向けては環境、資源・エネルギー、農林水産などの分野が重視されている。一方生活者ニーズへの対応としては、保健・医療・福祉、情報、都市・建築・土木等の分野に重視された課題が多い。 | |||
| 図 2 期待される効果の傾向(分野別) |
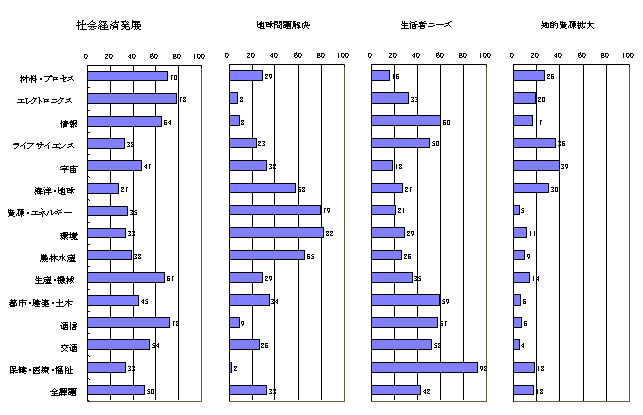 |
| 《効果が大きいと期待される課題の例》 | ||
| 「社会経済の発展への寄与」 | ||
| ・ | (エレクトロニクス)世界で使用可能なマルチメディア無線携帯端末の普及 | |
| ・ | (通信)セキュリティが高くリアルタイム性の高い情報も送れる次世代インターネットの実用化 | |
| 「地球規模の諸問題の解決」 | ||
| ・ | (環境)地球環境保全のための環境税の導入 | |
| ・ | (資源・エネルギー)廃車等から重要金属を99%以上の純度で分離する技術の実用化 | |
| 「生活者ニーズへの対応」 | ||
| ・ | (保健・医療・福祉)成人病予防用のための生活様式(栄養、休養、運動)の科学的指針の普及 | |
| ・ | (情報)家庭または病院等において介護を支援するロボットの実用化 | |
| 「人類の知的資源の拡大」 | ||
| ・ | (宇宙)惑星からのサンプルリターンの実施 | |
| ・ | (ライフサイエンス)生命誕生の分子機構の解明 | |
(3)実現予測時期の傾向
全課題(1072課題)の実現予測時期の分布を図3に示す。
| ・ | 実現予測時期の比較的早い課題の多い分野:情報、通信 | |
| ・ | 実現予測時期の比較的遅い課題の多い分野:資源・エネルギー、ライフサイエンス | |
| ・ | 2005年までに実現すると予測された課題は少ないが、その中では情報、通信の比率が高い。 | |
| ・ | 2006年〜2010年及び2011年〜2015年の5年間に実現すると予測された課題は、それぞれ全体の1/3強を占めており、この10年の間に実現すると予測された課題数は全体の3/4にのぼる。 |
| 図 3 実現予測時期の動向 |
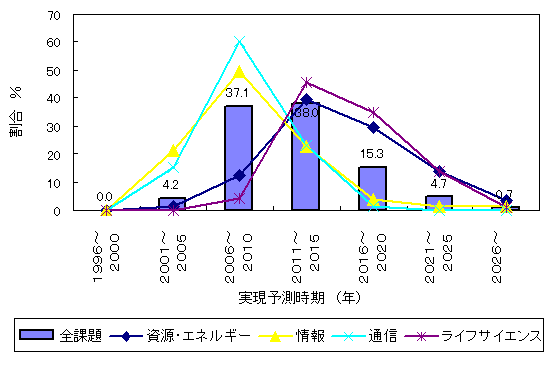 |
| 各課題の現在第一線にある国・地域を、 | ||
| ①アメリカ、②EU、③旧ソ連・東欧諸国、④日本、⑤その他の国、⑥わからない | ||
| の6つからの複数回答で調査を行った。 | ||
| ここでは、分野毎に上記①〜⑥の回答割合の課題平均を計算し、さらにこれを百分率(%)に直してグラフ化している。(図4参照) | ||
| ・ | 14分野の内11分野において「アメリカ」の比率が最も高い。 | |
| ・ | 「アメリカ」の比率が特に高い分野:宇宙、ライフサイエンス、情報、通信、保健・医療・福祉 | |
| ・ | 「日本」の比率が他の国・地域より高い分野:資源・エネルギー、都市・建築・土木、交通 | |
| ・ | 「EU」の比率が比較的高い分野:環境、交通 | |
| ・ | 「旧ソ連・東欧諸国」の比率が比較的高い分野:宇宙 | |
| 図4第一線にある国等(分野別) |
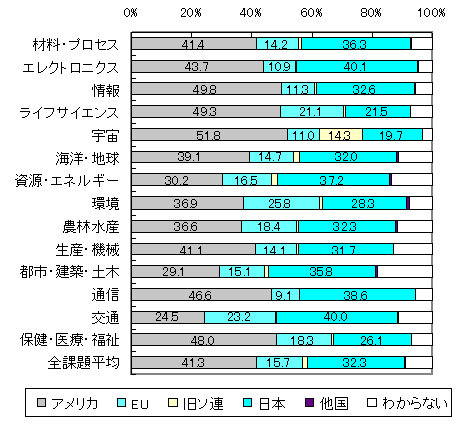 |
(5)政府がとるべき有効な手段
| 予測の対象として取り上げた課題の推進方策として、政府が取るべき施策があるかどうか、あるとすればそれは何かについて、以下の項目から最大3つまでの複数選択で回答者の見解を求めた。 | ||
| ① | 研究者、技術者及び研究支援者の養成・確保 | |
| ② | 産学官の人的交流、異分野間の協力等の促進制度の拡充 | |
| ③ | 先端的な研究開発施設・設備の整備及び開放 | |
| ④ | データベース、標準物質、遺伝子資源等の研究基盤の整備 | |
| ⑤ | 政府が負担する研究資金の拡充 | |
| ⑥ | 関連する規制の整備(緩和、強化、新設、廃止) | |
| ⑦ | その他 | |
| 各課題についてのパーセントを分野毎に平均すると図5のとおりとなる。全課題平均が比較的高いものとして、⑤政府が負担する研究資金の拡充、①研究者、技術者及び研究支援者の養成・確保、②産学官の人的交流、異分野間の協力等の促進制度の拡充があげられる。 | ||
| 図 5 政府がとるべき手段(分野別) |
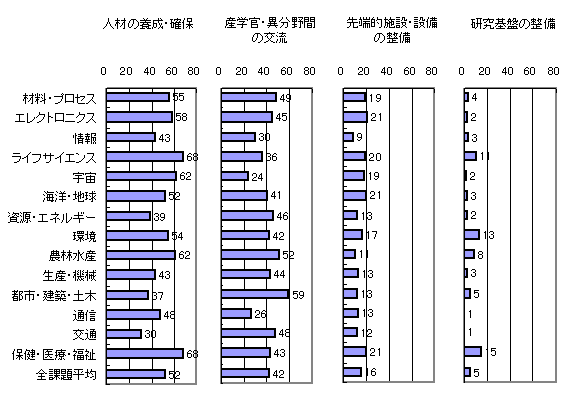 |
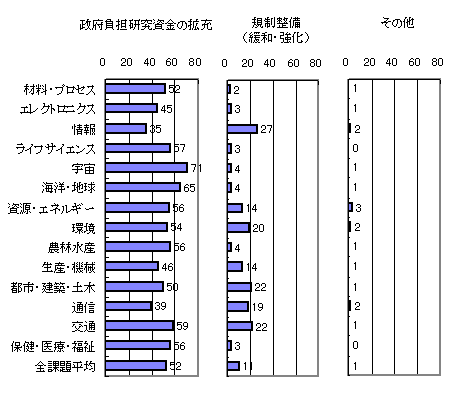 |
| それぞれの課題の実現に関連して、事前に考慮すべき点があるかどうかについて、 | ||
| ① | 自然環境への悪影響、 | |
| ② | 安全への悪影響、 | |
| ③ | 倫理・文化・社会への悪影響、 | |
| ④ | その他の悪影響 | |
| の4項目から最大2つまでの選択により評価を求めた。 | ||
| 各課題についてのパーセントを分野ごとに平均すると次の図6のとおりとなっている。 | ||
| 図 6 我が国において問題となる可能性のある事項の傾向(分野別) |
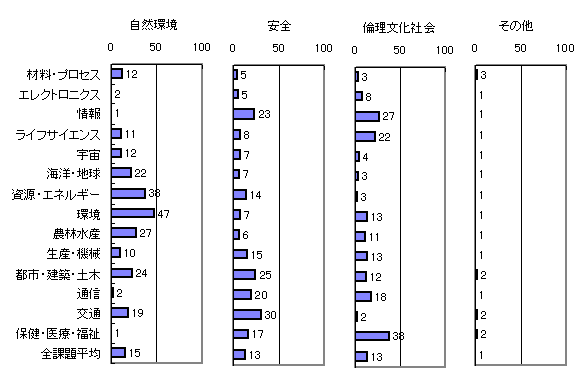 |
| 《悪影響に対する懸念の大きい課題の例》 | ||
| 「自然環境への悪影響」 | ||
| ・ | (環境)3000m以深の深海に二酸化炭素を貯留する技術の開発 | |
| ・ | (農林水産)水温変化等に高耐性で養殖に有利な水産生物の細胞融合、遺伝子操作等による開発 | |
| 「安全への悪影響」 | ||
| ・ | (交通)ビル内占有容積当りの輸送力が現在のエレベータの5倍以上のシステムの実用化 | |
| ・ | (通信)印鑑なしで契約書等がオンラインで作成できるサービスの普及 | |
| 「倫理・文化・社会への悪影響」 | ||
| ・ | (保健・医療・福祉)年齢に応じた老化度の定量的把握方法の実用化 | |
| ・ | (情報)電気磁気情報により人間の脳に記憶されている情報を解読 | |
(7)第1回、第2回技術予測調査結果の評価・分析
《評価方法》
第1回及び第2回調査の全課題をその内容に応じて各分科会に配分し、分科会において分科会委員を中心に実現の状況の検討を行った。この際各課題毎に、
| ・ | 実現 | : | 1996年までに実現した |
| ・ | 一部実現 | : | 1996年までに課題の一部が実現した |
| ・ | 非実現 | : | 上記以外 |
| のいずれかに当てはまるように評価を行った。 | |||
| なお、一部実現は、以下の内容をいう。 | |||
| ・ | 一つの課題の中で複数の事柄を予測しており、その一方が実現し、他方は実現していない。 | ||
| ・ | 題の中で表現された言葉(性能を表す形容詞を含む)の定義が不明確で、その解釈によってどちらにもとれる。 | ||
| ・ | 課題で要求されている内容の一部が実現されている。 | ||
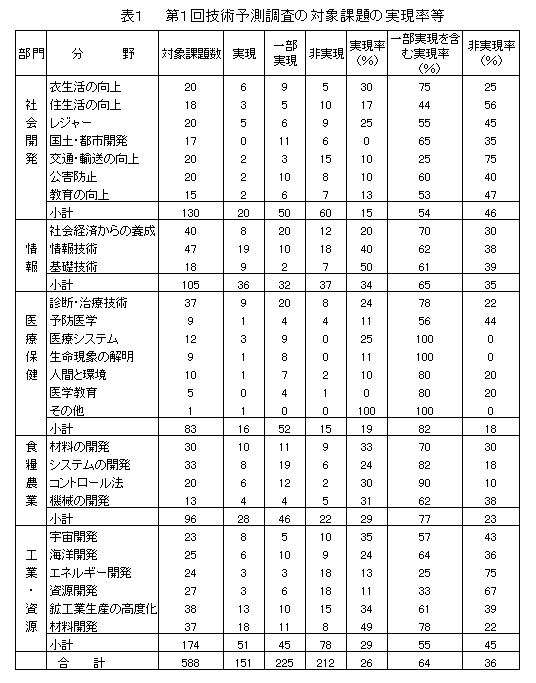 |
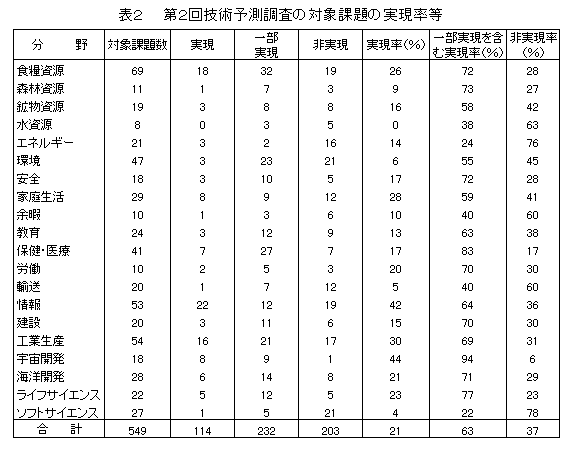 |
技術予測は、ヨーロッパを始めアジア各国においても科学技術政策の立案や技術開発計画策定に当たっての有効なツールと考えられており、様々な国で実施されるようになっている。
特に最近開始した国々では、科学技術全体についての包括的な将来像が得られることに加えて、調査のプロセス自体がコンセンサス形成に役立ち、また参加する専門家にとっても様々な「学習」効果つことの効果が大きいと考えられている。
| ドイツ | 1993年 デルファイ法による技術予測調査報告書(日本の第5回調査のアンケート表を使用) 1994年 日独技術予測比較報告書(日独共同レポート) 1995年 日独ミニデルファイ調査報告書(日独共同調査) 現在、日本の第6回調査に対応した技術予測調査を実施中。約40%の技術課題は日本の調査と共通。報告書は1997年末頃公表の予定。 |
| イギリス | 1994年から1995年にかけて技術予測を実施。デルファイ調査とともに、イギリス各地で各分野に関するパネルディスカッションを実施した。 次の予測調査は1999年頃実施する予定。 |
| フランス | 1994年 デルファイ法による技術予測調査報告書(日本の第5回調査のアンケート表を使用) |
| 韓国 | 1994年 技術予測報告書 技術政策管理研究所(STEPI) |
| タイ | 1995年 デルファイ法による技術予測調査NSTDA APECのプログラムとして、バンコクに「技術予測APECセンター」を設置すべく、現在フィージビリティスタディーを実施しており、本年6月上旬タイで国際シンポジウムを開催した。1998年春の発足を目指している。センターの機能としては、メンバー国などに対する技術予測情報の提供、予測専門家の教育訓練、APEC内共同予測プロジェクトの実施など。 |
| オーストラリア | 1996年 オーストラリア科学技術会議(ASTEC)が21世紀に向けての科学技術に対するニーズの総合調査を実施。 |
| インドネシア | 1996年よりデルファイ法による技術予測調査を実施中。 |
| オランダ | 1980年代よりいくつかの分野について小規模な調査を実施。 |
| 国連工業開発機関 (UNIDO) |
南米において、技術予測プログラムの実施を準備中。1996年12月ボリビアで国際会議を開催。 |
| その他 | イスラエル、南アフリカ、マレーシアなどにおいて実施中あるいは準備中 |
第3調査研究グループ
仁井 寛喜
1.調査目的本調査では、科学技術政策研究所が従来より「外国為替及び外国貿易管理法」による技術導入契約の締結(変更)に関する報告書等に基づき毎年作成している「外国技術導入の動向分析」の輸出版的な資料を作成することを目的として、平成4年度より毎年民間企業に対してアンケート調査を実施し、輸出された技術の内容、契約形態、対価の受取方法といった技術輸出の質的な面の分析を行っている。
2.調査方法及び回収状況
| ①調査対象企業 | : | 資本金10億円以上で、研究開発活動を実施している企業および技術貿易と関連のある日本国内の民間企業(1,597社) | |
| ②調査対象契約 | : | 平成7年4月1日以降平成8年3月31日までの1年間に締結された技術輸出契約 | |
| ③調査方法 | : | 郵送によるアンケート調査とし、上記各社の知的財産部門長もしくは研究開発管理部門長へ直接郵送した。 | |
| ④調査期間 | : | 平成9年1月9日(発送)から平成9年2月10日(締切)までの間に実施した。 | |
| ⑤回収結果 | : | 回答企業数 1,032社(回収率64.6%) |
なお、今年度は資本金1億円以上10億円未満の企業503社を抽出し、同様の調査を実施している。
3.調査事項
「外国技術導入の動向分析」との比較対照のため、当調査の設問は「外国技術導入の動向分析」の調査項目を参考にして作成している。
| 調査項目 | |||
| ①企業について | : | 産業分類、資本金規模 | |
| ②輸出された技術について | : | 技術の内容、技術分類、技術の種類、内包する特許数、特定技術分野 | |
| ③契約相手先企業について | : | 輸出先国・地域、資本関係 | |
| ④契約形式 | : | 契約期間、契約形態、対価の受取方法、独占権・再実施権の有無 | |
4.調査結果の概要
(1)平成7年度の技術輸出の傾向
①技術輸出件数
| ・ | アンケート回答企業1,032社(調査対象企業1,597社)のうち平成7年度に新規の技術輸出を実施した企業数は235社であり、その契約件数は766件となっている。 |
| ・ | 輸出先を地域別にみると、アジアが64.5%、北アメリカが18.7%、ヨーロッパが13.1%、その他が3.8%であり、3年連続してアジアの比率が増加し、今年度は全体の約3分の2を占めている。 |
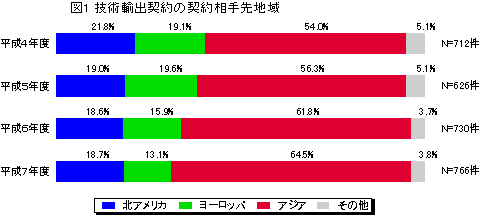
| ・ | 国・地域別にみると、米国が17.0%と最も多くなっているが、以下、韓国(16.3%)、中国(15.8%)、台湾(8.5%)、タイ(8.1%)の順となっており、上位5ヶ国・地域のうち4ヶ国・地域をアジアが占めている。また、年度毎の推移をみると中国の比率が引き続き大きく増加している(H4 7.9%→H7 15.8%)。 |
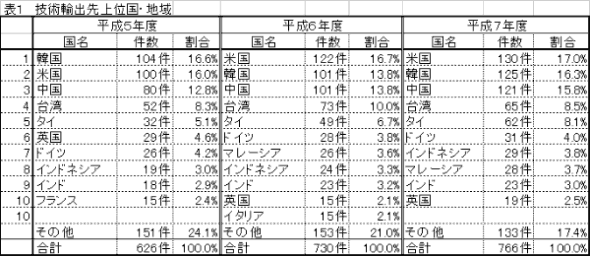
③輸出された技術の内容
| ・ | 技術分野をみると、「電気」分野27.0%、「機械」分野24.9%、「化学」分野20.6%、「金属」分野14.6%、「その他」分野12.8%の順となっており、各分野から比較的均等に輸出されている。 |
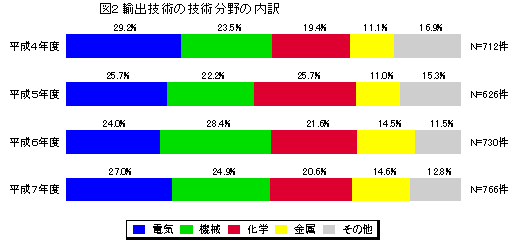
| ・ | 技術分類別にみると、「輸送用機械」に関する技術が4年連続して最も多く、今年度も前年度と同じく全契約の15.0%と非常に高い割合を占めている。 |

(2)技術輸出の全般的傾向
①契約先との資本関係
| ・ | 資本関係のある企業への輸出は42.6%で2年連続増加している。 | |
| ・ | アジアでは資本関係のある企業への輸出が約半数(50.8%)を占める。 |
②契約期間
| ・ | 「5〜10年」が35.8%、「1〜5年」21.7%。 | |
| ・ | 地域別にみると、アジアは欧米と比べて、「工業所有権等の期間まで」の割合が低く、「5年以上10年未満」の割合が高い。 |
③対価の受取方法
| ・ | 「ランニングロイヤルティのみ」は41.1%、「イニシャル+ランニング」は36.7%、「イニシャルペイメントのみ」は17.2%。 | |
| ・ | 資本関係のない企業への輸出では「イニシャルペイメントのみ」の割合が高く、資本関係のある企業への輸出では「ランニングロイヤルティのみ」の割合が高い。 | |
| ・ | ランニングロイヤルティの料率は「2%以上5%未満」の割合が過半数(57.3%)を占める。 |
④独占権・再実施権
| ・ | 「独占権有」は27.7%、「再実施権有」は7.4%。 | |
| ・ | 地域別にみると、アジアで「独占権有」が高く、「再実施権有」が低い。 |
⑤技術の種類
| ・ | 「特許有」は39.7%、「ノウハウ有」は83.7%、「商標有」は18.1% | |
| ・ | 地域別にみると、アジアでは欧米と比べて、「特許有」の割合が低く、「ノウハウ有」の割合が高い。 |
(3)技術輸出入の比較
我が国の技術貿易は、日銀統計や総務庁統計によると輸出額の伸びが輸入額の伸びを上回っており、技術貿易金額の総量的な面では入超から均衡へと変化しつつある。しかし、本調査と「外国技術導入の動向分析」の調査結果を用いて、輸出入を質的に比較すると、以下に挙げるような大きな違いがあることがわかる。
| ①技術形態 | |||
| −ハード系技術中心の技術輸出、ソフトウェアがハード系技術を上回る技術輸入− | |||
| ・ | 技術輸出においては、ハード系技術が全体の92.8%を占めている。 | ||
| ・ | 技術輸入においては、ソフトウェアが49.2%を占め、ハード系技術を上回っている。 | ||
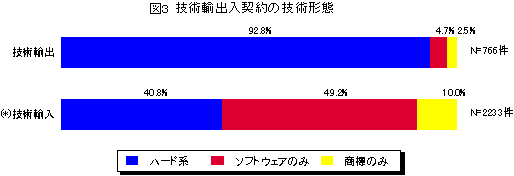
| ②契約相手先地域 | |||
| −欧米から技術輸入し、アジアへ技術輸出− | |||
| ・ | 技術輸出においては、アジアの割合がハード系技術で65.4%、ソフトウェアで42.4%と最も高くなっている。 | ||
| ・ | 技術輸入においては、北アメリカの割合がハード系技術で66.2%、ソフトウェアで82.6%と最も高くなっている。 | ||
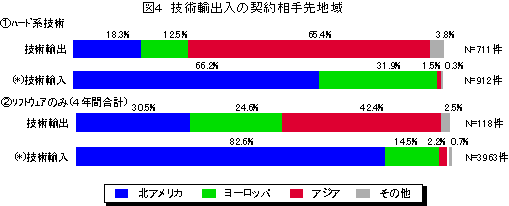
| ③技術輸出入と直接投資の関連 | |||
| −対外直接投資との関連が深い技術輸出、対内直接投資との関連が浅い技術輸入− | |||
| ・ | 技術輸出においては資本関係のある(資本の2分の1以上、2分の1未満の両方を含む)企業への輸出の割合が、ハード系技術で42.8%、ソフトウェアで45.8%と高くなっている。 | ||
| ・ | 技術輸入においては外資系企業(外国企業が資本の2分の1以上を所有する企業)による技術輸入の割合が、ハード系技術でもソフトウェアでも1.2%と非常に低くなっている。 | ||
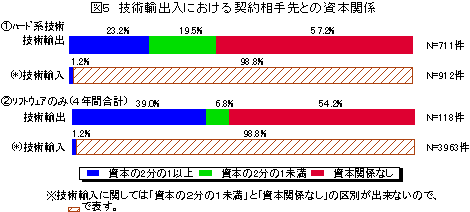
| ④輸出入されている技術の内容 | |||
| −「輸送用機械」の占める割合が高い技術輸出、電気関連の技術の割合が高い技術輸入− | |||
| ・ | 技術輸出においては「輸送用機械」が4年連続首位を占めている。 | ||
| ・ | 技術輸入においては「電子・通信用部品」、「電子計算機」、「通信機械」等の「電気」分野の技術が上位を占めている。 | ||
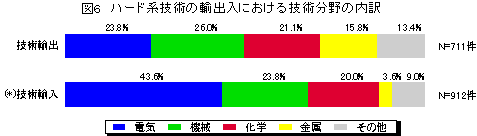
| ⑤技術輸出入の契約条件 | |||
| −技術輸入と差がある技術輸出の契約条件− | |||
| (1)契約期間 | |||
| ・ | 技術輸出においては、ハード系技術についても、ソフトウェアについても「10年未満」の契約の割合が高くなっている。 | ||
| ・ | 技術輸入においては、ハード系技術については「工業所有権期間」、ソフトウェアについては「その他(期間の定め無し等)」の割合が高くなっている。 | ||
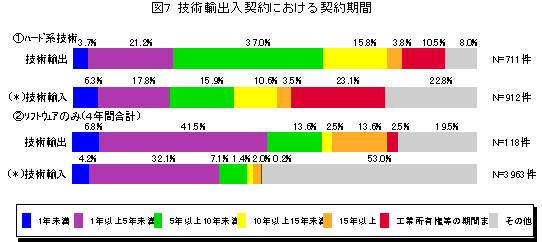
| (2)対価の受取方法 | ||
| ・ | ハード系技術については、技術輸出においては「ランニングロイヤルティのみ」の割合が高く、技術輸入においては「イニシャルペイメントのみ」の割合が高い。 | |
| ・ | ソフトウェアについては、技術輸出入ともに「イニシャルペイメントのみ」の割合が高い。 | |
| ・ | ランニングロイヤルティの料率をみると、技術輸出は技術輸入と比べて低率設定の割合が高い。 | |
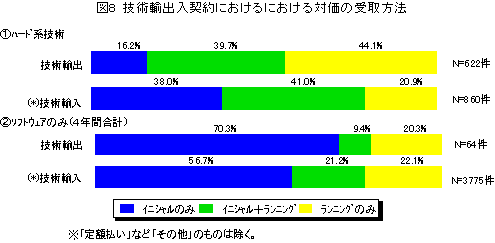
| ①欧米への依存 | |
| 我が国の技術貿易は欧米から輸入し、アジアへ輸出するという流れが基本的な構造になって いる。近年日本の技術輸出額は大幅に増加しているが、欧米と対等な技術取引をしているので はなく、アジアへの直接投資の増加に伴い、その投資先への技術輸出額が増加しているのに過ぎない。未だ、欧米と我が国の技術力の差が大きいことは否定できない。 |
| ②ソフトウェアの大幅な入超 | |
| ハード系の技術については、アジアだけでなく欧米に対してもある程度輸出されている。しかしソフトウェアについては、近年大きく輸入件数が増加しているのに対して、輸出に占める割合は非常に低くなっている。今後ソフトウェア開発能力の向上が我が国にとって急務であると思われる。 |
| ③外資を伴った技術導入の不調 | |
| 近年我が国の製造業は、内外の製造コストの格差の拡大につれて、東アジアを中心に対外直接投資を大幅に増加させており、その投資先への技術輸出件数が急増している。一方、外国企業による対内直接投資は低調であり、外資系企業による技術導入件数は非常に低い水準に留まっている。今後外国企業にとって魅力のある投資環境を整備し、外資導入に伴う技術移転を増加させることも必要であると思われる。 |
| ④輸入と差がある輸出の契約条件 | |
| 我が国の技術貿易は、輸出はアジアとの、輸入は欧米との取引がそれぞれ中心となっている。アジアの一部の国・地域では、欧米と比べて技術に対する意識が低く、技術輸出側の権利よりも技術輸入国の利益が優先されることが多くなっている。そのために、技術輸出は技術輸入と比較して、契約期間やランニングロイヤルティの料率などの契約条件に違いが見られる。今日輸出している技術は将来の技術の原資となるものであり、その権利の保護が重要であると思われる。 |
| ○ 講演会等/Lectures at NISTEP | |||
| ・ | 8/26 (火) | 「STS(Science, Technology and Society)研究の動向等について」 | |
| 長濱 元 (東洋大学 国際地域学部教授) | |||