
 |
No.103 MAY 1997 | |
| 科学技術庁科学技術政策研究所 | ||
| NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE | ||
| AND TECHNOLOGY POLICY |
| 目次 [Contents] |  レポート紹介 Highlight of the New Report レポート紹介 Highlight of the New Report |
 講演会紹介 Highlight of the Lectures at NISTEP 講演会紹介 Highlight of the Lectures at NISTEP | |
 最近の動き Current Topics 最近の動き Current Topics |
Ⅰ.レポート紹介/Highlight of the New Report
第1研究グループ
後藤 晃
永田 晃也
この調査では、各国の製造業に属する企業を対象とした質問票調査により、イノベーションの重要な決定要因である専有可能性と技術機会に関するデータを取得した。専有可能性とは、企業が自ら行ったイノベーションのもたらす利益をどの程度確保することができるかに関する概念であり、また技術機会とは企業の研究開発が効果的にイノベーションに結び付くような情報に接する機会を意味する。
米国では1980年代にイェール大学の経済学者らが、米国企業を対象とした質問票調査により専有可能性と技術機会の実態を分析して注目を集めたが、今回の調査はその国際比較版としての性格を有している。日本側調査は当研究所が実施し、米国側調査はカーネギー・メロン大学のウェズリー・コーエン、イリノイ大学シカゴ校のジョン・ウォルシュらが、また欧州側調査はMERIT(Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology)のアンソニー・アルンデルが担当した。ただし、このレポートでは、調査データの日米比較を中心にとりまとめを行った。
日本側調査では、1994年9月に1,219社に対して質問票を郵送し、643社の回答を得た(回収率52.7%)。一方、米国側調査は同じ頃、3,240社を対象として実施され、1.478社から回答が得られた(回収率46.0%)。これらのデータの比較可能性を考慮した結果、年間売上高5千万ドル未満の企業を除外し、最終的に日本企業593社、米国企業826社の回答を日米比較のサンプルとして用いることとした。
(1)イノベーションから得られる利益を専有するための方法
企業がイノベーションから得られる利益の専有可能性を確保するためには、特許による保護、企業機密、製品の先行的な市場化、優れた販売・サービス網や製造設備・ノウハウの保有などの様々な方法がとられると考えられる。図1は、製品イノベーションについて、これらの方法が専有可能性を確保する上で効果を持ったプロジェクトの割合を示し、図2は工程イノベーションに関する同様の調査結果を示している。
これによると、製品イノベーションについては、最も有効な方法は日米とも「製品の先行的な市場化」であり、企業は製品をいち早く市場化し他社がキャッチアップしてくるまでの間に利益を上げることによって、イノベーションから得られる収益を確保していることが分かる。しかし、これについで有効な方法は両国の間で異なっており、日本では「特許による保護」であるが、米国では「技術情報の秘匿」となっている。
工程イノベーションについては、日本では「製造設備・ノウハウの保有・管理」、「技術情報の秘匿」の順に有効とされているのに対して、米国では「技術情報の秘匿」の有効性が突出しており、これについで「製造設備・ノウハウの保有・管理」となっている。工程イノベーションは設備に体化するため、優れた設備・ノウハウを保有することがイノベーションを補完する上で重要であり、また設備は製品と異なり社外へ出ることはないので、技術情報を企業機密にすることが製品イノベーションの場合よりも効果的であることが示されている。
また製品、工程のいずれについても、概して特許以外の方法の有効性は日本よりも米国の方が高くなっていることが注目される。
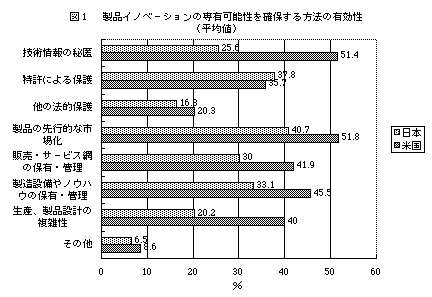
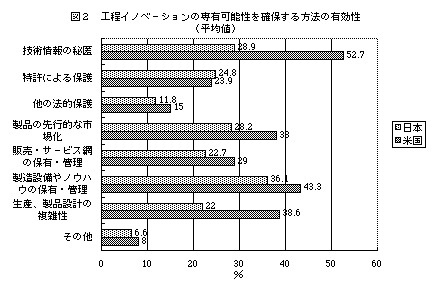
(2)イノベーションの模倣ラグ
専有可能性の程度は、イノベーションの模倣ラグの長さを指標としてみることもできる。図3は、企業が行ったイノベーションに対して他社が代替的な技術を導入するのにどの位の期間がかかるのかに関する調査結果を示している。
これによると、製品、工程のいずれについても、模倣ラグは特許化されなかったイノベーションよりも特許化された場合の方が長くなっており、特許が他社によるキャッチアップを遅らせる効果を持っていることが分かる。また、模倣ラグの長さは全般的に米国よりも日本の方が短くなっており、ライバル企業が自社のイノベーションにキャッチアップするまでの期間は、米国よりも日本の方が短いことが示されている。
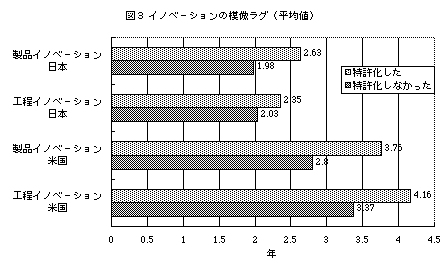
(3)技術情報の速度とプロジェクトの同質性
この調査では、企業間における技術情報の流出(スピルオーバー)の速さを把握するため、企業が競合他社の主要なイノベーションの存在を、そのプロジェクトのどのような段階(開始期、研究、開発、製品ないし工程の導入)で知ったのかについて質問した。また、競争がもたらす企業間のインタラクションを、プロジェクトの同質性という側面から把握した。
表1 に示す調査結果によると、研究段階までの間に競合他社のイノベーションの存在を知ったとする企業の回答割合は、米国の15.6%に対して日本では43.9%と高くなっている。一方、競合他社と同じ目的を持った研究開発プロジェクトの割合は日米間でほとんど差がなく、日本での技術情報のスピルオーバーの速さは、直ちにライバル企業間での同質的なプロジェクトをめぐる競争につながる訳ではないことがうかがえる。
| 研究段階までの間に競合他社のイノベーションを知った企業の割合* | 競合他社と同じ目的を持った研究開発プロジェクトの割合** | |
| 日本 | 43.9 | 52.1 |
| 米国 | 15.6 | 53.7 |
(4)専有可能性、開発競争およびイノベーションの速度の関係
専有可能性が高く、最初に開発に成功した企業が独占的に開発成果の生む利益を享受できるという状況の下では、一刻も早く開発成果を先取りしようとする企業間での開発ラッシュが発生することがある。このことは当該業種の研究開発集約度を高めるが、社会全体の資源配分の観点からみるとただ一つの研究開発が行われれば十分なのであり、その意味では無用の重複投資を引き起こすことにもなる。
| 製品イノベーションの専有可能性 | 工程イノベーションの専有可能性 | プロジェクトの同質性 | 製品イノべーションの速度 | |||||
| 製品イノベーションの専有可能性 | 1 | |||||||
| 工程イノベーションの専有可能性 | 0.4864 | 1 | ||||||
| プロジェクトの同質性 | 0.3604 | 0.1060 | 1 | |||||
| 製品イノベーションの速度 | 0.2974 | -0.0049 | 0.5401 | ** | 1 | |||
| 工程イノベーションの速度 | 0.1659 | 0.2221 | 0.3939 | * | 0.5987 | ** |
| 製品イノベーションの専有可能性 | 工程イノベーションの専有可能性 | プロジェクトの同質性 | 製品イノべーションの速度 | |||||
| 製品イノベーションの専有可能性 | 1 | |||||||
| 工程イノベーションの専有可能性 | 0.3031 | 1 | ||||||
| プロジェクトの同質性 | 0.6377 | ** | 0.0393 | 1 | ||||
| 製品イノベーションの速度 | 0.3690 | * | -0.0209 | 0.5536 | ** | 1 | ||
| 工程イノベーションの速度 | 0.3516 | 0.0272 | 0.4477 | ** | 0.8779 | ** |
この関係をみるために、調査結果から専有可能性、ライバル企業間におけるプロジェクトの同質性およびイノベーションの速度に関する指標をとり、それらの相関関係を分析した結果が表2および表3である。これによると、製品イノベーションについては、専有可能性の高さが重複的な研究開発を引き起こすという仮説が日米とも適合している。一方、ライバル企業間におけるプロジェクトの同質性とイノベーションの速度の関係をみると、製品、工程のいずれについても有意な正の相関がみられる点で日米の調査結果は一致しており、ライバル企業間の開発競争は研究開発のリードタイムを短縮させる効果を持っていることが分かる。
(5)大学・公的研究機関からの技術情報の利用
本調査では、日米の企業が研究開発を効果的に進めるために、イノベーションに結び付く情報をどのような機関からどのような頻度で取得しているのかを把握した。ここでは情報源としての大学・公的研究機関に関する調査結果の一部を取り上げる。
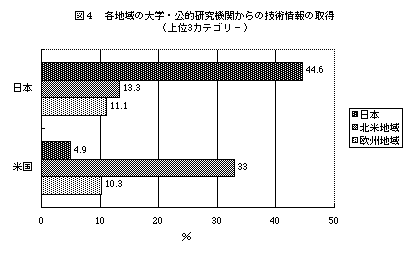
図4に示すように、月1回以上の頻度で大学・公的研究機関から技術情報を取得している企業の割合でみると、日米ともに自社の本国内の大学・公的研究機関からの情報の利用頻度が他地域からのそれを大幅に上回っている。情報の利用形態に関する調査結果によると、日米とも出版物についで「公開の研究集会・学会等」や「インフォーマルな情報交換」が重視されており、こうしたフェイス・ツゥ・フェイスによる情報を通じて提供される技術機会の重要性が、地理的に近接した大学・公的研究機関への接触を頻繁にさせている要因と考えられる。
国外の大学・公的研究機関からのフェイス・ツゥ・フェイスによる情報の取得は、当該地域に研究開発拠点を設置することによって容易になるであろう。今回の調査結果によると、国外研究開発拠点を設置している日本企業の割合は、北米地域については11.9%、欧州地域については5.7%であり、米国企業が国外研究開発拠点を設置している割合は、日本については10.9%、欧州地域については31.3%であった。
このように国外に研究開発拠点を設置することによって、当該地域の大学・公的研究機関の情報へのアクセスの頻度が高まるかどうかに関する相関分析を行った。この分析により、日本企業の研究開発拠点が北米や欧州に立地している場合や、米国企業の研究開発拠点が欧州に立地している場合は、いずれも当該地域の大学・公的研究機関の情報の利用頻度は高くなるが、米国企業の研究開発拠点が日本に立地しても、必ずしも日本の大学・公的研究機関の情報が活用されることにはならないという結果が示された。
企業の技術情報が外部にスピルオーバーする程度が高いという日本の特質は、一つの技術の上に改良を積み重ねていくタイプのイノベーションを実現していくプロセスには適合していた。しかし、より革新的なイノベーションを生みだし得るシステムへの転換が求められている今日においては、高度の専有可能性を確保する政策(例えば発明者の権利保護を強めるような特許制度の改革)によって、企業の研究開発投資インセンティブを高めていくことが求められると思われる。
このような政策は、一方で企業間における同質的な研究開発への重複投資を発生させる可能性を含んでいる。それは画期的なイノベーションを実現するための社会的なコストとしてやむを得ない面もあるが、同時に共同研究開発の促進などによって企業間の利害調整を図り、その社会的コストをできるだけ低減させることも必要となろう。
また、国外の大学・公的研究機関に対する情報アクセスをめぐって日米企業間にみられた非対称性は、基礎科学における日本の課題を浮き彫りにしていた。今後、わが国において外国企業にとっても研究開発の拠点立地のインセンティブとなる研究環境を形成するためには、イノベーションを刺激するような技術機会を提供できる大学・公的研究機関を整備していく必要があろう。
Ⅱ.講演会紹介/Highlight of the Lectures at NISTEP
政策研においては、より広範囲な科学技術政策研究に資する為、外部の講師を招いて講演をお願いしているところである。本稿では、「科学技術形成過程における評価に関する研究」の一環として、(株)パスコの坂倉副社長に政策評価についての講演をお願いした。同氏は通商産業省で長く政策立案・政策実施に携わり、その経験を踏まえたケーススタディを行われた。先日行われたその講演の概要を紹介する。
(株)パスコ副社長 坂倉省吾
戦後の復興のため、国内産業育成を規制及び制度によって保護していた。その後、昭和30年代、40年代、50年代にかけての政策推進は、輸入自由化対策と資本導入自由化対策が基本であった。輸入自由化対策では、ガット加盟(昭和30年)、IMF8条国移行(昭和34年)で始まり、コンピュータの輸入自由化(昭和50年)で100%自由化を完了し、また資本導入自由化対策では、OECD加盟(昭和35年)で始まり、コンピュータの資本導入自由化(昭和50年)で100%完了した。
外資に関する法律(外資法:昭和26年)では、外国の技術・資本を導入、そのための果実の送金を保証した。相手企業の技術の内容をチェック、国内企業の受入能力をチェック、国内企業同志の過当競争を防止、技術導入の条件を日本側に有利にし、資本導入では、日本側に経営の主導権を取らせる。外国為替・外国貿易管理法(昭和24年)では、外資法で技術導入を認めた企業について、必要な部品、材料、機械設備の輸入を認め、また技術導入を認めた同種製品の輸入を止め、国内市場を保護した。
機械工業振興臨時措置法(以下、機振法と記す)では、機械工業の基礎部門及び共通部品部門として19業種を指定し、技術開発目標、生産増強目標、年次技術開発計画、年次生産増強計画を作成した。生産設備への投資の為に日本開発銀行・中小企業金融公庫より長期低利融資、機械設備の特別償却、輸入機械の関税免除を行った。昭和40年頃からは、技術開発助成ということで、大型プロジェクト、サンシャイン計画などのプロジェクト開発が行われた。このプロジェクト開発の特徴は、長期計画(単年度主義でない)、研究委託方式、産学官連携、研究組合方式及び基礎技術開発を行い商品化は各企業がそれぞれ行うことであった。
昭和31年、自動車部品を機振法の指定業種に指定した。主要部品について、法律の有効期間5年間の「基本計画」を作成し、生産目標や技術レベルなどに関して毎年「実施計画」を作成する。それぞれの部品について、チャンピオン企業(原則的には上位2社)の育成を行う。機振法の対象企業は、毎年、通商産業省(以下、通産省と記す)に「設備投資計画」を提出した。通産省は設備投資計画が「基本計画」、「実施計画」に照らして適切な場合は、日本開発銀行や中小企業金融公庫に対して、融資の斡旋を行い、融資が実施された。設備投資の中の主要機械類は、輸入されるものは優先的に外貨割り当てを受け、輸入関税を免除され、特別償却対象として税制上の優遇措置を受けた。これらの企業が指定された部品の技術導入をする時には、速やかに外資法の認可を得られた。通産省は認可にあたり、受入企業に有利な条件を付け、契約を修正させるのが常であった。自動車技術会が昭和28年に機械工業振興資金の補助を受け、外国自動車及び部品の研究を開始し、昭和33年に自動車部品工業会が外国車部品の研究と言う形でそれを引き継いだ。これらの企業が、指定された部品の改良その他の研究開発をする時には、鉱工業試験研究費補助金を受け取ることも出来た。昭和32年に自動車部品の単純化規格作成に着手し、昭和35年に、団体規格−JASOの作成に引き継がれ、規格の整備が進められて行った。
このような政策の支援を得て、世界にあまり例のない専門部品企業群が育って行った。その大部分は、トヨタの系列企業、日産の系列企業あるいはカーメーカと全く関係のない独立部品企業であった。このように専門部品企業が自由に活動出来るようにすることが、通産省の機振法対象企業の選定条件でもあったが、トヨタと日産も系列企業が他のカーメーカに製品を納入すれば、それらの企業の生産量が増え、量産体制が整備され、品質が向上しコストも下がり、自社が製品をより低価格で入手出来るようになるのでバックアップした。
これらの専門部品企業も、生産の為の固定費はトヨタや日産向けの生産でカバーされるようになっていたので、他のカーメーカに製品を納入すれば利益になると言うことで積極的に行った。これらの企業に対するトヨタ、日産からの値引き要請は日本の乗用車工業の国際競争力を高めると言う命題達成の為に毎年繰り返され、それに応えなければならないと言う宿命を部品企業は負っていたので、こう言う形で利益を出すことは、部品企業にとっても絶対に必要なことであった。
このように専門部品企業が育って行ったので、トヨタや日産以外の日本のカーメーカも、質の良い機能部品を適正価格で入手することが出来た。これが現在でも、日本に8社もの乗用車メーカが厳しい国際競争下で生き続けている大きな要因の一つである。
この政策の評価は、機振法の体系で自動車の機能部品を作る企業を原則として2社育成し、経済成長につれて拡大する国内市場を輸入制限によって保護してそれらの企業に提供し、成果を上げたことであり、きちんとしたビジョンを作り、可能な税制、金融、補助金、各種規制等あらゆる政策を動員して、育成すべき企業を育てて行ったと言う点に注目すべきであろう。
日本の乗用車工業育成の政策についても、長い歴史がある。第一は、日本の乗用車が外国の乗用車に対して競争力がない間続けた外国為替・外国貿易管理法(昭和23年)による、輸入制限である。それと同時に、40%と言う高関税をかけ、日本の乗用車の価格と品質面の国際競争力の向上に合わせて輸入制限を緩め、関税も下げて行った。乗用車に関する技術導入についても、かなり工夫が行われた。昭和27年に、日産がオースチンから、いすゞがヒルマンから、そして日野がルノーから乗用車の技術導入を全く同一条件で行った。ここで通産省が打ち出したのが、3社それぞれの部品輸入の外貨割当金額を一定にするという政策であった。このようにすれば、国産化が進んだ企業は進まない企業より多くの車を作れる訳で、国産化の進んだ企業のマーケット・シェアはどんどん上がって行くことになった。日産は昭和31年に国産化を完了、いすゞと日野は昭和33年に国産化を完了した。
その間、トヨタは、戦前・戦時から軍用自動車生産の技術を引き継ぎ、技術導入をせずに自社技術に磨きをかけ、日産と並んでもう一方の旗頭となった。当時の通産省は、日本の乗用車工業育成にあたり、品質を向上させコストを下げるには、量産体制確立が重要であると言う見地から、カーメーカの数をなるべく少なくすると言う政策を取っていた。トヨタと日産の系列部品企業を中心とする機振法指定も、カーメーカ間でのトヨタと日産の優位を加速すると言う政策の一環でもあった。しかし、この専門部品企業育成が、日本の乗用車工業を世界トップレベルに引き上げる為に非常に役立った反面、第3位以下のカーメーカを助け、カーメーカの数を減らすと言う通産省の政策は失敗に終わらせたのは皮肉なことであった。
通産省は、カーメーカの体制整備を政策の中心に据えていたが、特に有効な政策手段を持っている訳ではなかった。しかし、輸入自由化、資本導入の自由化をひかえて、各企業とも相当な危機感を持っていたので、通産省が金融機関を通じた働きかけと、通産省の政策の双方向で、昭和41年に日産−プリンスの合併とトヨタ−日野の業務提携、翌42年には、日産−富士重工の業務提携とトヨタ−ダイハツの業務提携、更に43年、三菱−いすゞの業務提携も行われた。合併・提携を行った企業に対して日本開発銀行からの体制金融と言う特別融資が行われたが、部品企業の場合と異なり、皆大企業であったので、この体制金融によってそれがそれほど加速されたとは考えられなかった。
カーメーカ自身の合理化に非常に役立ったのは、部品企業の場合と同様に機械設備投資に対する税制上の優遇措置である。昭和32年に始まる重要機械類の関税免除制度と昭和34年に始まる企業合理化促進に基づく特別償却制度がフル活用され、世界の乗用車工業における最新設備が関税免除で輸入され、次いで工作機械メーカをはじめとする機械設備メーカが技術導入をして安く国産化したものが急ピッチに導入されて行った。
このように通産省の乗用車工業の育成に関する政策は、一部空振りをした面もあったが、結果として大成功し、世界トップレベルにまで育てることが出来たのである。この政策は、きちんとしたビジョンを持ち、それを可能な手段を動員して実現していったと言うことが評価出来るのではないかと思う。
戦後の復興プログラムの中で最優先に取り上げられたのが、発電所の建設であった。新鋭火力発電所に関して通産省が取った政策は一号機輸入、二号機技術導入による国産化と言う方式であった。この二号機技術導入による国産化と言うのは、部品輸入も認めないと言う完全国産化であった。この国産化は、日立と東芝がGEから、三菱重工と三菱電機がウエスチングハウスから技術導入して行った。
三菱は、火力発電用の機器に次いで昭和30年代にガス・タービン技術もウエスチングハウスから技術導入していた。当時は通産省が完全国産化出来るように技術導入契約を修正しない限り認可しなかったので、当然ガス・タービンの心臓部、ローターの製造技術も技術導入契約に入っていた。
しかし、昭和20年代に結ばれた火力発電機器に関するGEと日立、東芝との技術導入契約には、ガス・タービンが含まれていなかったので、ガス・タービンが注目されるようになった昭和40年代に入って技術導入が計画された。その頃には、外貨準備も充分になってきたので、技術導入は民間企業の自主性を尊重すべきと言う考え方が出てきたのである。規制緩和のはしりとして、技術導入を本来の企業の自己責任で結ぶと言う形に戻そうと言う方向になってきたのである。
この時、日立が申請したGEからのガス・タービンの技術導入契約には、ローターは輸入すると言うことで、技術導入対象にローター製造技術が入っていなかった。それまでの通産省であったら、当然ローターはガス・タービンで一番大切なものであり、ローターが含まれない技術導入など認めるべきでなく、条件変更交渉を日立にやらせるべきであると言う結論が出るところであった。その後、昭和57年に東芝もGEからガス・タービンの技術導入を行ったが、当然日立と同じ条件になった。
このように、ガス・タービンに関しては、日立、東芝がGEからローターの供給を受け、周辺機器を作って電力会社に納入しているのに対し、三菱はウエスチングハウスからの技術導入を早期に打ち切り、技術レベルは今やGEと並び世界の最高水準にあると言われている。
何が原因でこのような差が生じたかというと、第一の原因は、技術導入の条件の違いである。三菱の場合は、ローターを含めた技術を導入出来るようになっていた。その為、昭和30年代の終わりから基礎的技術を勉強することが出来たのである。
もう一つの原因は、三菱が通産省・工業技術院の大型プロジェクトでガス・タービンの技術開発に参加したことである。このプロジェクトは、高効率ガス・タービン技術研究組合が300億円近い研究開発費を投入して実施したものである。三菱重工は、パイロットプラントの取りまとめと運転及びローターの高圧タービン翼の開発を担当した。
三菱は、ウエスチングハウスから技術導入したベースの技術に大型プロジェクトで拾得した技術を加え、GEに対抗出来るガス・タービンメーカとなり、数年前に東北電力の東新潟に世界最高水準のガス・タービンと火力発電を組み合わせる複合発電システム発電所を建設した。現在ガス・タービンでは、三菱とGEの間で競争が行われている。
技術導入の条件の差がこのよな結果を生む最大の原因になった。また大型プロジェクトのような政府の技術開発も、将来を見据えて本当に役立つものを、実用化出来る企業に担当させることが大切である。ここでも、きちんとしたビジョンを持って開発を推進することが重要である。
○ 講演会等/Lectures at NISTEP
・4/16(水) 「政策評価―通産省におけるケーススタディー」 坂倉 省吾((株)パスコ副社長) ・4/24(木) 「科学技術政策評価」 川崎 雅弘(科学技術振興事業団専務理事)○ 主要来訪者一覧/Foreign Visitors to NISTEP
・4/2 Dr. Sandor Toth (駐日ハンガリー大使館 Counsellor,S&T Affairs)